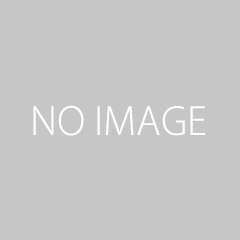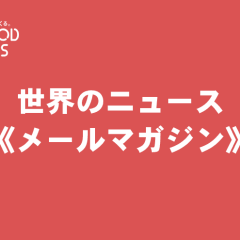--- フェアな木材を使おう ---  http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、3月は日本各地で森林火災が相次ぎ、大面積の山林や多数の建物が焼失した上、死傷者も出てしまいました。これだけの被害が日本で出たことは記憶になく、長期の乾燥と強風という気候変動の影響を感じざるを得ません。オーストラリアのNGOとのオンライン会議の最中には「近隣で山火事が発生、火が迫って来たら中断するかも」と言われ驚きました。脅威が世界中で身近な問題となっていること、生物多様性と気候変動の抑制に寄与する森林の保全と健全な森の回復が急務であることを、改めて実感しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【森林減少】
●2025.3.28 BorneoPost:EUによる木材樹種の再分類がマレーシア経済に悪影響を及ぼす可能性
マレーシアにおいて散見されるいくつかの木材樹種を、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)に基づいて、持続不可能と分類するという欧州連合(EU)の提案は、同国の経済に深刻な影響を及ぼす可能性がある。
サラワク木材協会の会長ダト・ヘンリー・ラウ氏は、この動きは国内市場と国際市場の両方へのアクセスを制限する可能性があると述べた。
メランティやセランガン・バツなどを含むこれらの木材樹種は、マレーシアの森林被覆の大部分を占めており、同国の木材取引に不可欠であると彼は述べた。
原文はこちら(英語)
 https://www.theborneopost.com/2025/03/28/eu-timber-reclassification-could-impact-malaysia-negatively/
https://www.theborneopost.com/2025/03/28/eu-timber-reclassification-could-impact-malaysia-negatively/
●2025.3.28 NHK:大規模な山林火災 気候変動が影響か 国際的な研究グループ発表
今月、日本や韓国で相次いだ大規模な山林火災について、気候変動によって気温や雨量に変化があったことが影響したと考えられるとする分析結果を国際的な研究グループがまとめました。日本の専門家は「日本は湿潤な気候なので大規模な山林火災は少ないと説明してきたが、今後増えるか注視する必要がある」と指摘しています。
これは、フランスの国立科学研究センターなどから支援を受けて、気候変動の影響について分析している国際的な研究グループ「クリマメーター」が発表しました。
分析では、愛媛県今治市と岡山市、それに韓国南部で山林火災が発生した今月21日から23日までの周辺の気象条件を分析し、過去に同様の条件だった時の気温や雨量などを調べました。
そして、1950年から1986年までの過去の期間と、1987年から2023年までの直近の期間でデータを比較したところ、この地域では最大で、雨量は3割減少した一方、気温は2度上昇し、風速は1割ほど強まっていることが分かったということです。
詳しくはこちら
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250328/k10014764031000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250328/k10014764031000.html
●2025.3.13 Euractiv:世界で最も豊かな国々が国境を越えて森林破壊を助長
世界で最も豊かな国々は、農業と林業の需要を満たすため森林破壊を引き起こし、国内よりも国際的に15倍の生物多様性の損失をもたらした。
科学雑誌「ネイチャー」に最近発表された研究で、研究者らは、経済的に発展した24か国が、国内よりも海外で種の生息域の著しい喪失を引き起こしていることを発見した。
この研究は、世界の生物多様性喪失のホットスポットを地図上に示し、豊かな国々がしばしば近隣地域の種に影響を及ぼしているだけでなく、遠隔の地の生態系にも圧力をかける可能性があることを示している。
生物多様性の喪失は主に生息地の破壊が原因となっており、人為的活動によって加速している。各国は農業や開発のために国内で皆伐する一方、森林破壊をもたらす製品を輸入することで海外の生息地の喪失にも貢献している。
原文はこちら(英語)
 https://www.euractiv.com/section/eet/news/worlds-richest-countries-fuelling-deforestation-beyond-their-borders/
https://www.euractiv.com/section/eet/news/worlds-richest-countries-fuelling-deforestation-beyond-their-borders/
●2025.3.17 ウェザーニュース:地球温暖化で世界的に山火事が多発 森林火事リスクは2050年までに50パーセント増か
世界的にも森林火災が多発しています。世界資源研究所のデータによると、20年前は世界の森林の焼失面積は400万ヘクタール前後でしたが、2023年には約1200万ヘクタールを記録し、3倍近くも増大しました。
記憶に新しいところでは今年1月に発生したアメリカ・ロサンゼルスの大規模火災があります。こうした世界的な山火事の増加も、地球温暖化が影響していると言います。
「地球温暖化が進むと、世界の多くの地域で極端な乾燥、強風が増えて、山火事の発生や拡大が起こりやすくなります。
また、気温が高いと土や植物の水分が空気中に蒸発しやすくなるので、空気の乾燥だけでなく土や植物の乾燥も進み、さらに燃えやすい状況となってしまうのです。
ロサンゼルスの場合も大船渡市と同様に、極端な乾燥、強風、落葉・落枝や下草など火災の原因となる燃料が溜まっていたことが、火災拡大の要因と考えられます。
地球温暖化が進むと北米の各地域で極端な乾燥、強風の気象が増えて、山火事が拡大しやすくなります。
詳しくはこちら
 https://weathernews.jp/s/topics/202503/120225/
https://weathernews.jp/s/topics/202503/120225/
●2025.1.28 Mongabay:ロサンゼルスの森林火災により発生した有毒な化学物質は、野生生物を脅かしている、と専門家が指摘
ロサンゼルスで現在も続いている火災により、16,000棟以上の建物が焼失したが、その多くは合成素材でできており、燃焼すると人間と野生動物のいずれにも有毒な化学物質を放出する。
家具、電化製品、フローリング、塗料、断熱材、水道管などが燃えると、ダイオキシン、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、アスベストなど、発がん性物質として知られる有毒化学物質の混合物が放出される可能性がある。人間の場合、そのような化学物質への曝露は「糖尿病、心臓病、高血圧の増加」を引き起こす可能性があり、同じことが野生生物にも当てはまると、米国アルバニー大学の公衆衛生医師であるデビッド・カーペンター博士は語った。
過去の研究により、ダイオキシンやPCBなど人工的につくられた化学物質に晒された野生動物は、深刻な健康問題を発症することが分かっている。
また、山火事は魚類や両生類の生息地に被害を与えることが多いと米国カリフォルニア州ペパーダイン大学の生物学教授リー・カッツ氏は述べた。森林が燃えると、灰が水路に流れ込むことが多く、土壌を保全する木の根がなければ川岸は簡単に浸食される。その結果、小川は土砂や瓦礫で埋まり、通常2メートルほどの深さがある水たまりは、数か月以内にわずか数センチにまで縮小する。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/short-article/2025/01/la-wildfires-release-toxic-chemicals-that-threaten-wildlife-experts-say/
https://news.mongabay.com/short-article/2025/01/la-wildfires-release-toxic-chemicals-that-threaten-wildlife-experts-say/
●2025.1.23 Mongabay:アマゾン諸国では、社会的不平等と法制度の対象外に置かれることが、インフォーマル経済を刺激している
アマゾン地域のように、階級・民族・地理により形成された階層社会では、不平等は極めて現実的で具体的な構造的障壁によって維持されている。根深い貧困と機会の欠如により、何百万人もの人々がアマゾンの辺境でより良い生活を求めるようになった。
安定した雇用を見つけられない人々は、フォーマル経済の外で商品やサービスを販売して生計を立てることを余儀なくされている。農村部でのインフォーマル経済には、規制されていない食品市場で販売される農産物を栽培し、生産物や土地に税金を払わない小規模農家が含まれる。土地利用や森林伐採に関する規制は彼らに適用されない。
近年、森林破壊の大部分は企業や大規模生産者によって引き起こされてきたが、それでもなお、小規模農家によるところが大きい。アンデス山脈の麓では、小規模農家が、長期的な持続可能性や、高速道路や貯水池などインフラ資産への侵食の影響を考慮せずに、非常に急峻な斜面の森林を日常的に皆伐している。インフォーマルの金採掘者の間でも同様の行為が横行している。ここでは環境への影響に対する軽視が甚だしく、鉱山経営者は複数の労働基準や安全基準を無視している。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/01/in-the-pan-amazon-inequality-and-informality-fuel-informal-economies/
https://news.mongabay.com/2025/01/in-the-pan-amazon-inequality-and-informality-fuel-informal-economies/
●2025.1.22 Mongabay:森林の劣化は優占樹種と炭素貯蔵量に変化をもたらす(研究)
人間の活動によって森林地帯が劣化し続けると、その減少は残された木々に重大な影響を及ぼし、森林の構造を変える可能性があることが最近の研究で明らかになった。ネイチャー・エコロジー・アンド・エボリューション誌に掲載されたこの研究は、アマゾン熱帯雨林から大西洋沿岸林まで、著しく劣化した景観を含むブラジルの6つの地域の271の森林プロットで1,207種の樹木を分析した。
この研究によると、より成長が早く、より柔らかい木質を持つ木が、より密度が高く炭素貯蔵能力の高い樹種よりも優勢になる傾向がある。研究者らは、これは、大きな種子を散布する比較的大きな野生生物が、人間が改変した景観から早い段階で姿を消し、より小さな種子を持つ木々、つまり鳥のようなより小さな散布者が森林景観を支配するようになるためだと述べている。
さらに、スイスのベルン大学の研究者で本研究の筆頭著者であるブルーノ・ピニョ氏は、問題は単に数種類の樹木が失われるということではなく、森林の重要な特性の一部が変化することだと述べた。例えば、軟材で成長の早い木は炭素貯蔵能力を失い、火災や干ばつに対する耐性が弱く、一般的に枯れるのが早い。これまでの研究によると、アマゾン熱帯雨林は1990年代に比べて2000年代に炭素を吸収する量は、30パーセント減少しているという。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/01/study-shows-degradation-changes-a-forests-tree-profile-and-its-carbon-storage/
https://news.mongabay.com/2025/01/study-shows-degradation-changes-a-forests-tree-profile-and-its-carbon-storage/
【バイオマス】
●2025.3.27 Mongabay:オランダ最大の森林バイオマス発電所が中止、森林保護活動家は歓喜に沸く
オランダ第3位のエネルギー生産者で、スウェーデンに本社を置くバタンフォール社は、2月下旬に、同国最大の木質ペレット燃焼発電所の建設計画を断念すると発表した。これを受けて、2019年に同社の計画を阻止するキャンペーンを開始した森林保護団体は勝利を宣言した。アムステルダム郊外に建設予定だったこの施設は、オランダ政府が約束した4億2480万ドルの補助金と引き換えに、最大2万4000世帯に電力を供給する予定だった。
業界誌「バイオマス・マガジン」によると、オランダは依然として欧州連合における産業用エネルギー生産向け木質ペレットの最大の輸入国である。2023年、オランダは230万トンのペレットを輸入したが、そのほぼ半分は米国からであった。
EUはおそらく世界で最も野心的な炭素排出削減目標を掲げており、2040年までに90パーセントの削減を約束している。しかし、この目標には根本的な問題がある。EUの政策では、木材燃焼を再生可能エネルギー源としている(バイオマス燃焼による煙突からの炭素排出は、国の年間排出量にカウントされない)。
EUは、この大きな炭素会計の誤りを修正する手段を提案した。2024年11月にアゼルバイジャンで開催された国連気候サミットで、オランダ人のEUの気候コミッショナー、ウォプケ・フクストラ氏は、EUが今後数年間で再生可能エネルギーのポートフォリオを3倍にすると約束した。そして、それは木質ペレットの燃焼を増やしなが、BECCS(二酸化炭素回収・貯留とバイオマス発電を組み合わせた技術)を導入して実現させるという。
しかし、この戦略には問題がある。さまざまな気候科学者によると、BECCS は実証されていない技術であるという。
森林保護活動家たちは、「私たちにできる最も重要なことは、森林を回復し、保護し、拡大することです」と言う。「気候変動が進む中、世界で何よりも多様な生物が生息する森林が必要なのです」
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/03/netherlands-largest-forest-biomass-plant-canceled-forest-advocates-elated/
https://news.mongabay.com/2025/03/netherlands-largest-forest-biomass-plant-canceled-forest-advocates-elated/
●2025.3.20 Newswitch:バイオエネの本命は「発電から熱利用へ」…燃料価格高騰、稼働率調整必要に
経済産業省・資源エネルギー庁によると、バイオマス発電の設備導入量は2023年末に656カ所・計504万9000キロワット、認定容量は1026カ所・計841万6000キロワット。バイオマス発電は1000キロワット以上が市場価格連動型制度(FIP)のみの価格体系となり、27年度から50キロワット以上はFIPのみとなる。26年度から1万キロワット以上は再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)、FIPがなくなる。
制度変更を背景に新規のバイオマス発電は減少が見込まれ、バイオマス産業社会ネットワークの泊みゆき理事長は「バイオエネルギーは発電から熱利用へと、バイオエネの本命に移っていく」と話す。
23年のバイオマス発電燃料の内訳を認定容量で見ると、トップは一般木質の179件・662万キロワット。輸入される木質ペレットとPKS(アブラヤシ核殻)が中心で、PKSは586万トン。木質ペレットは同581万トンで30パーセント以上だ。
日本の木質ペレット生産は年15万トンにとどまり、海外からの木質ペレットの安定供給に課題もある。国内林地残材は1000万立方メートルをバイオマス発電に利用し、林地残材は増える傾向にある。
バイオマス発電は国産残材などを燃料とする数千キロワット級に対し、輸入材は数万キロワット級が中心。この2年ほどで稼働した主な発電所は33件で、1万キロワット以上は15件。木質バイオマス燃料の価格が高騰し、稼働率の調整を余儀なくされている。このため、150-400度と他の再生エネにはできない高付加価値の熱エネルギーを、コージェネレーション(熱電併給)やバイオマスボイラといった産業用に利用する事業が拡大しそうだ。
詳しくはこちら
 https://newswitch.jp/p/45052
https://newswitch.jp/p/45052
●2025.3.17 DiamondOnline:三菱商事や三井物産の出資先も…木質バイオマス発電事業者の破綻や休止が相次ぐワケ
再生可能エネルギー発電の一端を担う木質バイオマス発電で、事業者の経営破綻や事業の休停止が目立つ。投資した資金を回収できず、多額の負債を抱えて法的整理や苦境に陥り、事業を他社に譲渡するケースもある。新規参入が増え、発電燃料の木材チップや木質ペレットの需要が想定外に増えたことや、ウッドショック、円安、輸送費の上昇などが重なって調達コストが上昇し、採算が悪化したことが背景にある。
脱炭素社会の実現に向け、国の施策FIT(固定価格買取制度)に沿って木質バイオマス発電は進んできたが、2012年の施行当初から状況は大きく変化した。ブームが終焉を迎えて、これから業者の淘汰が加速すると指摘する専門家も少なくない。
詳しくはこちら
 https://diamond.jp/articles/-/360936
https://diamond.jp/articles/-/360936
●2025.3.17 Novara Media:英国最大の「再生可能」発電所、環境問題を告発した従業員を解雇
再生可能エネルギー会社とされる企業が、内部告発した従業員に対し、秘密保持契約書にサインさせて退職させようとし、その後、解雇するという対応をとったことが雇用審判所で明らかになった。
この主張は、ドラックス社の元従業員の弁護士によってなされたものであり、同従業員は同社の環境への取り組みに対する懸念を訴えようとした。
ドラックス社は、この解雇が内部告発によるものではないと否定し、同社の弁護士は他のスタッフとの「信頼関係の崩壊」が原因だと主張している。
原文はこちら(英語)
 https://novaramedia.com/2025/03/17/uks-biggest-renewable-power-station-sacked-employee-who-blew-whistle-on-environmental-claims/
https://novaramedia.com/2025/03/17/uks-biggest-renewable-power-station-sacked-employee-who-blew-whistle-on-environmental-claims/
●2025.3.7 Financial Times:ドラックス社はバイオマス燃料の木材調達について「政府を欺いていた」と元ロビイストが主張
ドラックス社の元広報担当は、同社を不当解雇で訴える申し立ての中で、木質ペレットの調達に関して「市民、政府、規制当局を欺いた」と非難しました。元広報部長であるRowaa Ahmar氏は、「ドラックス社は、バイオマス用に持続可能な木材のみを調達していることを証明できず、実際には持続不可能な木材を使用している」と指摘しました。 彼女は同社の最高経営責任者(CEO)に書簡で懸念を伝えた後、最終的に解雇されたと主張している。
彼女は内部告発に関連した不当な扱いと解雇について、雇用審判所で同社およびCEOと他の幹部1名を相手取り訴訟を起こした。これは、英国政府が、2027年に現在の補助金制度が終了した後も、ヨークシャー州にある同社の主力バイオマス燃料発電所への補助金を継続することで合意したと発表した数週間後のことである。 ドラックス社は彼女の主張を否定し、この訴訟を争う構えです。
原文はこちら(英語)
 https://www.ft.com/content/b8d64846-d890-4b1e-b49d-12495f7c35e5
https://www.ft.com/content/b8d64846-d890-4b1e-b49d-12495f7c35e5
●2025.2.27 日経新聞:マツダ、溶解炉の燃料を全量バイオマスに 転換実証成功
マツダは27日、本社工場に設置されている鉄を溶かす溶解炉「キュポラ」に用いられる燃料を、燃焼時に温暖化ガスの排出量を実質ゼロにするバイオマス燃料にすべて転換する実証実験を行い、安定的な操業が確認できたと発表した。
ヤシ殻由来の材料を炭化して固形燃料にしたバイオ成型炭に全量転換して実証した。従来はCO2を排出する化石燃料を用いていた。同社の技術本部担当者によると「これまでバイオ成型炭を少量ずつ入れたり、粉状燃料にしたりして転換してきたが、100パーセントバイオ成型炭でのキュポラ操業は初めて」という。
詳しくはこちら
 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC277K50X20C25A2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC277K50X20C25A2000000/
●2025.2.25 オルタナ:日本最大のバイオマス発電所が稼働、採算はとれるか
2024年12月末、山口県下関市の長府バイオマス発電所が稼働し始めた。輸入する木質ペレットを燃料とする出力規模7万4950キロワットの日本最大級のバイオマス発電所だ。だが同じ12月に、静岡県富士市の鈴川エネルギーセンター発電所が発電を停止したことは、あまり知られていない。
二つの発電所を持っていた北海道バイオマスエネルギー社は、昨年10月に清算した。今年1月には和歌山県の新宮フォレストエナジー社も破産手続に入った。バイオマス発電所は、全国各地で経営が行き詰まっており、停止や経営陣の交代などが相次いでいる。
その背景には、燃料価格の高騰がある。主な燃料としてきた木質ペレットやチップ、PKS(ヤシ殻)は、いずれも輸入しているが、原材料不足や規制強化などの問題から生産減と値上げが続くのだ。円安も価格を引き上げている。
詳しくはこちら(一部有料会員記事)
 https://www.alterna.co.jp/149987/
https://www.alterna.co.jp/149987/
●2025.2.10 The Guardian:それは一時的な命綱だ:ドラックス社に対する決定は労働党政権による環境政策の試金石
本日月曜日、政府は、ドラックス社への補助金支給が終了する2027年以降も、ドラックス発電所でのバイオマス燃焼に対する補助金支給を継続すると発表した。このニュースは環境保護活動家にとって打撃となった。
しかし、穏健な見方をする専門家もいる。この政府の和解案は、補助金を半減、補助期間を4年間に制限し、事業の持続可能性に厳しい新条件を課している。英国のシンクタンク、E3Gのキャンペーンディレクター、エド・マシュー氏は「同社の遺産は高い排出量と森林破壊であり、ドラックスの廃業は早ければ早いほど良い」と述べた。「この一時的な命綱は、同社の環境対策への信頼がズタズタに引き裂かれているという事実を隠すものではない。補助金の半減は、確固たる不信任投票だ。」
ただ、ドラックス社は英国の電力のかなりの部分を供給しており、総電力の4パーセントから6パーセントを占めている。専門家らは、英国はドラックスなしでも2030年までに電力部門を脱炭素化するとの目標を達成できると示しているが、その「可能性」は多くの「もし」に基づいている。
グリーンピースの主任研究員ダグ・パー氏は、「2027年(現在の補助金が切れる年)にドラックスを廃止するのは勇気ある決断だろう」と認めた。同氏はバイオマス発電には断固反対だが、代替のグリーン発電の建設が間に合わなければ政府は電力不足に陥る可能性があることは認めている。同氏は、新たな和解案は「完璧ではないが、もっと悪くなる可能性もあった」と述べた。
原文はこちら(英語)
 https://www.theguardian.com/environment/2025/feb/10/while-some-green-activists-decry-drax-decision-others-take-a-softer-view
https://www.theguardian.com/environment/2025/feb/10/while-some-green-activists-decry-drax-decision-others-take-a-softer-view
【違法伐採問題】
●2025.2.3 Mongabay:カンボジア、違法伐採について報道したモンガベイのジャーナリストの再入国を拒否
ジャーナリストのジェラルド・フリン氏は、有効なビザと労働許可証を持っていたにもかかわらず、2025年1月5日にカンボジアへの入国を禁止された。入国管理局は、2024年2月に提出された書類に誤りがあったとして、同氏が不正なビザ申請をしたと主張、同氏をブラックリストに掲載した。
これは、カンボジアの代表的な炭素オフセットプロジェクトである南部カルダモンREDD+プロジェクトの有効性を疑問視する、フランスの放送局フランス24が制作したドキュメンタリーが11月22日に放映され、フリン氏が重要な情報源として取り上げられた直後のことだった。カンボジアの環境省とREDD+プロジェクト推進団体の野生生物同盟は、フランス24のドキュメンタリーを「フェイクニュース」として否定する声明を発表した。
フリン氏は2022年から2023年の間、ピュリッツアー・センターの熱帯雨林調査ネットワーク(RIN)フェローとして、カンボジアの刑務所を拠点とする伐採事業を明らかにし、政府高官が違法木材の密売人であること等を暴露していた。フリン氏の報道は、カンボジアの天然資源の略奪から利益を得ている政界およびビジネス界のエリートたちの正体を幾度も暴いてきた。
また、環境問題や土地の権利問題を取材していたカンボジア人ジャーナリストのチュウン・チェン氏が、 2024年12月にシェムリアップ州で射殺された。これはジャーナリストのオウク・マオ氏が2024年9月に保護地域での違法伐採の罪に問われた直後のことだった。
同国におけるジャーナリストへの嫌がらせについての情報を提供している人権団体は、2024年を通じて脅迫、威嚇、リーガルハラスメント、身体的暴力の件数が急増したと報告した。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/02/cambodia-denies-re-entry-to-mongabay-journalist-who-reported-on-illegal-logging/
https://news.mongabay.com/2025/02/cambodia-denies-re-entry-to-mongabay-journalist-who-reported-on-illegal-logging/
●2025.2.18 Reuters:アマゾンで違法伐採を標的に一斉摘発に乗り出す(ブラジル)
ブラジルの環境保護当局は、ここ数週間、アマゾンの熱帯雨林で最も伐採が行われてきた地域の一つをターゲットとした作戦で、トラック5,000台分以上の木材を押収したと、当局がロイター通信に語った。
この摘発により、アマゾナス州、パラ州、ロンドニア州で、「マラヴァリャ作戦」と呼ばれる1年間にわたるプロジェクトが始まった。政府はマラヴァリャ作戦が過去5年間で最大の作戦になると予想している。
この作戦を主導した環境保護庁Ibamaは、2週間にわたる摘発で約12カ所の製材所を閉鎖、総額270万ドルの罰金を科した。
作戦の目的は、国内で最も森林破壊率が高い保護区や先住民族の土地での違法伐採を抑制することだと、Ibamaの環境保護責任者ジャイル・シュミット氏は語った。
原文はこちら(英語)
 https://www.reuters.com/world/americas/brazil-targets-illegal-logging-major-amazon-raids-2025-02-17/
https://www.reuters.com/world/americas/brazil-targets-illegal-logging-major-amazon-raids-2025-02-17/
【森林保全】
●2025.3.11 IdeasForGood:マレーシア、土地開発前に地元の「完全な同意」義務化へ。先住民の森林を守る
日本が木材の供給を国外に頼っていることは、多くの人が知っているだろう。特に、ベトナムやEU、中国からの輸入が多いが、実は合板の主な輸入先の一つがマレーシアである。マレーシアの熱帯雨林の広葉樹は、「薄く、強度が高く、滑らか」という合板に適した特徴を持っているからだ。
そんなマレーシアではかつて、ボルネオ島北西部のサラワク州で、先住民の強い反対を無視した、政府関係者の賄賂までも絡む大規模な森林伐採がおこなわれ、その木材の主な輸出先が日本であることが明らかになった。先住民の意に反した森林伐採は決して他人事ではなく、私たちの身の回りに潜む現実であるかもしれない。
この現状に、先住民の人々は立ち向かい続けてきた。そしてついに、彼らが長きにわたって政府に求めてきた権利が現実のものになろうとしている。
2025年2月初旬、マレーシア首相府法務局が公開した「ビジネスと人権に関する国家行動計画の草案」において、土地の開発前に地域コミュニティの完全な同意を得ることが義務化される計画が示されたのだ。具体的には、2030年までに「自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(以下、FPIC)」の国家ガイドライン作成と、国全体で標準化するための法律制定が計画されている。
詳しくはこちら
 https://ideasforgood.jp/2025/03/11/malaysia-law-for-full-consent/
https://ideasforgood.jp/2025/03/11/malaysia-law-for-full-consent/
●2025.1.17 Mongabay:400年続くエチオピアの伝統農法を守る: 長老ゲハノ・グチョイル氏へのインタビュー
エチオピア南部では、コンソ族が400年もの間、半乾燥地帯での農業に欠かせない石積みの段々畑を維持してきた。
ユネスコに登録されているこの農法は、土壌浸食を防ぎ、水を節約し、農業の生産性を高めるのに役立つ。その中心にいるのは、コンソ族の長老たちで、彼らは段々畑に関する知識を若い世代に伝える上で重要な役割を果たしている。
コンソ族は、雨量が不安定で、急峻で土壌侵食が起こりやすい地域に住んでいる。長年にわたり、彼らは、アグロフォレストリー、雨水利用、段々畑、ふん尿の堆肥化などの複雑なシステムを開発してきた。この農業システムは、段々畑、土壌と水の管理、林業を組み合わせたものである。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/01/the-elder-sustaining-a-400-year-old-ethiopian-farming-tradition-interview-with-gehano-nekayto/
https://news.mongabay.com/2025/01/the-elder-sustaining-a-400-year-old-ethiopian-farming-tradition-interview-with-gehano-nekayto/
【パーム油問題】
●2025.1.24 Mongabay:オランウータンの保護区から違法パーム油があなたの近所の店にやってくる
オランウータンが多く生息していることで知られるインドネシア・スマトラ島北端のラワ・シンキル野生生物保護区で、違法な森林伐採が記録的なレベルまで急増していると報じられている。米国を拠点とするNGO、レインフォレスト・アクションネットワーク(RAN)が発表した報告書によると、同保護区の2,577ヘクタールの森林が2015年以降伐採され、2021年から2023年にかけて森林破壊が劇的に増加したという。RANは、この地域を監視してきた過去10年間で、このような森林破壊の速度は前例のないものだと述べた。
また、この破壊が、森林破壊防止規則(EUDR)の森林破壊ゼロの期日の後に発生しているため、森林破壊ゼロの約束と世界的な保全活動の有効性の両方について懸念が生じている。EUDRが今年末に適用されれば、パーム油を含む特定の商品のEUへの輸入は、2020年12月31日以降に森林破壊された土地から産出されたものでないことが求められるのである。
報告書は、違法に伐採された土地で栽培されたアブラヤシ由来のパーム油が、プロクター・アンド・ギャンブル、ネスレ、モンデリーズ、ペプシコ、日清食品など大手消費財ブランドのサプライチェーンに流入している恐れがあると警告した。
一部のブランドやパーム油取引業者は、この報告書を受けて、違法農園からの調達を停止したり、調査を開始した。しかし、これらの措置が野生生物保護区での違法な伐採を止めるのに十分かどうか疑問視されている。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/01/coming-to-a-retailer-near-you-illegal-palm-oil-from-an-orangutan-haven/
https://news.mongabay.com/2025/01/coming-to-a-retailer-near-you-illegal-palm-oil-from-an-orangutan-haven/
【コミュニティ】
●2025.1.20 Mongabay:先住民コミュニティが都市部の洪水を防ぐために山林を復元(フィリピン)
フィリピンのカラトゥンガン山保護区の先住民コミュニティは、数十年にわたる商業伐採と農業によって失われた在来植物を回復させるため、2015年以来植樹キャンペーンを実施している。熱帯雨林化として知られるこの取組は、洪水緩和などの重要な生態系サービスの活性化を目指しており、下流の都市部に利益をもたらすとともに、復元を進めるコミュニティにインセンティブを与えることをも目的としている。
この「熱帯雨林農業(アグロフォレストリー)」は、地元のNGOであるザビエル科学財団(XSF)が実施している生態系サービスへの支払いイニシアチブと組み合わされている。
熱帯雨林化プログラムは、コミュニティグループが主導、在来植物に関する彼らの知識を活用しており、政府が数十年にわたって一元管理してきた外来種の植林に基づく森林再生活動からの転換を目指している。
2021年から2024年にかけて、約40世帯がプロジェクトに土地を登録し、熱帯雨林化を目指す農場の植林と管理に対して、各世帯が少なくとも1ヘクタールあたり1,029ドルを得ている。
XSFの事務局長ロエル・ラバネラ氏は、先住民族タラアンディグの組織MILALITTRAと2014年に開始、試験的に実施しているこの取組は、民間部門と先住民コミュニティを結び付け、企業がコミュニティによる森林の保護・保全の取組に資金を提供するものだと述べている。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/01/philippine-indigenous-communities-restore-a-mountain-forest-to-prevent-urban-flooding/
https://news.mongabay.com/2025/01/philippine-indigenous-communities-restore-a-mountain-forest-to-prevent-urban-flooding/
●2025.1.16 Mongabay:鉱山会社は、孤立した先住民族が住む立ち入り禁止区域を検討すべきか?(解説)
再エネ技術に使われている重要な鉱物の無責任な採掘は、世界で最も脆弱な集団の一つである、自発的に孤立している先住民族の存在を脅かす可能性がある。
エネルギー転換に伴い重要な鉱物の需要が高まるにつれ、尊重を重視した、権利に基づく採掘アプローチの必要性がこれまで以上に高まっている。このアプローチは、影響を受ける先住民族の土地で採掘が行われるべきかどうか、またどのように行われるべきか、彼らがその利益をどのように分配するかについての決定に対する、彼らの意味のある包括的な関与と参加に依存している。
しかし、自発的に孤立している先住民族にとっては、関与や参加は不可能であり、国際的人権枠組は、そのようなコミュニティは自らの領域に影響を及ぼすプロジェクトに同意することができない、と述べている。したがって接触禁止の原則は彼らを保護する基礎となっている。
テスラのような企業は、未接触部族が住む立ち入り禁止区域の設置を検討している。こうした区域を設けるという考えはますます現実的になってきている。著者の国際金属鉱業評議会(ICMM)のダニエル・マーティン氏は、企業が行うべき最も重要なことは、鉱山開発の初期段階から閉鎖に至るまで、厳格な人権デューデリジェンスを実施することだと述べている。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/01/should-mining-companies-consider-no-go-zones-where-isolated-indigenous-peoples-live-commentary/
https://news.mongabay.com/2025/01/should-mining-companies-consider-no-go-zones-where-isolated-indigenous-peoples-live-commentary/
●2025.1.16 Mongabay:石油が採掘されてきたニジェールデルタで、オゴニの女性たちがマングローブと生活を回復させる
女性主導の森林再生の取組みにより、深刻な荒廃に陥っているナイジェリア・ニジェールデルタに、活着率の高いマングローブ数百万本が植えられた。デルタ地帯のオゴニランドに住むオゴニ族は、数十年にわたり、度重なる石油の流出、伐採、外来種・ニッパヤシの繁茂による数千本ものマングローブの破壊に直面してきた。
特に女性の食料や生活に影響が出ている。オゴニの女性たちは、海岸で甲殻類を採取して販売する役割を担っていることが多いが、これらの生き物は原油に晒されて大きな影響を受けている。
失われたものを取り戻し、オゴニ族の女性の自律を回復する試みとして、地元の環境・ジェンダーの権利団体であるロキアカ・コミュニティ開発センターは、2016年以来、石油流出やその他の脅威の影響を受けた女性たちをマングローブ林再生の研修に受け入れている。
ロキアカは、オゴニ族の4つのコミュニティで約300人の女性にマングローブの植林を指導してきた。彼女たちは、2018年に復元プロジェクトが始まって以来、ボド・クリーク、ヤアタ、ティーナマの湿地に260万本のマングローブの木を植えてきた。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/01/ogoni-women-restore-mangroves-and-livelihoods-in-oil-rich-niger-delta/
https://news.mongabay.com/2025/01/ogoni-women-restore-mangroves-and-livelihoods-in-oil-rich-niger-delta/
【日本は今!】
●2025.3.27 日刊建築工業新聞:国内建築用木材、半世紀ぶり自給率50パーセント超に/中高層の木質化促進
2023年度の国内建築用木材の自給率が半世紀ぶりに50パーセントを上回ったことが、政府の集計で分かった。総需要約2926万立方メートルに対し、国内生産量が55.3パーセントに当たる約1618万立方メートルとなった。政府は4階建て以上の中高層建築物の木造・木質化を促すため、建築基準法の構造規制を4月に緩和するなど木材利用促進策をさらに展開する。
詳しくはこちら
 https://www.decn.co.jp/?p=172512
https://www.decn.co.jp/?p=172512
●2025.3.26 読売新聞:CO2排出量取引推進 オンラインマーケット 都が開設企業無料
都は25日、都内外の企業がCO2(二酸化炭素)の排出量を取引できる「東京都カーボンクレジットマーケット」をオンライン上に開設した。CO2削減の取り組みを支援し、脱炭素化を進める狙いがある。都によると、自治体による排出量取引市場の運用は初めて。
詳しくはこちら
 https://www.yomiuri.co.jp/local/tokyo23/news/20250325-OYTNT50228/
https://www.yomiuri.co.jp/local/tokyo23/news/20250325-OYTNT50228/
●2025.3.23 日経新聞:2050年、桜舞う卒業式は幻? 温暖化で開花サイクルに乱れ
桜に異変が起こっている。開花が遅れたり、逆に早まったりし、桜のイベントの開催者やツアー会社は頭を抱える。地球温暖化の影響が大きいとみられ、2050年ごろには九州の一部地域で桜が開花しない可能性がある。桜が舞う卒業式など1億人が思い描く春のイメージは幻と消えかねない。
詳しくはこちら(一部会員限定記事)
 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA28AA00Y5A220C2000000/?msockid=144ac6910a416a8e0c7dd5f60bab6b23
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA28AA00Y5A220C2000000/?msockid=144ac6910a416a8e0c7dd5f60bab6b23
●2025.3.19 HousingTribuneOnline:木住協 国産材利用調査、52.7パーセントで過去最高更新
木住協が3月4日、2005年より3年ごとに継続して実施している「木造軸組工法住宅における国産材利用の実態調査報告書」の最新版を公表した。2023年度に完工した住宅が対象で、住宅供給会社93社、プレカット会社84社から回答を得た。回答社の年間供給住宅数の合計は、住宅供給会社が5万6957戸、プレカット会社が12万3194戸で、同年度の全国の木造軸組工法着工戸数の34万9213戸に対し、それぞれ16.3パーセント、35.3パーセントとなっている。
住宅の注文形態を戸数割合で見ると、戸建注文住宅63.5パーセント、戸建建売住宅36.5パーセントとなっており、令和2年度と比べ建売住宅が16.7ポイントと大きく増加したが、今回の回答社に年間供給戸数が1万1000戸超の大手建売メーカーが新たに加わったことが影響したと考えられるとした。
詳しくはこちら
 https://htonline.sohjusha.co.jp/700-060/
https://htonline.sohjusha.co.jp/700-060/
●2025.3.19 PR TIMES:東海圏を中心とする持続的な森林管理や地域脱炭素化の実現に向けた業務提携
株式会社地域創生Coデザイン研究所は、株式会社名古屋銀行と、東海圏を中心とする持続的な森林管理や地域脱炭素化の実現に向けて業務提携し、森林資源を中心とした地域資源活用によるカーボン・クレジット創出や民間企業へのカーボン・クレジット流通と普及啓発に取り組むことで、地域の脱炭素化実現をめざすとともに、持続的な森林管理を通じた地域創生への貢献をめざす。
詳しくはこちら
 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000151841.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000151841.html
●2025.3.5 日経クロステック:再造林率日本一に宮崎県が挑む
資源循環型林業を確立しようと、林業県の1つである宮崎県が動き出した。再造林率90パーセント以上の達成を目指し、再造林に関する補助金を積み増す一方、伐採・造林事業者らのネットワークを県内8地域に立ち上げるのを後押しする。2024年7月に施行した都道府県初の再造林推進条例を後ろ盾に、2024年度予算においてグリーン成長関連に8億7000万円を計上した。
詳しくはこちら
 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00461/021200094/
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00461/021200094/
●2025.2.28 農林水産省:令和5年林業産出額
林業産出額は、平成25年以降増加傾向で推移してきたが、令和5年は、製材用素材等の価格の低下や生産量の減少等から、前年に比べ230億円(4パーセント)減少し、5,563億円となった。
詳しくはこちら
 https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/ringyo/r5/index.html
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/ringyo/r5/index.html
●2025.2.27 NHK:シカ被害 都道府県向け新たなガイドライン案示す 環境省
生息数が増え山林の植物が食べ尽くされるなど、被害が深刻化しているシカへの対応を話し合う環境省の専門家会議が開かれ、地域別に目標を立てて被害の大きい場所で優先的に捕獲にあたることなどを都道府県向けのガイドラインに新たに盛り込む案などが示されました。
環境省によりますと国内のシカの生息数は2022年度におよそ246万頭と推計され、30年余りで8倍以上に増えています。
山林の植物がシカに食べ尽くされるなど被害が深刻化しているため、国は2028年度までに生息数を半減させる目標を掲げ、捕獲を進めていますが、生息数は横ばいで、被害をいかに食い止めるかが課題になっています。
詳しくはこちら
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250227/k10014734871000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250227/k10014734871000.html
【中露情報】
●2025.3.20 中華網:中国が米国からの原木輸入一時停止を発表
中国税関総署は3月4日、米国から輸入された原木からキクイムシやカミキリムシなどの植物検疫の対象となる病害虫が検出されたと発表した。有害生物の侵入を防ぎ、国内の農林業と生態系の安全を守るため、「中華人民共和国生物安全法」、「中華人民共和国輸出入動植物検疫法」およびその実施条例、国際植物検疫措置基準などの関連規定に基づき、税関総署は同日から米国産原木の輸入を一時停止することを決定した。
原文はこちら(中国語)
 https://news.china.com/socialgd/10000169/20250304/48040680.html
https://news.china.com/socialgd/10000169/20250304/48040680.html
●2025.2.27 Interfax-Russia:木材2億5000万ルーブル相当の密輸事件の被告が沿海地方の裁判所に出廷
ロシア連邦検察総局は、極東において2億5000万ルーブル(約297万ドル)以上の木材の密輸に関連した刑事事件の訴えを承認した。
この捜査によると、被告らは2019年から2021年にかけて、特に高価な樹種とされるモンゴリナラとヤチダモを、国境を越えて違法に輸送したとされる。
原文はこちら(露語)
 https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/figuranty-dela-o-kontrabande-lesa-na-250-mln-rubley-predstanut-pered-sudom-v-primore
https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/figuranty-dela-o-kontrabande-lesa-na-250-mln-rubley-predstanut-pered-sudom-v-primore
●2025.1.25  argumenti.ru:ハバロフスク地方が極東における森林再生のリーダー的存在に
argumenti.ru:ハバロフスク地方が極東における森林再生のリーダー的存在に
ハバロフスク地方は2024年、ウラジミル・プーチン大統領が主導して創設された国家プロジェクトである「エコロジー」に含まれる地域プロジェクトである「森林保護」の枠組みにおいて記録的な成果を示した。ハバロフスク地方林業・木材加工省によると、同地方内で再生された森林面積は、伐採された、あるいは枯死した森林地帯のほぼ2倍にあたる、195.7パーセントを超えるとされている。
原文はこちら(露語)
 https://argumenti.ru/society/2025/01/935694
https://argumenti.ru/society/2025/01/935694
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆4/9(水)開催 原生林を燃やす日本のバイオマス発電~カナダの燃料生産地 視察報告会
 https://www.gef.or.jp/news/event/250409bcforest_biomass/
https://www.gef.or.jp/news/event/250409bcforest_biomass/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本のバイオマス発電の主要燃料である木質ペレットの輸入元第2位はカナダで、そのほとんどがブリティッシュコロンビア州で生産されています。現地に広がる原生林は、絶滅危惧種の森林トナカイなどの生息地であり、樹木や土壌に膨大な炭素を蓄え、先住民族の暮らしを支えてきました。
しかし、毎年、東京の面積に匹敵する20万ヘクタールが皆伐され続け、その一部が日本に輸出されバイオマス火力発電の燃料として燃やされています。
わたしたちはバイオマス燃料の生産地で起きている問題を理解し、日本に伝えるため、現地調査を行ってきました。昨年9月にはパタゴニア環境助成金の支援の下、自然写真家・伊藤健次さん、持続可能な森林経営を行っている速水林業代表・速水亨さんらと共にBC州の視察を行いました。
この報告会では、今回現地で確認した原生林の伐採やペレット工場周辺の状況をお伝えし、海外の貴重な森林を燃料にするバイオマス発電を「再エネ」として使うことの課題について考えます。
【日時】2025年4月9日(水)16:00-17:30
【開催方法】オンライン(Zoomウェビナー)
【参加費】無料
【お申し込みフォーム】
 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aGyZwEAASBu2XxdzHnnptQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aGyZwEAASBu2XxdzHnnptQ
【プログラム】
動画:【カナダの森林学者が語る】原生林を燃やす私たちの電気
発表①「日本の輸入木質バイオマス発電の現状」 鈴嶋克太(地球・人間環境フォーラム)
発表② 伊藤健次氏
発表③ 速水亨氏
コメント 石井徹氏
質疑応答
【主催・お問合せ】
一般財団法人 地球・人間環境フォーラム (担当:鈴嶋・飯沼、E-mail:event[a] gef.or.jp)
gef.or.jp)
【協力】
パタゴニア日本支社、NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク、ウータン・森と生活を考える会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆第85回フェアウッド研究部会「森の入り口から出口までをつなぐやまとわの挑戦」
 https://fairwood.jp/event/250417/
https://fairwood.jp/event/250417/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「森をつくる暮らしをつくる」を理念にかかげ、拠点を長野・伊那市に置く株式会社「やまとわ」。家具づくりや、薪ストーブ・ウッドボイラーなど木のエネルギー利用地域材を使った家づくりから、馬糞堆肥を使った循環農業の促進、15年後の未来を描いたゾーニングマップ“SATOYAMA CONCEPT MAPs”をもとに地元の関係者とともに進める鳩吹山での森づくりなど、森と暮らしの新しい関係性をつくる多様な事業を展開しています。
同社の取締役の奥田悠史さんを講師に迎えて、森の入り口から出口までをつなぎながらトータルデザイン、実践する「森の企画室」をご紹介いただき、やまとわと奥田さんが日本の森そして林業の未来をどう考えているのかを伺います。
「木の流れから、未来をつくる」を掲げるフェアウッド・パートナーズが開催する研究部会は85回目の開催です。ぜひご参加ください。
【開催概要】
日時:2025年4月17日(木)18:00~19:30(開場:会場は15分前、オンラインは5分前)
場所:ハイブリッド(zoom×地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)東京都渋谷区神宮前 5-53-70 国連大学ビル 1F)
参加費: 1,500円(懇親会費別)
定員:会場25名、オンライン90名
※懇親会は会場参加者のみご参加いただけます。当日の受付の際にお申込み・お支払いを承ります。
※会議URL:お申込みいただいた方に後日ご案内いたします。
※お申込みいただいた方で希望のある場合は、当日の録画アーカイブを後日、期間限定でご覧いただくことが可能です。
【プログラム】(敬称略、内容は予告なく変更することがあります)
第1部:講演(18:00~19:30 質疑含む)
講師:奥田 悠史/株式会社やまとわ 取締役・企画室長、森林ディレクター
第2部:懇親会(会場参加者の希望者のみ、別会場にて開催予定)
【講師プロフィール】(敬称略)
奥田 悠史(おくだ・ゆうじ)/株式会社やまとわ 取締役・企画室長、森林ディレクター
大学では農学部森林科学を専攻。バックパッカー世界一周を経てライターとして地域の農家さんを取材する毎日を過ごし、デザイン事務所を立ち上げる。2016年に「森をつくる暮らしをつくる」をミッションに掲げる(株)やまとわを立ち上げる。
暮らしの提案が森と暮らしをつないでくことを目指して、森づくりからモノづくり、自然×クリエイティブ事業などに取り組んでいる。2023年より伊那谷の農と森のインキュベーション施設 inadani seesの企画運営も担当。
【お申込み】
お申し込みフォーム( https://fw250417.peatix.com)よりお申し込みください。
https://fw250417.peatix.com)よりお申し込みください。
フォームがご利用できない場合、「第85回フェアウッド研究部会参加希望」と件名に明記の上、1)お名前、2)ふりがな、3)ご所属(組織名及び部署名等)、4)Eメールアドレス、5)参加方法(会場またはオンライン)、6)(会場参加の場合)懇親会の出欠を、メールにてinfo@fairwood.jp まで送付ください。
【主催】
国際環境 NGO FoE Japan、地球・人間環境フォーラム、佐藤岳利事務所
【後援】
マルホン
【助成】
緑と水の森林ファンド
【問い合わせ】
FoE Japan(担当:佐々木)
 http://www.foejapan.org、info@foejapan.org
http://www.foejapan.org、info@foejapan.org
地球・人間環境フォーラム(担当:坂本)
 http://www.fairwood.jp、info@fairwood.jp
http://www.fairwood.jp、info@fairwood.jp
※テレワーク推進中のため、メールにてお問合せお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆改正クリーンウッド法の適正な施行・運用に向けた提言
 https://fairwood.jp/document/241001proposalcwa
https://fairwood.jp/document/241001proposalcwa
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
近年、国際社会では気候変動対策や生物多様性保全の観点から包括的な森林減少・劣化対策の必要性への認識が定着しています。2024年12月から施行される欧州森林減少防止規則(EUDR)も、違法伐採対策に主眼を置いていた前身の欧州木材規則(EUTR)を大幅に刷新しました。
日本の違法伐採対策法であるクリーンウッド法も改正され、2025年4月に施行されますが、違法伐採対策から森林減少対策へ推移した国際社会との課題認識の乖離が見られます。
日本政府による違法伐採対策によって日本の木材市場から違法リスクおよび森林減少リスクの高い木材が取り除かれ、世界の森林保全に寄与することを期待し、責任ある木材利用の実現に向けて提言します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆かわさきFM "TO THE NATURE"で紹介されました!
 https://www.youtube.com/watch?v=NOxPsgWUXcQ
https://www.youtube.com/watch?v=NOxPsgWUXcQ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
フェアウッド・パートナーズの事務局団体の一つである地球・人間環境フォーラム活動がFMかわさきの"TO THE NATURE"で紹介されました。
「カナダの原生林を燃やす日本の木質バイオマス 本当に二酸化炭素削減になるのだろうか?森の役割、豊かな生態系の価値。みんなで考えよう!」と題して、8月16日に放送されました。
Youtubeで視聴可能です。ぜひお聞きください。
 https://www.youtube.com/watch?v=NOxPsgWUXcQ
https://www.youtube.com/watch?v=NOxPsgWUXcQ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・みなさんの知人、友人、ご家族の方にもこのメールマガジンをお知らせしてください。メールマガジンの登録、バックナンバーはこちらです。
 http://www.fairwood.jp/news/newsbk.html
http://www.fairwood.jp/news/newsbk.html
・本メールマガジンの記事について、無断転載はご遠慮ください。
ただし、転載許可の表記のある場合を除きます。
・本メールマガジンに関するご意見・ご感想などは下記のEmailにお寄せくだ さい。お待ちしております。e-mail: info@fairwood.jp
発 行 : フェアウッド・パートナーズ  http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp
編 集 : 坂本 有希/三柴 淳一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
![]() http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp![]() https://www.theborneopost.com/
https://www.theborneopost.com/![]() https://www3.nhk.or.jp/news/
https://www3.nhk.or.jp/news/![]() https://www.euractiv.com/
https://www.euractiv.com/![]() https://weathernews.jp/s/
https://weathernews.jp/s/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://newswitch.jp/p/45052
https://newswitch.jp/p/45052![]() https://diamond.jp/articles/-/
https://diamond.jp/articles/-/![]() https://novaramedia.com/2025/
https://novaramedia.com/2025/![]() https://www.ft.com/content/
https://www.ft.com/content/![]() https://www.nikkei.com/
https://www.nikkei.com/![]() https://www.alterna.co.jp/
https://www.alterna.co.jp/![]() https://www.theguardian.com/
https://www.theguardian.com/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://www.reuters.com/world/
https://www.reuters.com/world/![]() https://ideasforgood.jp/2025/
https://ideasforgood.jp/2025/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://www.decn.co.jp/?p=
https://www.decn.co.jp/?p=![]() https://www.yomiuri.co.jp/
https://www.yomiuri.co.jp/![]() https://www.nikkei.com/
https://www.nikkei.com/![]() https://htonline.sohjusha.co.
https://htonline.sohjusha.co.![]() https://prtimes.jp/main/html/
https://prtimes.jp/main/html/![]() https://xtech.nikkei.com/atcl/
https://xtech.nikkei.com/atcl/![]() https://www.maff.go.jp/j/
https://www.maff.go.jp/j/![]() https://www3.nhk.or.jp/news/
https://www3.nhk.or.jp/news/![]() https://news.china.com/
https://news.china.com/![]() https://www.interfax-russia.
https://www.interfax-russia.![]() argumenti.ru:
argumenti.ru:![]() https://argumenti.ru/society/
https://argumenti.ru/society/![]() https://www.gef.or.jp/news/
https://www.gef.or.jp/news/![]() https://us02web.zoom.us/
https://us02web.zoom.us/![]() gef.
gef.![]() https://fairwood.jp/event/
https://fairwood.jp/event/![]() https://fw250417.
https://fw250417.![]() http://www.foejapan.org、info@
http://www.foejapan.org、info@![]() http://www.fairwood.jp、info@
http://www.fairwood.jp、info@![]() https://fairwood.jp/document/
https://fairwood.jp/document/![]() https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?![]() https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?![]() http://www.fairwood.jp/news/
http://www.fairwood.jp/news/![]() http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp