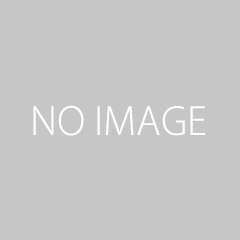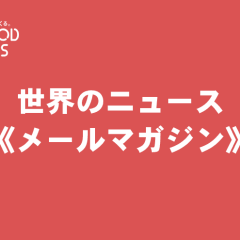--- フェアな木材を使おう ---  http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
霊長類研究者のジェーン・グドール氏が他界しました。チンパンジーの研究だけでなく環境問題への取組みでも知られ、亡くなる直前まで世界を回って講演を続けていました。
昨年のインタビューでは「自然を再生し、既存の森林を保護するために、私たちがもっと努力すれば、状況の改善につながる」と話していたそうです。来月にはブラジルでCOP30が開催され、熱帯林の保全も大きなテーマの一つとなります。あと5%の消失で取返しのつかないティッピングポイントを超えると言われるアマゾン熱帯林。私たちは森と生活と未来を守るために、舵を切ることができるでしょうか。ジェーン・グドール氏もその行方を見守っていることでしょう。
今回は事務局の不備で発行が遅れましたことをお詫び申し上げます。また今年前半にお伝えしきれなかった記事が複数含まれておりますこと、ご容赦ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【森林減少】
●2025.9.25 ESGグローバルフォーキャスト:EU、森林破壊防止規則の開始をさらに1年延期へ 欧州メディア報道
欧州委員会が森林破壊防止規則(EUDR:the Regulation on Deforestation-free Products)の適用開始を、2025年末からさらに1年延期する検討に着手したことが明らかになった。25年9月23日付の欧州政策メディア「ユーラクティブ」は、欧州委員会で環境保護を担当するジェシカ・ロスウォール委員が22日、記者団に1年延期を公表したと報じた。
ユーラクティブは、「欧州委員会が世界最大のパーム油輸出国であるインドネシアとの貿易交渉を終えた後に発表された」と指摘している。欧州委員会は9月23日にインドネシア政府と包括的貿易連携協定と投資保護協定を締結したことを発表している。また、8月21日の米EU共同声明では、EUDRについて米国の懸念に配慮し見直す方針が盛り込まれていた。
詳しくはこちら
 https://project.nikkeibp.co.jp/ESG/forecast/atcl/news/092500064/
https://project.nikkeibp.co.jp/ESG/forecast/atcl/news/092500064/
●2025.9.16 Mongabay:衛星データはミャンマーの希土類鉱業のホットスポットで森林破壊の急増を示している
モンガベイが収集した情報筋と衛星画像によると、ミャンマーのカチン州では、ほとんど規制されていない希土類鉱物の採掘が森林、河川、そして人間の健康に大きな損害を与えている。
2018年から2024年にかけて、採掘が集中している郡区では亜熱帯湿潤林の樹木被覆面積約32,720ヘクタールが失われた。
研究者らによると、カチン州産の希土類鉱物はすべて中国の磁石製造業者に送られ、電気自動車、風力タービン、電子機器の世界的に有名なメーカーに供給されているという。
ミャンマーで続く内戦は、この問題を複雑化させる要因となっている。カチン州の鉱山を支配する武装勢力は現在、鉱物を輸入する中国企業や当局と条件の再交渉を進めている。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/09/satellite-data-show-burst-of-deforestation-in-myanmar-rare-earth-mining-hotspots/
https://news.mongabay.com/2025/09/satellite-data-show-burst-of-deforestation-in-myanmar-rare-earth-mining-hotspots/
●2025.9.16 Mongabay:FSCの改訂により、森林問題への責任が弱まる恐れがあるとの批判
FSCは、認証を受けた企業が関連会社、供給業者、子会社による違反に対して責任を負うかどうかを決定する「企業グループ」規則の適用方法を更新した。
フォレスト・ピープルズ・プログラム、グリーンピース、レインフォレスト・アクションネットワークなどのNGOは、この変更により過去の森林破壊や土地紛争を完全に解決しないまま、APPやAPRILなどの林産業大手がFSCに再加入する可能性があると警告している。
NGOは審査プロセスに参加したが、企業側の意見が優先され市民社会の意見が歪曲されたと指摘。今回の改訂が企業の評判を地域社会の権利より優先させる懸念を表明している。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/09/critics-say-fsc-update-risks-weakening-accountability-for-forest-harm/
https://news.mongabay.com/2025/09/critics-say-fsc-update-risks-weakening-accountability-for-forest-harm/
●2025.9.6 FSC:ベトナムにおける森林管理に関する調査、最終結果を発表
FSCとASI(Assurance Services International)は、「ベトナムにおける森林管理の取引情報の照合調査」を完了しました。この取引情報の照合調査では、厳格な監査が追加して実施され、その結果、認証機関によって非適切な組織の認証が自主的に取り下げられたり、強制的に取り消されたりする事例が見られました。
FSCとASIは、2023年にベトナムにおける森林管理の取引情報の照合調査を開始しました。目的は、FSC認証林から伐採され、木質ペレット製造業者に販売される木材の取引パターンと量を追跡することでした。ASIは、ベトナム国内の24万1,600ヘクタールを超える森林を対象に、56の森林管理認証取得社と368のCoC認証取得者から、2022年1月から12月までの取引データを収集しました。
この調査中に、取引データの提出要求に応じなかった6つの認証取得者が認証機関によって認証を取り消されました。また、精査を避けるためか、自主的に認証を取り下げた組織も少数見られました。
詳しくはこちら
 https://jp.fsc.org/jp-ja/newsfeed/integrity-and-disputes/final-results-of-the-vietnam-tvloop
https://jp.fsc.org/jp-ja/newsfeed/integrity-and-disputes/final-results-of-the-vietnam-tvloop
●2025.7.28 Mongabay:地球温暖化は嵐や雷を変化させ、熱帯林に影響を与えている
研究者らは、世界の熱帯林における樹木の枯死の30~60パーセントは、暴風雨によって引き起こされている可能性があると推定している。懸念されるのは、この割合が今後上昇する可能性があり、データによると熱帯での暴風雨は10年ごとに5~25パーセント増加していることだと、研究の筆頭著者であるキャリー生態系研究所の森林生態学者エヴァン・ゴラ氏は述べている。
論文が指摘するように、熱帯地域におけるデータは限られており、暴風雨の影響に関する研究のほとんどはパナマ、ブラジル、ボルネオに集中している。しかし、ゴラ氏によると、彼のチームの研究結果は、アマゾンとオーストラリアで過去数十年にわたって樹木の枯死率が上昇しているという観察結果と一致しており、暴風雨が何らかの役割を果たしている可能性を示唆しているという。
「嵐の活動が増加することで、実際に炭素貯蔵量が減り、森林の気候調節能力に大きな損害を与える可能性がある。これは非常に重要なことだ」と彼は付け加えたが、今回の研究ではこうした可能性は調査されていない。
一方、気候変動によって熱帯地方における雷の発生が減少するか増加するかについては矛盾したデータがあり、将来の影響については不確実性が生じている。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/07/global-warming-is-altering-storms-lightning-impacting-tropical-forests/
https://news.mongabay.com/2025/07/global-warming-is-altering-storms-lightning-impacting-tropical-forests/
●2025.7.15 Mongabay:熱帯林の根には地上の変化が地下に及ぶにつれて負荷がかかっている
根は菌根と呼ばれる菌類と共生している。菌類は根にミネラルと水分を供給し、病原菌から保護し、その見返りに、根は菌類にエネルギー源として炭素を提供する。この重要な関係は、熱帯林生態系全体の安定性を維持するのに役立っている。
最近の研究は、森林内の根系全体が地球規模の変化にどのように反応するか、特にそれらの変化が地下の炭素貯蔵にどのような影響を与えているかを扱っている。
根系の変化への反応を示すデータから得られる新たな知見が、気候科学者が将来の炭素循環のシナリオをより正確に予測し、森林管理者が熱帯林の保全と再生に関してより良い意思決定を行うのに役立つことが期待される。
この画期的な研究の多くは、根の研究者による国際的なグループ、TropiRootが主導している。
TropiRootチームは、現在、巨大な熱帯炭素貯蔵庫は、熱帯林が地球温暖化、降雨パターンの変化、森林劣化と伐採、大気中のCO2濃度の上昇に伴う土壌養分枯渇を経験するにつれ、ますます危険にさらされていると主張している。
TropiRootを率いるコロラド州立大学生態系科学・持続可能性学部准教授のダニエラ・F・カサック氏は、幸いなことに、熱帯林の中にはより回復力の高いものもあり、その鍵は主に地下の根の柔軟性にあると指摘する。根が反応し適応できれば、熱帯林は気候変動により長く耐えられる可能性が高くなる。
カサック氏は、「科学者たちは現在、どの森林がより回復力があり、どの森林がより脆弱であるかに関するデータを蓄積しつつある」と述べている。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/07/tropical-forest-roots-show-strain-as-changes-aboveground-filter-below/
https://news.mongabay.com/2025/07/tropical-forest-roots-show-strain-as-changes-aboveground-filter-below/
【森林保全】
●2025.10.4 ブラジル日報:アマゾンでCOP30の意義=ブラジルや日本企業にとっての展望=CIが商議所でセミナー
COP30(国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議)が11月、アマゾンの玄関口ベレンで開催される。
これを前に9月27日、ブラジル日本商工会議所と国際環境NGOコンサベーション・インターナショナル(CI)が共催するセミナーが開かれた。セミナーではまず、地球が不可逆的な転換点=ティッピングポイントに迫っていると警鐘が鳴らされた。ブラジル・アマゾンはすでに17%が失われ、劣化も含めれば約半分に達している。科学者は「アマゾンは、あと5%の消失でティッピングポイントに達する」と警告し、広大な熱帯林はサバンナ化に向かい、地球規模の気候システムに深刻な影響を及ぼすと指摘する。
CIブラジル気候ソリューションダイレクターのラウラ・ラモニカ氏は、「無為はもはや選択肢ではない」と強調し、わずか0・1度の温度差が極端気象や生態系崩壊を左右する現実を訴えた。
詳しくはこちら
 https://news.yahoo.co.jp/articles/e579de733158d0e8c68283c486ddc271d9ce41f5?page=1
https://news.yahoo.co.jp/articles/e579de733158d0e8c68283c486ddc271d9ce41f5?page=1
●2025.9.26 Mongabay:COP30サミットを前にブラジルが新たな森林金融メカニズムの推進を主導
世界中の熱帯林を保全するための1250億ドル規模の基金「熱帯林フォーエバー・ファシリティ(TFFF)」は、2023年にブラジルによって策定され、2024年にコロンビアで開催された国連生物多様性サミットで推進された。
1250億ドル規模のこの基金が設立されれば、合計10億ヘクタール以上の熱帯林を保有する70カ国以上のTFFF対象開発途上国に分配される可能性がある。基金は2030年までに運用開始される可能性がある。
9月23日にニューヨークで開催されたClimate Week NYCにおいて、ブラジルのルーラ大統領は、ブラジルがこの基金に最初の10億ドルを投資すると発表した。中国、ノルウェー、英国、ドイツ、日本、カナダなどの国々も拠出する準備が整っているようだ。
TIFFFの成否を分ける決定的瞬間は、11月10日から21日までブラジルのベレンで開催される国連気候変動枠組条約第30回締約国会議(COP30)で訪れると予想されている。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/09/brazil-leads-push-for-novel-forest-finance-mechanism-ahead-of-cop30-summit/
https://news.mongabay.com/2025/09/brazil-leads-push-for-novel-forest-finance-mechanism-ahead-of-cop30-summit/
●2025.7.29 Mongabay:科学者とコミュニティは、希少で多様なブラジルの草原生態系の保存を急いでいる
「岩地の草原(rupestrian grasslands)に生育する植物の9割は、必然的に何らかの癌を患っている」とミナスジェライス連邦大学の生態学教授のフェルナンデス氏は言う。これは、岩地の草原の植物はほとんどが山頂で生育しているためである。強い紫外線と資源の不足が植物にストレスを与え、防御機構が弱体化することで腫瘍を発症しやすくなる。しかし、数千年をかけて、この植物はストレス要因に適応するように進化し、逆境にもめげずに生き延びてきた。
ブラジル国土のわずか0.8パーセントを占める岩地の草原は、490カ所に分布しており、そのほとんどはミナスジェライス州とパラ州に集中している。ブラジルの植物相の15パーセントの生育地となっており、これらの種のうち40パーセントが固有種である。
しかし、保全地域に指定されている岩地の草原面積は、現存面積の1割未満に過ぎず、種の存続が危ぶまれている。復元には多くの課題が伴う。特に、鉱山会社は鉱物採掘のために土壌をすべて除去することが一般的であるためだ。しかし、研究チーム、コミュニティ、そして大学と鉱山会社のパートナーシップは、地球上で最も生物多様性に富んだ生態系の一つを守るために準備を整えている。
現在、シルヴェイラ氏と彼の同僚たちは、ブラジルでは新しい技術である表土移植を用いて、カラジャス地方の再生プロジェクトを進めている。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/07/scientists-communities-rush-to-save-rare-diverse-brazilian-grassland-ecosystem/
https://news.mongabay.com/2025/07/scientists-communities-rush-to-save-rare-diverse-brazilian-grassland-ecosystem/
【カーボンクレジット】
●2025.6.17 Mongabay:アマゾンの検察がクレジットの無効を求めるなか、「世界最大」の炭素クレジット取引が批判にさらされている
2024年9月、ブラジルのパラ州は、アマゾン、バイエル、H&Mグループ、ウォルマート財団などに1億8000万ドルで1200万の炭素クレジットを販売する契約を締結した。パラ州によるREDD+プログラムで創出されたクレジットに関わるこの取引は、これまでで世界最大の炭素クレジットの販売として注目を集めた。
しかし9か月後の6月3日、この契約は、ブラジル連邦裁判所で法的異議申し立てを受けており、完全に破棄される可能性がある。
ブラジル連邦検察庁は、この合意の無効化と地域コミュニティへの精神的損害に対する賠償として3,600万ドルの支払いを求める訴訟を起こした。訴訟では、パラ州政府が炭素クレジットの事前販売を行っていたと主張されている(炭素市場に関するブラジルの新しい法律に違反)。
もう一つの争点として、検察は州が地域コミュニティから自由で事前の、かつ十分な情報に基づく同意を得ていなかったとして非難している。パラ州によるREDD+プログラムは、州内のすべての森林地帯を対象としており、その面積は8,400万ヘクタールに及び、これはフランスとドイツを合わせた面積にほぼ匹敵する。この地域には、1,000以上の伝統的先住民族、キロンボラ(かつて奴隷だった人々の子孫)、そして採掘を行うコミュニティが暮らしている。
パラ州環境局長のラウル・プロタツィオ・ロマオン氏は、この地域には多くの伝統的コミュニティが存在することから、個別の協議を実施することは不可能だと述べた。「10年かかっても完了できないでしょう」と、ロマオン氏は述べた。「各コミュニティが独自の協議プロトコルを持ち、それをすべて遵守するとしたら、700件、800件、900件もの協議が必要になります。私たちの見解では、個別の協議は不要です。」
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/06/worlds-largest-carbon-credit-deal-under-fire-as-amazon-prosecutors-seek-repeal/
https://news.mongabay.com/2025/06/worlds-largest-carbon-credit-deal-under-fire-as-amazon-prosecutors-seek-repeal/
【バイオマス】
●2025.9.30 日経新聞:レノバ、佐賀県内のバイオマス発電所稼働 国内7カ所目
再生可能エネルギー大手のレノバは30日、佐賀県のバイオマス発電所の商業運転を始めたと発表した。発電容量は4万9900キロワット。同社が出資・運営に参画するバイオマス発電所として7カ所目となる。
レノバが計画を公表していたバイオマス発電所は全て稼働したことになる。輸入燃料を使う大型バイオマス発電所について政府が補助金の対象外としたことなどを受け、レノバは30年度までは輸入材を使った大型バイオマス発電の新規開発をゼロとする予定だ。
詳しくはこちら
 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC302XT0Q5A930C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC302XT0Q5A930C2000000/
●2025.9.24 電気新聞:ゼロワットパワー、バイオマス発電所買収/静岡で8.5万キロワット
新電力のゼロワットパワー(千葉県柏市、佐藤和彦社長)は22日、静岡県富士市で出力8万5400キロワットの木質バイオマス発電所を保有する鈴川エネルギーセンターを買収し、完全子会社化したと発表した。買収額は非公表。発電所は2024年12月から稼働を停止している。木質ペレットの輸入コストの上昇が背景とみられるが、ゼロワットパワーはバイオマス発電所の建設支援や木質燃料の調達に関する知見を生かして事業再建に乗り出し、26年度中に再稼働させる考えだ。年間発電量は6億キロワット時を見込む。
詳しくはこちら(有料記事)
 https://www.denkishimbun.com/archives/394398
https://www.denkishimbun.com/archives/394398
●2025.8.28 Investing.com:バイオマス供給開示でイギリス当局の調査を受けるDrax社、株価急落
Drax社は、内部告発者の申し立てを受け、バイオマスペレット用の木材調達方法について英国金融行動監視機構(FCA)の調査を受けている。
木曜日のロンドン市場で同エネルギーグループの株価は約9パーセント下落した。
この動きは、同社の元広報・政策部長であるRowaa Ahmar氏が、不当解雇の申し立ての一環として、木材調達に関する誤解を招く声明についてDrax社を今年初めに告発した後に起きたものである。
RBCキャピタル・マーケッツのアナリスト、アレクサンダー・ウィーラー氏はノートで「FCAがこの時点で調査を開始した理由は現時点では示されていない」と述べた。
同氏は、調査範囲がOfgemの以前のレビューと重複する可能性があり、そのレビューでは不正行為の発見はなかったと付け加えた。
それでも、アナリストはこのプロセスが「Drax発電所の将来に関する政府との最終合意の締結をめぐり、市場にある程度の不確実性をもたらす可能性がある」と警告した。
詳しくはこちら
 https://jp.investing.com/news/stock-market-news/article-1230577
https://jp.investing.com/news/stock-market-news/article-1230577
●2025.7.2 Mongabay:カリフォルニア州の木質ペレット工場、市場の低迷と国民の反発で閉鎖
カリフォルニア州の農村経済開発に注力する非営利公益法人ゴールデンステート・ナチュラル・リソーシズ(GSNR)は、州内に2つの木質ペレット工場を建設する計画を中止した。同組織は、市場環境の悪化と地元住民からの反対を決定の理由として挙げている。
同組織は、繁茂した植生を減らし、火災リスクを軽減するため、2工場から半径161キロメートル圏内の公有林および私有林から木材を調達し、主に輸出市場向けにバイオマスエネルギーとして年間約100万トンのペレットを生産する予定だった。
しかし、ペレットの需要は近年大幅に減少している。韓国は、 2025年1月以降、新規バイオマスプロジェクトへの補助金を廃止し、輸入森林バイオマス燃料を使用する発電所への補助金も段階的に削減することを、2024年12月に発表した。2月には、英国政府が、物議を醸している木質燃料発電所への補助金を半減させると発表した。
GSNRは、代わりに木質チップの国内市場を開拓すると発表した。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/short-article/2025/07/california-wood-pellet-plants-canceled-amid-market-decline-public-pushback/
https://news.mongabay.com/short-article/2025/07/california-wood-pellet-plants-canceled-amid-market-decline-public-pushback/
【違法伐採問題】
●2025.7.10 Mongabay:地域パトロールによりアマゾンの犯罪件数が減少(研究)
ブラジルのアマゾンで実施された調査によると、2つの保護区における地域密着型のボランティアパトロール活動が、2003年から2013年にかけて記録された環境犯罪の80パーセント減少と関連していることが明らかになった。同時期に、これらの保護区外で政府主導の活動によって摘発された環境違反には明確な減少が見られなかったことから、地域密着型のパトロールの方がより効果的であったことが示唆される。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/short-article/2025/07/community-patrolling-reduces-crime-numbers-in-the-amazon-study-shows/
https://news.mongabay.com/short-article/2025/07/community-patrolling-reduces-crime-numbers-in-the-amazon-study-shows/
【パーム油問題】
●2025.8.22 Mongabay:インドネシアのアチェ州で森林破壊のないパーム油を求める運動に世界的ブランドが参加
ネスレ、ペプシコ、ユニリーバなどの主要ブランドは、インドネシアのアチェ州における森林破壊のないパーム油に向けた新たなロードマップに沿うため、「アチェ持続可能なパーム油ワーキンググループ」を発足させた。スマトラ島にあるアチェ州は、ルセール生態系をはじめとする重要な生息地を有するが、2020年以降、約42,000ヘクタールの森林を失い、その多くはアブラヤシ農園の拡大が原因である。
この取り組みは、小規模農家の人々の生計向上、保護価値の高い森林の保護、EU森林破壊規則(EUDR)など、新たな国際ルールへの生産者の対応支援を目的としている。計画は国際的な支持を得ているが、市民団体は違法な森林破壊を止めるための説明責任、透明性、持続的な圧力の確保が成功の鍵だと強調している。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/08/global-brands-join-drive-for-deforestation-free-palm-oil-in-indonesias-aceh/
https://news.mongabay.com/2025/08/global-brands-join-drive-for-deforestation-free-palm-oil-in-indonesias-aceh/
●2025.7.30 Mongabay:インドネシアがパーム油から森林を取り戻すなか、小規模農家らは取り締まりの標的となっている
1月に発布された規制に基づき、プラボウォ大統領は、アブラヤシ栽培や採掘など森林地での違法行為を取り締まるための特別チームを編成した。違法なパーム油農園だけでも、合計337万ヘクタールの森林を占有している。特別チームは2025年2月の発足以来、 200万ヘクタールの土地を取り戻し、そのほぼ半分を国営プランテーション会社アグリナス・パルマ・ヌサンタラに引き渡した。
これにより、土地面積で世界最大の国営パーム油会社が誕生する可能性があり、民間の土地独占が国営に置き換わる危険性があると批判されている。また、この取り締まりは大規模な企業活動と、歴史的に一方的な森林区域指定により土地保有権をめぐる紛争に直面してきた先住民族を含む地域コミュニティの活動を区別していないと指摘されている。
同国最大の環境NGO WALHIの分析によると、この取り締まりにより先住民族や地域コミュニティが追放され、大企業が保護され、正当な手続きなしに土地がアグリナス社に譲渡されたという。
活動家らは政府に対し、森林地帯でのアブラヤシ栽培の複雑な現実に対処しておらず、地域コミュニティの権利も保護していない森林法(1999年制定)を改正するよう求めている。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/07/as-indonesia-reclaims-forests-from-palm-oil-smallholders-bear-brunt-of-enforcement/
https://news.mongabay.com/2025/07/as-indonesia-reclaims-forests-from-palm-oil-smallholders-bear-brunt-of-enforcement/
●2025.7.24 Mongabay:インドネシアのパーム油会社、1800万ドルの汚染賠償判決獲得に貢献した専門家を提訴
環境専門家のバンバン・ヘロ・サハルジョ氏とバスキ・ワシス氏の証言によって、ボルネオ島中部カリマンタン州で発生した大規模火災の汚染者、パーム油会社カリマンタン・レスタリ・マンディリ(KLM)は有罪に追い込まれたが、バンバン氏らはそのKLMから訴えられている。
裁判所は、バンバン氏とバスキ氏が行った評価に基づき、火災の責任はKLMにあると認定し、同社に550万ドルの罰金と1290万ドルの環境修復費用の支払いを命じた。
7年を経て、KLMはバンバン氏とバスキ氏を相手取り民事訴訟を起こした。
活動家らはこのKLMによる訴訟を、企業や政府が批判者を脅迫したり黙らせたりするために使う法的戦術である、スラップ(SLAPP)の典型的な例として非難している。
インドネシアは、軽率なスラップ訴訟に対抗するための措置を講じている。しかし、様々な反スラップ訴訟規制が存在するにもかかわらず、その実施状況は依然として不十分であり、スラップ訴訟はしばしば裁判に持ち込まれる。
グリーンピース・インドネシアの森林キャンペーン担当者、セカール・バンジャラン・アジ氏は、汚染者が依然としてスラップ訴訟を提起できるのは、KLMの場合のように、裁判所の判決執行が不十分なことが一因だと指摘する。同社は2019年に有罪判決を受けたにもかかわらず、裁判所は判決執行に必要な罰金を未だに徴収していない。そのため、KLMはバンバン氏とバスキ氏を提訴する余地が生まれていると、セカール氏は述べている。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/07/indonesian-palm-oil-company-sues-experts-who-helped-secure-18m-pollution-ruling/
https://news.mongabay.com/2025/07/indonesian-palm-oil-company-sues-experts-who-helped-secure-18m-pollution-ruling/
【コミュニティ】
●2025.7.22 Mongabay:FSC伐採救済枠組みの試験的導入に期待と失望(インドネシア)
インドネシアは、2023年に採択された森林管理協議会(FSC)の新たな救済枠組みの最初のテストケースであり、この枠組みは、認証をはく奪された伐採会社が過去の環境的・社会的損害を修復することで、認証を取得または回復できるというものである。
インドネシア最大の伐採会社2社がこの取り組みに参加している。
しかし、FPP、YMKL、バハテラ・アラムなどのNGOが、新しい報告書のなかで検証している、ロイヤル・ゴールデン・イーグル(RGE)グループ傘下のエイプリル社の救済プロセスは、同意の欠如、性急な評価、影響を受ける多くの先住民コミュニティの排除など、重大な欠陥があるとされている。
エイプリル社は2013年にFSC認証を取り消されたが、再加盟を目指し、2023年11月にFSCと是正プロセス開始に関する合意を締結した。このプロセスの一環として、エイプリル社はコンサルタント会社であるリマーク・アジアによる環境・社会被害に関するベースライン評価を受けた。FSCによると、リマーク・アジアは2024年11月に北スマトラ州におけるエイプリル社の事業評価を完了していた。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/07/hope-and-frustration-as-indonesia-pilots-fscs-logging-remedy-framework/
https://news.mongabay.com/2025/07/hope-and-frustration-as-indonesia-pilots-fscs-logging-remedy-framework/
●2025.7.22 Mongabay:COP30の意思決定から先住民族代表は依然として排除されているとリーダーが語る
ブラジル政府は、アマゾンのベレンで11月に開催されるCOP30気候変動サミットの意思決定プロセスに先住民族を参加させるという約束を果たしていない、と著名な先住民族指導者ベト・マルボ氏は述べた。
ブラジル気候変動先住民委員会の参加といった措置により、先住民コミュニティとの連携が強化された。
しかし、ブラジルは依然として矛盾に満ちているとマルボ氏は述べた。気候変動対策のリーダーとしての地位を確立しようとしながらも、同時に環境保護に関する法律を弱体化させているのだ。
7月17日、ブラジル議会は環境保護団体が「破壊法案」と呼ぶ、環境規制を大幅に緩和する法案を承認した。大統領は拒否権を発動するか、署名して成立させるかの選択を迫られている。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/short-article/2025/07/indigenous-representatives-still-excluded-from-cop30-decision-making-says-leader/
https://news.mongabay.com/short-article/2025/07/indigenous-representatives-still-excluded-from-cop30-decision-making-says-leader/
●2025.7.22 Mongabay:研究は、アフリカ系コミュニティが森林伐採の減少と生物多様性の増加に関与していることを示唆
コンサベーション・インターナショナル・ムーア科学センターの社会科学者であるスシュマ・シュレスタ氏が筆頭著者の新たな研究によると、ブラジル、エクアドル、コロンビア、スリナムでのアフリカ系の人々が暮らす法的に認められた土地は、保護地域や保護されていない対照地域と比較して、極めて高いレベルの生物多様性を支えていた。
1,000万人以上のアフリカ人が奴隷にされ、その約90パーセントがラテンアメリカに連れてこられ、そのうち約半数がブラジルに移住した。奴隷制から逃れた人々は、しばしば森林、マングローブ、湿地帯などの辺境に向かった。そこで彼らは、伝統的な知識と新たな環境を融合させ、革新的な生存と管理の実践を生み出した。それらは、今もなお子孫に受け継がれている。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/short-article/2025/07/study-links-afro-descendant-communities-to-less-deforestation-more-biodiversity/
https://news.mongabay.com/short-article/2025/07/study-links-afro-descendant-communities-to-less-deforestation-more-biodiversity/
●2025.6.24 Mongabay:国連、インドネシアのメラウケ・フードエステートが先住民コミュニティを強制退去と非難
人権に関する国連特別報告者は、2025年3月7日付で、インドネシア政府と主要なプロジェクトデヴェロッパーであるグローバル・パプア・アバディ(GPA)社に対し、両者が先住民族コミュニティを強制移住させ、彼らの同意なしに109,000ヘクタールを超える森林を伐採し、反対意見を抑圧するために軍隊を派遣したとの疑惑について、書簡を送った。
いわゆるメラウケ・フードエステートプロジェクトの下、アグリビジネス大手はメラウケにおいて、300万ヘクタールの土地を開拓するためのコンセッションを確保した。その3分の2はサトウキビ農園、残りは水田となる。
現在のプロジェクトは、2010年に開始されたメラウケ・フード・アンド・エネルギー・エステート(MIFEE)プログラムを基盤としており、このプログラムは国家戦略プロジェクト(PSN)として復活・拡大された。重要なのは、PSN指定によって政府と承認されたデヴェロッパーが、国益を口実に住民を土地から立ち退かせる土地収用権を付与されることである。
インドネシア政府は、国内法を遵守していると主張し、このプロジェクトは食糧安全保障を高め、先住民の権利と環境保護が尊重されていると述べて、特別報告者らの主張を否定している。
NGOは、国連による監視の強化、事実調査団の派遣、真のFPIC(事前の自由意思におる十分な情報を得た上での同意)プロセスを強く求めている。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/06/un-calls-out-indonesias-merauke-food-estate-for-displacing-indigenous-communities/
https://news.mongabay.com/2025/06/un-calls-out-indonesias-merauke-food-estate-for-displacing-indigenous-communities/
【日本は今!】
●2025.9.26 日経新聞:トヨタのミライ、福島の森から走る バイオマス燃料で林業再生へ
東京電力福島第1原子力発電所の事故で被災したバイオマス(生物資源)から水素を作るプロジェクトが2025年度に始まった。スギなどの間伐材を高温で燃焼して水素を生産し、燃料電池車(FCV)の「MIRAI(ミライ)」に供給する。豊富な木材を生かした再生可能エネルギーの新たな地産地消になると期待される。
詳しくはこちら(一部会員限定記事)
 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC0373P0T00C25A9000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC0373P0T00C25A9000000/
●2025.9.24 新建ハウジング:木造化への支援など盛り込む 概算要求で2.7兆円要求─農水省
農林水産省は2026年度の概算要求で、対前年度比117.1パーセントの2兆6588億円を要求した。この中には、2023年に約3400万立米だった国産材の供給量を2030年に約4200万立米まで引き上げる目標のもと、木材需要拡大に対応できる、安定的かつ持続可能な供給体制の構築と、それに必要な森林の集積・集約化などを推進するとしている。
詳しくはこちら(有料会員記事)
 https://www.s-housing.jp/archives/397450
https://www.s-housing.jp/archives/397450
●2025.9.22 日経新聞:フィデアHD傘下の2行が13億円債権放棄 「業績予想影響なし」
フィデアホールディングス(HD)は22日、傘下の荘内銀行、北都銀行が鈴川エネルギーセンター(静岡県富士市)に貸し出していた13億9000万円について、債権を放棄すると発表した。
稼働当初は石炭火力発電所だったが、22年にバイオマス発電所に転換した。輸入木質ペレットといった燃料価格の高騰などを受け、24年12月には発電所の運用を停止した。
詳しくはこちら
 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC225ZY0S5A920C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC225ZY0S5A920C2000000/
●2025.9.19 林野庁:「『森の国・木の街』づくり宣言」に参画する自治体や企業等の募集を開始
林野庁は、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、平成18年4月1日から、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられたことをうけ、「『森の国・木の街』づくり宣言」に参画する自治体や企業等の募集を開始した。宣言に参画した自治体や企業等には、農林水産省から建築物の木造化や木材利用の効果の見える化などに関連する情報の提供等が行われる。
詳しくはこちら
 https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/mokusan/250919.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/mokusan/250919.html
●2025.9.17 日経クロステック:内装制限や防火規制など見直す政令が25年11月施行、狙いは木材利用の促進
政府は「建築基準法施行令の一部を改正する政令」により、建基法の内装制限や防煙壁の構造、防火関係の規制などを見直す。カーボンニュートラルの実現に向けて、温暖化ガスの吸収・貯蔵効果がある木材の利用を促す狙いがある。2025年8月29日に閣議決定し、同年9月3日に公布した。施行は同年11月1日を予定している。
詳しくはこちら(有料会員記事)
 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/02566/
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/02566/
【中国情報】
●2025.9.25 木材網:『中国人造板産業報告2025』が正式発表
9月20日、第10回世界人造板会議が山東省臨沂市で開催された。会議では『中国人造板産業報告2025』が正式に発表され、人造板(エンジニアードウッド)産業の発展現状と将来のトレンドが明らかにされた。
『報告』のデータによると、2024年末時点で、全国のエンジニアードウッド製造企業は8,600社余りを維持しており、前年比14.9パーセント減少したものの、総生産能力は8.41パーセント増加し、3億6,200万立方メートル/年に達し、「企業数は減少、生産能力の集中度向上」という特徴を示している。
合板の生産企業は6,020社余り、総生産能力は約2億2,100万立方メートル/年で、2023年末比7.8パーセント増加。企業平均生産能力は約3万6,700立方メートル/年。中国の合板産業は企業数が年々減少する一方、総生産能力は増加し、企業平均生産能力は持続的に拡大する傾向を示している。合板企業の平均生産規模は着実に拡大しており、2023年末の企業平均生産能力は約3.67万立方メートル/年で、2022年末比32.5パーセント増加した。
繊維板産業は、企業数・生産ライン数・総生産能力が減少する一方、平均単線生産能力が上昇する傾向を示し、総生産能力は中国の人造板産業で第3位を占める。2024年末時点で、全国240社の繊維板生産企業の総生産能力は4183万立方メートル/年。
一方2024年度、全国で48のパーティクルボード生産ラインが完成・稼働し、年間生産能力1,541万立方メートルが新たに追加され、中国パーティクルボード産業発展史上、最大の年間稼働総量を記録した。2024年末時点で、全国305社のパーティクルボード生産企業の総生産能力は6,415万立方メートル/年、純増生産能力は1,146万立方メートル/年となり、2023年末比で大幅な21.7パーセント増となった。
2024年、中国の人造板生産量は3億4,917万立方メートルで前年比3.9パーセント増。消費量は約3億2,967万立方メートルで前年比3.5パーセント増となった。三大板種の消費量はそれぞれ増減した。過去10年間の人造板消費量の年平均成長率は2.8パーセントであった。
国際貿易面では、昨年中国の合板類製品輸出量は1760.94万立方メートル(換算値)で前年比23.3パーセント増、輸出額は67億7,400万米ドルで前年比9.7パーセント増となった。合板類製品、繊維板類製品、パーティクルボード類製品の輸出量・輸出額はいずれも前年比で増加傾向を示した。一方輸入量は198.80万立方メートル(換算値)で前年比34.7パーセントの大幅増、輸入額は6億1,300万米ドルで前年比4.3パーセント増となった。
原文はこちら(中国語)
 https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=85616
https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=85616
●2025.9.12 木材網:ベトナムが中国産の一部繊維板に高額な反ダンピング関税を課す
ベトナム商工省は第2491/QD-BCT号決定を発表し、中国原産の一部繊維板製品に対し暫定的な反ダンピング関税を課すことを決定した。税率の範囲は2.59~39.88パーセントで、中国企業に対する最高税率はタイの同種製品を大幅に上回っている。
ベトナムの「対外貿易管理法」に基づき、調査の結果、中国から輸出される繊維板には明らかなダンピング行為が認められ、そのダンピング幅はタイ製品を大幅に上回っていることが判明した。ベトナム側の予備調査によると、中国の低価格繊維板はベトナム国内産業に重大な実質的損害の脅威をもたらし、現地企業の市場シェアが急激に縮小している。調査結果では、ベトナムによる調査開始後、中国からの対象製品の輸入量が前年比52パーセント急増し、ベトナム市場の均衡をさらに悪化させていることも明らかになった。
ベトナム政府は、今回の暫定措置は中国製品のダンピング流入を抑制し、国内産業が回復不能な損害を被るのを防ぐことを目的としていると表明した。今後ベトナムは関係機関と連携して継続的にデータを検証し、6ヵ月以内に最終裁定を下す予定で、税率のさらなる調整が行われる可能性がある。
原文はこちら(中国語)
 https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=85571
https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=85571
●2025.9.11 木材網:中国の合板類製品の輸出量が過去最高を記録
中国は世界有数の合板類製品貿易国の一つである。20世紀以来、中国は合板類製品の輸入大国であったが、WTO加盟後、合板類製品の輸出は急速な成長期に入り、国際的な合板類製品輸出貿易大国となった。
しかし近年、合板類産業は市場需要の変動、木材資源供給の制約、運営コストの上昇など複数の課題に直面しており、貿易障壁の影響も加わり、合板類製品の国際貿易は新たな特徴を示している。
中国の合板類製品の年間輸入量は、2022年以前は基本的に14万~22万立方メートルで推移していた。しかしここ2年間は、国際政治経済情勢の変化の影響を受け、年間輸入量の変動幅が著しく拡大している。
2023年に中国が輸入した合板類製品は29.54万立方メートルに達し、前年比50.64パーセント増となった。2024年には輸入量が前年比1倍以上増加し79.29万立方メートルに達し、輸入金額は1億8,900万米ドルで前年比7.25パーセント増となった。
この顕著な増加は主に、大量のロシア製合板が低価格で中国市場に流入したためであり、合板類製品の輸入量は過去10年間で最高水準に達した。
輸入合板類製品全体では、普通合板が主導的地位を占めている。2024年、中国は普通合板を77.43万立方メートル輸入し、前年比175.75パーセント増加した。
ロシアからの輸入量は73.68万立方メートルに達し、総輸入量の95.17パーセントを占めた。インドネシア、マレーシア、日本、ベトナムなどからの輸入量シェアはわずか1パーセント前後である。ロシアは過去5年間で中国最大の合板輸入国であり、2020年の輸入総量に占める割合34.58パーセントから、2024年には95.17パーセントに上昇した。ロシア・ウクライナ紛争以降、欧米市場がロシア産木材を制裁対象としたため、ロシアは木材輸出政策を調整:原木輸出を禁止し、加工品輸出を奨励しており、将来的に一定の供給リスクが生じる可能性がある。
一方、2024年の合板類製品の輸出量は1315.15万立方メートルに達し、前年比22.80パーセント増となり、過去10年間で同製品輸出量の新高値を更新した。しかし輸出金額はわずか9.45パーセントの増加に留まった。輸入と同様、中国全体の普通合板輸出が主導的地位を占めており、ここ2年間の輸出量はいずれも1,000万立方メートルを超えている。
原文はこちら(中国語)
 https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=85564
https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=85564
●2025.9.11 木材網:2024年中国の加工板輸出入が過去最高を記録
世界有数の加工板生産・輸出大国である中国は、2024年に国内外の市場課題の中で輸出入貿易の成長を達成した。年間の加工板輸入総量は107.94万トンで、過去10年間で最高を記録、輸出総量は1,005.51万トンでこれも史上最高を更新した。内訳は以下の通り:
■合板:輸入量は26.11万トンで、前年比33.76パーセントの大幅増となり、過去10年で最高値を記録。輸出量は676.81万トンで、前年比18.95パーセント増となり、過去10年で最高値を更新。
■パーティクルボード:輸入量は76.48万トンで前年比1.03パーセントの小幅増、輸出量は52.86万トンで前年比34.40パーセントの急増。
■ファイバーボード:輸入量は5.35万トンで下落傾向に歯止めがかかったものの依然低水準、輸出量は275.84万トンで、過去10年間で最高値を記録。
原文はこちら(中国語)
 https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=85562
https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=85562
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆第88回フェアウッド研究部会「認証材が取り持つビジネスマッチング
~大館市・北鹿地域林業成長産業化協議会と三菱地所レジデンスが木材利用促進協定を締結した訳~」
2025年10月15日(水)18:00~19:30@ハイブリッド
 https://fairwood.jp/event/251015
https://fairwood.jp/event/251015
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2021年に創設された「建築物木材利用促進協定制度」。全国で多くの事例が生まれる中、今年8月25日に締結された大館市・北鹿林成協と三菱地所レジデンスによる協定は、少し異なる“縁”から始まりました。そのきっかけとなったのは、「認証材」。木材の品質と信頼性が、川上(林業)と川下(マンション開発)を結びつけたのです。
本セミナーでは、大館市林政課 加賀谷洋昌氏と三菱地所レジデンス 石川博明氏のお二人を講師にお迎えし、行政・林産地域の理念と期待、そして木材を使用する側の希望と背景をそれぞれの視点から語っていただきます。
「なぜこの連携が実現したのか?」「認証材が果たした役割とは?」「地域材利用の未来に何が期待されているのか?」「川上と川下がどう結びついたのか?」、そのプロセスと想いを深掘りする貴重な機会です。木材利用の新たな可能性を探るこのセミナー、ぜひお聞き逃しなく!
【開催概要】
日時:2025年10月15日(水)18:00~19:30(開場:会場は15分前、オンラインは5分前)
場所:ハイブリッド(zoom×地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)
東京都渋谷区神宮前 5-53-70 国連大学ビル 1F)
参加費:一般1,500円、学生無料(いずれも懇親会費別)
定員:会場25名、オンライン90名
※懇親会は会場参加者のみご参加いただけます。当日の受付の際にお申込み・お支払いを承ります。
※会議URL:お申込みいただいた方に後日ご案内いたします。
※お申込みいただいた方で希望のある場合は、当日の録画アーカイブを後日、期間限定でご覧いただくことが可能です。
【プログラム】(敬称略、内容は予告なく変更することがあります)
第1部:講演(18:00~19:30 質疑含む)
講師:石川 博明/三菱地所レジデンス(株)経営企画部サステナビリティ推進グループ専任部長
加賀谷 洋昌/大館市産業部森林整備課林政課木材産業係主任
第2部:懇親会(会場参加者の希望者のみ、別会場にて開催予定)
【講師プロフィール】(敬称略)
石川 博明(いしかわ・ひろあき)/三菱地所レジデンス(株)経営企画部サステナビリティ推進グループ専任部長
広島県出身。1985年藤和不動産(株)入社、設備・電気技術者としてマンションの品質管理などに従事、2011年会社統合により三菱地所レジデンス(株)が誕生、分譲・賃貸マンションのモノづくりや企業のサステナビリティ推進を行う。現在は持続可能な木材活用とは何か?を日々研究中であり、日本の山がはげ山にならない木材活用をするための仲間集めに奔走中。
加賀谷 洋昌(かがや・ひろあき)/大館市産業部林政課木材産業係主任
秋田県出身。2014年大館市役所に入庁、福祉部子ども課で補助金や給付費業務に従事。2017年に全く畑違いである秋田県庁産業労働部に出向、東京事務所配属となり、企業誘致業務を担う。大館市に戻って以降、企業誘致・折衝、市有林整備・整備計画策定など産業畑を中心とした業務に従事し、現在は森林認証林整備と流通調整を行いながら、森林(もり)と消費者との心理的距離を近いものとするため、地元林業事業体や木材加工事業者と共に各所との関係性構築を進めている。
■お申込み
お申し込みフォーム(本サイト)よりお申し込みください。
フォームがご利用できない場合、「第88回フェアウッド研究部会参加希望」と件名に明記の上、1)お名前、2)ふりがな、3)ご所属(学生の場合は学校名など、組織名及び部署名等)、4)Eメールアドレス、5)参加方法(会場またはオンライン)、6)(会場参加の場合)懇親会の出欠を、メールにてinfo@fairwood.jp まで送付ください。
■主催
国際環境 NGO FoE Japan、地球・人間環境フォーラム、佐藤岳利事務所
■後援
マルホン
■助成
緑と水の森林ファンド
■お問合せ
FoE Japan(担当:佐々木)
 http://www.foejapan.org、info@foejapan.org、TEL:03-6909-5983
http://www.foejapan.org、info@foejapan.org、TEL:03-6909-5983
地球・人間環境フォーラム(担当:坂本)
 http://www.fairwood.jp、info@fairwood.jp
http://www.fairwood.jp、info@fairwood.jp
※テレワーク推進中のため、極力メールにてお問合せをお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆10/17【ウェビナー】脱炭素が脅かすインドネシアの天然林~現場からの報告~
 https://foejapan.org/issue/20251007/26114/
https://foejapan.org/issue/20251007/26114/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
世界的にも貴重な生物多様性豊かな熱帯林が広がっているインドネシア。
その豊かな森が、現在、エネルギー産業用造林(通称:HTE)により失われようとしています。
この背景の1つに、「脱炭素」を名目とした木質ペレットなど森林由来のバイオマス燃料の生産推進が挙げられます。
インドネシアは海外向けにバイオマス燃料を輸出しており、日本も主要な輸出国の一つです。インドネシアからの木質ペレット輸入量は急増しており、日本で再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT制度)が始まった2012年は15トンでしたが、2024年は30万トン以上にも達しています(貿易統計より)。
また、FIT制度により日本においてバイオマス発電が促進されてきた側面が強く、私たちの電気料金がインドネシアの天然林を含めた森林の破壊に寄与してしまっているととらえることもできるでしょう。
今回のウェビナーでは、天然林の減少が今まさに起こっているインドネシアの最前線で活動しているNGOのスタッフをお招きし、インドネシアの現状や森林減少の問題をバイオマスの観点からお伺いします。また、FoE Japanからは今年8月末~9月初旬にかけて現地NGOとともに実施した現地調査の結果をご報告します。
今回のウェビナーを通して、インドネシアの森林減少の現場の情報と日本の関与について紹介すると同時に、現状を受けて私たちはどのように対応すべきか皆様とともに考える機会にできたら幸いです。
■日時:2025年10月17日(金) 15:00~16:30
■形式:オンライン(Zoomウェビナー)
※上記開始時間の5分前より入室可能
※インドネシア語から日本語の逐次通訳が入ります。
■プログラム:「脱炭素」がインドネシアの天然林に与えるインパクトとは?
■講演概要:
インドネシアの現地NGOスタッフと現地調査を実施したFoE Japanのスタッフより、バイオマス燃料の需要拡大に伴うインドネシアの森林減少、および日本の関与の現状をお話しします。
■登壇者:
・Anggi Putra Prayoga / Forest Watch Indonesia
・三柴 淳一 / FoE Japan
※質疑応答あり
■申込み:ウェビナー登録はこちら
 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_968NNG9PS9iE2y93XR5xxQ#/registration
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_968NNG9PS9iE2y93XR5xxQ#/registration
■言語:日本語、インドネシア語(逐次通訳あり)
■参加費:無料/ご寄付歓迎  https://foejapan.org/get-involved/
https://foejapan.org/get-involved/
■主催・お問い合わせ:国際環境NGO FoE Japan、Forest Watch Indonesia
■お問い合わせはこちら
 https://foejapan.org/contact/
https://foejapan.org/contact/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆ウェブサイト『バイオマス発電info』を公開しました!
 https://bioenergyinfo.jp/
https://bioenergyinfo.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地球・人間環境フォーラム(以下GEF)は、日本の再生可能エネルギー固定価格買取(FIT)制度が支援する「輸入木質バイオマス発電」の課題について理解を促すための最新動向やデータを提供するウェブサイト『バイオマス発電info』( https://bioenergyinfo.jp/)を公開しました。
https://bioenergyinfo.jp/)を公開しました。
「バイオマス発電info」は、主にメディア関係者と再エネに関心を寄せる事業者や金融機関を対象に、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)で支援されている輸入木質バイオマスが、再エネとして「持続可能」なのかを検証できる情報を提供しています。
“カーボンニュートラル”で“地産地消”とされる木質バイオマス発電の気候変動対策としての有効性や燃料生産地における環境・社会への悪影響などをわかりやすく解説し、「輸入木質バイオマス発電」をFIT制度で支援することが本当に「持続可能」と言えるのか、考えるサイトです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆レポート「持続可能なバイオマスプログラム:持続不可能なものを認証する」を発行!
 https://www.gef.or.jp/news/info/250731sbpreport/
https://www.gef.or.jp/news/info/250731sbpreport/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地球・人間環境フォーラムは、海外の環境NGO、4団体の共同でレポート『持続可能なバイオマスプログラム:持続不可能なものを認証する』を発行しました。
日本語版レポートの公開は10月上旬を予定しています。
バイオマス発電は、経済産業省の「再生可能エネルギー固定価格買取」(FIT)制度で「カーボンニュートラルな再生可能エネルギー」とされ、消費者負担の再エネ賦課金を原資に支援されてきました。
製材の残材や間伐材を燃料とすると言われてきましたが、実際には約7割の発電所で、海外から輸入される木質ペレットやパーム核殻(PKS)を燃やしています。2024年の輸入量は、木質ペレット638万トンとPKS 600万トンに上っています。
当団体では過去にカナダ・ブリティッシュコロンビア州の現地視察を行い、ペレット生産と原生林等の貴重な森林の伐採と関係など、現地の問題をお伝えしてきました。
本レポートは、カナダのペレット工場のケーススタディも踏まえて、現地で広く用いられている「持続可能なバイオマスプログラム(SBP)」の問題点を解説するものです。
日本のFIT・FIP制度は燃料の持続可能性の証明を「認証」に過度に依存しており、SBPも既に証明方法として認められています。早急な見直しに向けて、本レポートは極めて重要な分析を提供しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆フェアウッド・マガジン 世界のニュース登録方法を追加しました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
フェアウッド・パートナーズが、毎月、無料で配信している「フェアウッド・マガジン 世界のニュース」の登録・削除方法を追加しました。
これまでは、外部のメールマガジン配信サービス「まぐまぐ」のみとなっていましたが、フェアウッド・パートナーズからのダイレクト配信システムを加えました。いずれも無料ですので、以下からお好みの方法で登録してください。
 https://fairwood.jp/mailmagagine/16/
https://fairwood.jp/mailmagagine/16/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・みなさんの知人、友人、ご家族の方にもこのメールマガジンをお知らせしてください。メールマガジンの登録、バックナンバーはこちらです。
 https://fairwood.jp/worldnews/
https://fairwood.jp/worldnews/
・本メールマガジンの記事について、無断転載はご遠慮ください。
ただし、転載許可の表記のある場合を除きます。
・本メールマガジンに関するご意見・ご感想などは下記のEmailにお寄せくだ
さい。お待ちしております。e-mail: info@fairwood.jp
発 行 : フェアウッド・パートナーズ  http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp
編 集 : 坂本 有希/三柴 淳一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです
◎フェアウッド・マガジン-世界のニュース
の配信停止(unsubscribe)はこちら
⇒  https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=147706&e=sagaragef%40gmail.com&l=scj1851435
https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=147706&e=sagaragef%40gmail.com&l=scj1851435
![]() http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp![]() https://project.nikkeibp.co.jp
https://project.nikkeibp.co.jp![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://jp.fsc.org/jp-ja/newsf
https://jp.fsc.org/jp-ja/newsf![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.yahoo.co.jp/artic
https://news.yahoo.co.jp/artic![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://www.nikkei.com/article
https://www.nikkei.com/article![]() https://www.denkishimbun.com/a
https://www.denkishimbun.com/a![]() https://jp.investing.com/news/
https://jp.investing.com/news/![]() https://news.mongabay.com/shor
https://news.mongabay.com/shor![]() https://news.mongabay.com/shor
https://news.mongabay.com/shor![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/shor
https://news.mongabay.com/shor![]() https://news.mongabay.com/shor
https://news.mongabay.com/shor![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://www.nikkei.com/article
https://www.nikkei.com/article![]() https://www.s-housing.jp/archi
https://www.s-housing.jp/archi![]() https://www.nikkei.com/article
https://www.nikkei.com/article![]() https://www.rinya.maff.go.jp/j
https://www.rinya.maff.go.jp/j![]() https://xtech.nikkei.com/atcl/
https://xtech.nikkei.com/atcl/![]() https://www.chinatimber.org/ne
https://www.chinatimber.org/ne![]() https://www.chinatimber.org/ne
https://www.chinatimber.org/ne![]() https://www.chinatimber.org/ne
https://www.chinatimber.org/ne![]() https://www.chinatimber.org/ne
https://www.chinatimber.org/ne![]() https://fairwood.jp/event/2510
https://fairwood.jp/event/2510![]() http://www.foejapan.org、info@f
http://www.foejapan.org、info@f![]() http://www.fairwood.jp、info@fa
http://www.fairwood.jp、info@fa![]() https://foejapan.org/issue/202
https://foejapan.org/issue/202![]() https://us02web.zoom.us/webina
https://us02web.zoom.us/webina![]() https://foejapan.org/get-invol
https://foejapan.org/get-invol![]() https://foejapan.org/contact/
https://foejapan.org/contact/![]() https://bioenergyinfo.jp/
https://bioenergyinfo.jp/![]()
![]() https://www.gef.or.jp/news/in
https://www.gef.or.jp/news/in![]() https://fairwood.jp/mailmagagi
https://fairwood.jp/mailmagagi![]() https://fairwood.jp/worldnews/
https://fairwood.jp/worldnews/![]() http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp![]() https://regist.mag2.com/reader
https://regist.mag2.com/reader