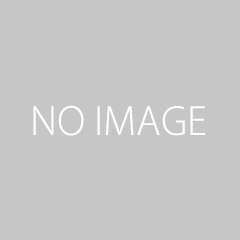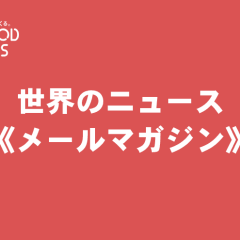--- フェアな木材を使おう ---  http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大規模バイオマス発電に関して、FIT・FIP支援の打ち切りが発表されましたが、対象となるのは2026年度以降の案件に限られるということで、その効果を疑問視する記事も散見されます。
フェアウッド・パトナーズは、3月13日にエコッツェリア協会と共催で「フェアウッド×木のある暮らし」と題したイベントを開催します。これからのライフスタイルに木造建築や木のある環境をどう取り入れていけるか、皆さまと共に考えるイベントです。学生無料ですので、是非ご参加下さい。
 https://fairwood.jp/event/250313/
https://fairwood.jp/event/250313/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【森林の再生】
●2025.2.19 Sustainable Brands(日本版):気候変動の緩和策で、生態系保全に最も有効なのは「森林の再生」――米サイエンス誌の最新研究で明らかに
気候変動の抑制を促す土地ベースの緩和策は従来、森林再生、植林、バイオ燃料用作物の栽培だと思われてきた。だが、これらは必ずしも等しく生物多様性にプラスであるわけではないことが、米サイエンス誌の最新研究で明らかになった。生物多様性にもっとも有効な対策は実は「森林の再生」であり、この方策こそが生き物に生息地を与え、気候変動の抑制にもつながるという。
この研究論文を執筆したのは、米自然保護団体ネイチャー・コンサーバンシー、生態環境の保護と復元に取り組む米ニューヨーク植物園のCenter for Conservation and Restoration Ecology、プリンストン大学の進化生態学部ならびにハイメドウズ環境研究所(HMEI)の科学者で構成された研究チームだ。
今回の最新研究は、森林再生、植林、バイオ燃料用作物の栽培という3つの世界的な気候変動緩和策が生物多様性に及ぼし得るインパクトを評価した初の試みだ。
最も多くモデル化されている種の生息地が森林であったため、かつての森林地帯で樹木生育を促進することには平均してプラスの効果があった。これに対し、バイオ燃料用作物の栽培の場合は平均してマイナスに作用した。森林再生は多くの脊椎動物に恩恵をもたらす可能性がある。しかし今回の研究では、非森林地帯の大半では植林したりバイオ燃料用作物を栽培したりせず、何もしないほうが生物多様性には好ましいことが示された。
詳しくはこちら
 https://www.sustainablebrands.jp/news/us/detail/1226752_1532.html
https://www.sustainablebrands.jp/news/us/detail/1226752_1532.html
●2024.12.5 Mongabay:樹木は驚くべき方法で一生を終えることを大掛かりな研究が解明
約120名の研究者らの国際チームは、南北アメリカ全域の1,000種を超える樹木を網羅した320万件の幹の成長率、樹齢、枯死など樹木測定値のデータセットをまとめた。
最近、サイエンス誌に発表された彼らの研究は、樹木の生活史はこれまで考えられていたよりも複雑であることを示しており、この成果は、炭素予測と保全戦略の改善に有用となる可能性がある。
早く生きて若くして死ぬ種から、ゆっくり生きて長生きして死ぬ種まで、4つの「成長戦略」グループが出現した。
また、データから、より多様な成長戦略を持つ森林の方が炭素を固定する能力が高いこともわかった。この研究の筆頭著者、ビアリック・マーフィー氏は、異なる成長戦略を持つ種が同じ資源をめぐって競争しないからではないかと述べている。
科学者らは、炭素予測では、多種多様な樹木に炭素がどのくらいの期間貯蔵されるかをより詳細にみていくべきだと提言している。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2024/12/trees-live-out-their-lives-in-surprising-ways-massive-new-study-finds/
https://news.mongabay.com/2024/12/trees-live-out-their-lives-in-surprising-ways-massive-new-study-finds/
【森林保全】
●2024.12.27 Mongabay:IPBES報告書は、先住民族と地域コミュニティの知識が社会変革の鍵だと強調
IPBES(生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム)が12月に発表した新しい報告書によると、先住民族や地域コミュニティの知識体系が人間と自然の相互関係を育む能力は、生物多様性喪失の根本原因に取組むために必要な変革を生み出す上で、重要な役割を果たす可能性があるという。
この報告書は、IPBESのもとで活動する42か国の100人以上の専門家によって作成された。
同報告書は、生物多様性の喪失の根本原因を3つ特定し、変化を導く4つの原則、変化を推進する5つの戦略、6つの幅広いアプローチ、そしてこの変化が直面する5つの課題を挙げて結論づけている。
報告書によると、 87か国にわたる、保護地域および生態学的に無傷の景観の約40パーセントの保有権を持つ先住民族と地域コミュニティは、保全プロセスと変革において重要な役割を果たしているという。
ただ一方で、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンスの環境・開発学教授ティム・フォーサイス氏は、研究によると、先住民族の伝統的な生態学的知識や生態系の保護から学ぶことは多いが、こうした文化の多くは若い世代において変化しつつあるという。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2024/12/ipbes-report-highlights-indigenous-local-knowledge-as-key-to-transformative-change/
https://news.mongabay.com/2024/12/ipbes-report-highlights-indigenous-local-knowledge-as-key-to-transformative-change/
【森林減少】
●2025.2.19 ロイター:米国製紙業界、トランプ大統領にEU森林破壊防止規制の緩和を求める
米国の製紙・パルプ業界は、トランプ政権に対し、米国が森林破壊ゼロの国と分類されるようEUに求めるべきだと働きかけている。
これは、商務長官に指名されたハワード・ラトニック氏が米国を「低リスク」に分類するよう求めた内容を超えるものだ。低リスクとは、EUの政策で最も緩いレベルである。EUDRには森林破壊ゼロとみなされる国のカテゴリーは含まれていない。
全米林産物製紙協会(AF&PA)によれば、米国のEU向け林産物輸出は35億ドルを超え、米国は、おむつや生理用品の製造に使用される特殊パルプの欧州の最大の供給国となっている。
AF&PAは、米国の製紙パルプ工場はEUの政策のトレーサビリティ要件を遵守できないと述べた。AF&PAのハイジ・ブロックCEOは「我々の業界で使用されている製材所残材や林地残材は、生産工程を通じて複数回混合される」と言う。「このため、元の森林の土地から最終製品に至るまで、個々の木材チップを追跡することは事実上不可能である。」
原文はこちら(英語)
 https://www.reuters.com/business/us-paper-industry-asks-trump-seek-lighter-eu-deforestation-rules-2025-02-18/
https://www.reuters.com/business/us-paper-industry-asks-trump-seek-lighter-eu-deforestation-rules-2025-02-18/
●2025.2.7 Mongabay:合法的な土地開拓の急増により、2024年のインドネシアの森林破壊率が上昇
インドネシアの森林破壊は2024年に、2021年以来最高レベルに増加し、ジャカルタの4倍に該当する26万1575ヘクタールの森林が失われた。
このうち97パーセントは合法的な伐採許可の範囲内で発生しており、違法な森林破壊から合法的な森林破壊への移行が浮き彫りになっている。
政府は数々の森林保護政策を発表しているが、その主な目的は、森林の皆伐を伴う植林やその他の商業活動に対する新たな伐採権の発行を制限することである。しかし、政府がすでに付与した伐採権の範囲内に残っている森林を保護する政策はない、との環境NGOアウリガ・ヌサンタラのティマー氏は述べた。
実際、政府は、企業が伐採許可を得ると、伐採許可区域内の皆伐を奨励し、伐採が遅ければ伐採許可を取り消して他の開発業者に与えることで罰している。その結果、伐採許可区域外での違法な伐採から、政府が伐採を許可し奨励する伐採許可区域内での合法な伐採へと変化しているとティマー氏は語った。
なお、2024年のスマトラ島の森林消失面積は9万1248ヘクタールで、2023年のほぼ3倍となった。その多くは、パーム油会社が農園拡大のため、伐採許可地域内の森林を皆伐したことと、違法な農園が森林に侵入したことによるものだ。近年、アブラヤシのための森林破壊は減少しているものの、農園産業は依然として同国の森林減少の主な要因となっており、2024年の総森林破壊の14パーセントを占めている。
カリマンタンでは、パルプ材農園の開発に加えて、政府の木質ペレット計画も森林破壊増加の要因となっている。政府は、発電所で使用する石炭の最大10パーセントを木質ペレットに置き換えるという目標を掲げている。クリーンエネルギーシンクタンクのトレンドアジアによる2022年の分析によると、エネルギー農園のために少なくとも100万ヘクタールの森林を伐採する必要がある。これはバリ島の2倍の面積に相当する。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/02/surge-in-legal-land-clearing-pushes-up-indonesia-deforestation-rate-in-2024/
https://news.mongabay.com/2025/02/surge-in-legal-land-clearing-pushes-up-indonesia-deforestation-rate-in-2024/
●2025.1.31 LiCASニュース:インドネシアの森林破壊は開発の拡大により3年連続悪化
環境監視団体によると、インドネシアの森林減少率は2024年も上昇傾向を続け、3年連続で森林減少が増加することになる。 同団体は、この破壊は政府支援の開発プロジェクトと、主要産業(木材、パーム油、鉱物)の拡大によるものだとしている。
アウリガ・ヌサンタラの新たな分析によると、インドネシアでは2024年に原生林と二次林約26万1575ヘクタールが失われた。10月に就任したプラボウォ・スビアント大統領は、輸入への依存を減らすためにバイオ燃料の生産を拡大するなど、食糧とエネルギーの自給率を高めることを約束している。
環境団体は、このような政策は森林破壊を加速させる可能性があると警告している。
アウリガ・ヌサンタラの報告書によると、森林破壊の主な推進力の一つはインドネシアの新首都のための土地の割り当てであり、このプロジェクトにより、地方政府は何十万ヘクタールもの森林を開発のために開放するよう提案している。
報告書はまた、インドネシアがバイオマスエネルギーの利用と輸出を特に日本と韓国に拡大しようとしていることから、バイオマス生産のための森林伐採に対する懸念も強調している。
原文はこちら(英語)
 https://www.licas.news/2025/01/31/indonesias-deforestation-worsens-for-third-year-as-development-expands/
https://www.licas.news/2025/01/31/indonesias-deforestation-worsens-for-third-year-as-development-expands/
●2024.12.24 Mongabay:アグリビジネス大手のオラムはEUDRで先行、サプライヤーは遅れ気味
欧州連合(EU)の森林破壊防止規則(EUDR)の遵守をめぐる競争で、大きなギャップが生まれている。シンガポールに本社を置くアグリ・フードビジネスのオラム・グループの子会社であるオラム・アグリおよびオフィは、先進的なトレーサビリティと情報システムを活用して優位に立っているとモンガベイに語った。対照的に、ホンジュラスやインドネシアなどの国の小規模農家は、EUDRが適用される前にコンプライアンス手続きを開始するのに必要な重要な情報とリソースをまだ欠いている。
ストックホルム環境研究所の上級研究員マイロン・バストス・リマ氏は、EUDRの義務を果たさなければならないとの圧力が高まるにつれ、大企業が自社のコンプライアンスの必要性を満たすためにサプライヤーを簡単に切り離してしまう危険性があると述べた。
欧州の大手企業は、不適合な製品を輸入した場合、売上高の最大4パーセントの罰金を科せられることになるのである。
エチオピアのカファ地域では、コーヒー豆のほとんどは貧しい農家により栽培されており、彼らにはEUDRの要件を満たすために必要な複雑なデータを収集する専門知識や技術がない。このため、すでに一部のヨーロッパの買い手が注文を減らしている。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2024/12/agribusiness-giant-olam-gets-head-start-on-eudr-its-suppliers-not-so-much/
https://news.mongabay.com/2024/12/agribusiness-giant-olam-gets-head-start-on-eudr-its-suppliers-not-so-much/
●2024.12.20 Mongabay:アマゾンの沸騰する川により、科学者たちは熱帯林の未来を覗くことができる
ペルーにある「沸騰する川」は、地中から湧き出る熱水が周囲の森林のなかに異なる温度帯を作り出すことからその名が付けられた。この自然のホットスポットは何千年も前から存在しており、科学者にとっては気温上昇が熱帯樹木にどのような影響を与えるかを研究する自然の実験室となっている。
「グローバル・チェンジ・バイオロジー」に掲載された研究で、マイアミ大学の研究者らは気温が1度上昇するごとに、その地域の樹木種が11パーセント減少することを発見した。科学者らは、この地域は2100年までに3~6度温暖化する可能性があると予測しており、気温が樹木の多様性に与える影響は大きいと著者らは述べている。
しかし、「この研究結果をアマゾンの森林全体に一般化するには、慎重に考慮する必要がある」と、この研究には関与していない米国パデュー大学のジンジン・リャン教授は述べた。アマゾン川流域の多くの地域では、気温ではなく水があるかどうかということの方が、樹木の多様性にとってより重要かもしれない。アマゾン川流域では季節的な降雨パターンや干ばつによるストレスによって、どの種が生き残れるかが決まることが多いからだ。「沸騰する川」の調査地は、暑い地域でも湿度が高いという点が珍しい。一方、アマゾンのほとんどの地域は、気温が上がるにつれて乾燥する傾向がある。論文の研究者はこの点について認めつつも、「平均気温の1度上昇につき多様性が11パーセント減少するという観測結果が熱だけで出ていることを考えると、これはかなり厳しい警告と言える」と述べている。
熱帯雨林は、樹木が水蒸気を大気中に放出する蒸散作用を通じて、降雨の多くを樹木自身に頼っている。この自立的なサイクルは、森林伐採、火災、気温上昇によって脅かされている。樹木が伐採されたり枯れたりすると、大気中に放出される水分が減少する。その結果、残った森林は乾燥し、火災が発生しやすくなり、さらに多くの樹木が枯死する。
科学者たちは、このサイクルが続けば、アマゾンの一部地域がティッピング・ポイント(転換点)に達し、森林の生物種が失われ、地域がより劣化したサバンナのような環境に変化する可能性があると警告している。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2024/12/amazons-boiling-river-gives-scientists-a-window-into-the-rainforests-future/
https://news.mongabay.com/2024/12/amazons-boiling-river-gives-scientists-a-window-into-the-rainforests-future/
【バイオマス】
●2025.2.13 朝日新聞:カナダの「マザーツリー」も燃料に 木質バイオマス発電はエコなのか
太平洋に面したカナダ・ブリティッシュコロンビア(BC)州。内陸部には針葉樹の森が広がるが、原生林は残り少なくなっている。
「木質バイオマス発電を持続可能だと思っている人がいますが、それは事実ではありません」。原生林を伐採から守る活動をしている地域団体「コンサベーションノース」のディレクター、ミシェル・コノリーさんは、同州の「古代の森」を歩きながら訴えた。
コノリーさんによれば、原生林が伐採されると、樹木や土壌に蓄えられた炭素の4分の3が失われる。たとえ植林しても、炭素を貯蔵し始めるのは20~30年後で、原生林と同様の貯蔵能力に達するには1世紀以上かかるという。
木質バイオマスは、再エネとしてカーボンニュートラルに位置づけられているが、木材の単位熱量(テラジュール、TJ)当たりの炭素排出量は29.6トンで、天然ガスの2倍以上、発電用の輸入石炭の24.3トンよりも多い。国連は、温暖化による破壊的な影響を回避するために「30年までの取り組みが決定的に重要」と位置づけている。排出と吸収が均衡するまで長期間を要するのは、温暖化対策としては致命的な欠点と言える。
詳しくはこちら
 https://digital.asahi.com/articles/AST2B2QPTT2BULBH00CM.html?ptoken=01JKZ5B2KMCM46AR9TMM2Z1TR5
https://digital.asahi.com/articles/AST2B2QPTT2BULBH00CM.html?ptoken=01JKZ5B2KMCM46AR9TMM2Z1TR5
●2025.2.6 朝日新聞:(バイオマス発電はエコなのか:上)原生林伐採 木質ペレット、日本へ
日本では、バイオマス発電に使う木質ペレットの輸入が急増。2023年は580万トンで、再生可能エネルギーの固定価格買い取り(FIT)制度が始まった12年以降、80倍になった。輸入元は、ベトナム、カナダ、米国の順だ。
日本のFIT制度下での新たなバイオマス発電施設は23年末時点で、認定1026カ所(稼働656カ所)。このうち燃料がペレットなどの一般木材なのは179カ所(同95カ所)で、その8割が輸入を想定している。これがカナダの原生林の減少につながっている、とカナダで原生林を伐採から守る活動をしている地域団体「コンサベーションノース」のコノリーさんは言う。
(輸入木質燃料に頼るバイオマス発電は)気候変動対策と称して森林破壊が進められる温床になっており、見せかけの環境配慮「グリーンウォッシュ」との批判も絶えない。欧州連合(EU)や韓国は監視を強め、支援をやめる方向に動く。経産省も、新規で輸入ものを使うことが多い大型の木質バイオマス発電について、26年度からFITの対象から外す方針だ。
詳しくはこちら(一部有料記事)
 https://digital.asahi.com/articles/DA3S16144240.html?ptoken=01JKD9ESGJXPS9HPSHW5FPVAKJ
https://digital.asahi.com/articles/DA3S16144240.html?ptoken=01JKD9ESGJXPS9HPSHW5FPVAKJ
●2025.2.6 日経BP:輸入木材による大規模バイオマス発電、FIT・FIP支援を打ち切りへ
経済産業省は2月3日、調達価格等算定委員会を開催し、バイオマス発電における輸入したチップやペレット、ヤシ殻(PKS)などを含む「一般木質燃料」区分の10MW以上案件と、パーム油など「液体燃料」区分の全規模案件について、固定価格買取制度(FIT)およびフィード・イン・プレミアム(FIP)による支援の対象外とする委員会意見を公表した。
事業者団体ヒアリングでは、FIT・FIPからの自立化には、燃料コストの低減が課題との説明があった。その一方、特に入札区分である「一般木質等(10MW以上)」および「液体燃料(全規模)」について、国際市場の需給や円安などの影響を強く受ける性質があり、新規の案件形成が大きく進むとは考えにくいとの説明があった。
詳しくはこちら
 https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/news/00001/04792/?ST=msb
https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/news/00001/04792/?ST=msb
●2025.2.4 日経新聞:再エネ支援、一部対象外 輸入材バイオマス、コスト下がらず
経済産業省は再生可能エネルギー支援の範囲を初めて縮小する。26年度から輸入木材などを使うバイオマス発電を対象から外す。輸入価格の高騰で新規参入が途絶え、将来的な発電コストも太陽光の4倍近くに高止まりするのが背景にある。
詳しくはこちら(一部会員限定記事)
 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO86502880U5A200C2MM8000/
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO86502880U5A200C2MM8000/
●2025.2.18 ヤフージャパン:輸入燃料はFIT打ち切り?バイオマス発電のカラクリ
経済産業省が、輸入木質燃料によるバイオマス発電へのFIT(固定価格買取制度)適用を打ち切りにする方針を決めた。
同様の措置は、ヨーロッパに続き韓国が先んじて始めている。日本も後追いしたわけだ。多少遅れたが、ようやく海外の動向に追いついたか……と思ったのだが、よくよく内容を確認すると、がっかりなカラクリが見えてきた。
今回経産省が打ち出した方針は、1万キロワット以上の一般木質(ペレット、チップ、ヤシ殻)などと、アブラヤシから搾ったパーム油など液体燃料について、2026年度以降の新規案件は、FIT等の支援対象外とするというものだ。
ここで気をつけないといけないのは、1万キロワット以上という条件と、2026年以降に認定を受けた発電所としている点だ。たしかに輸入燃料を使用する発電所は規模が大きく1万キロワット以上が多い。だが、このクラスの建設申請は、2022年以降は1件もないのである。一方で、すでに建設され稼働している1万キロワット以上の大規模発電所には適用しないのだから、現状の改革にはならない。
現在、建設中を含めると1万キロワット以上の大型バイオマス発電所は100を超すほど存在するが、それらは今後最長20年間稼働を続け、輸入木質バイオマス燃料も使用し続けるわけだ。まさに、誰も困らない見せかけだけの規制である。
詳しくはこちら
 https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/768e1a99d259883cd4397d4ce4612e96e7dbf25f?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1tIS0DuOhNJ9mbgeaA90tM6ZDb-TkG35DHg4IX-Np2Mk1SraIRnaEyrZI_aem_4Dc42HEtyu-M1G30sMzlBg
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/768e1a99d259883cd4397d4ce4612e96e7dbf25f?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1tIS0DuOhNJ9mbgeaA90tM6ZDb-TkG35DHg4IX-Np2Mk1SraIRnaEyrZI_aem_4Dc42HEtyu-M1G30sMzlBg
●2025.2.18 ヤフージャパン:木質バイオマス発電を目的に設立された山形バイオマスエネルギーが特別清算
山形バイオマスエネルギー(株)は、2月4日に山形地裁より特別清算開始命令を受けた。当社は、2015年(平成27年)6月に木質バイオマス発電を目的に設立され、2019年度の稼働に向けて設備投資を行っていた。しかし、2019年2月、発電プラント引き渡し前の試験運転中に爆発事故が発生。爆発事故後も、安全性を確保したうえでの事業継続を模索したが、追加の設備投資が必要であったことから断念。
詳しくはこちら
 https://news.yahoo.co.jp/articles/cdd92195125d4d0451b7a7d06151d9ea6bcf5571
https://news.yahoo.co.jp/articles/cdd92195125d4d0451b7a7d06151d9ea6bcf5571
【違法伐採問題】
●2025.1.14 Mongabay:インドネシアの科学者、違法な錫採掘の実態を暴露して非難を浴びる
インドネシアの環境法医学専門家バンバン・ヘロ・サハルジョ氏は、スズ・ロンダリング事件での違反容疑者に不利な証言を行ったが、そのバンバン氏が訴訟を起こされる可能性がある。
検察側の証人としてバンバン氏は、バンカ・ブリトゥン諸島の錫産地での違法採掘をめぐる汚職事件により、環境被害総額は271兆ルピア(約166億ドル)に達したと法廷で証言した。これに対し、バンカ・ブリトゥン地域全体の代表と主張する弁都市のアンディ・クスマ氏は、バンバン氏の査定が地元の錫鉱山産業に悪影響を及ぼしたと主張する被害届を警察に提出した。
この錫採掘事件は、環境被害の評価額という点では、これまでで最大の事件である。検察は、インドネシアの最大の採掘業者である国営ティマ社の元CEOを含む幹部らが民間組織と結託し、一連のダミー会社を通じて違法に採掘された錫をロンダリングしたとしている。
バンバン氏の評価によると、2015年から2022年にかけてティマ社の採掘権内で行われた違法採掘は、広範囲にわたる環境破壊を招き、保護林や海洋生態系に影響を及ぼした。同産業の環境被害は深刻であることが長年の研究で示されており、森林破壊、生物多様性の喪失、水系の劣化がバンカ・ブリトゥンの生態系と伝統的な生活、特に漁師の生活に損害を与えている。
活動家らは、バンバン氏に対する被害届を、スラップ(司法制度を利用して批判者を脅迫し、沈黙させる行為)の典型的な例だとしている。
環境NGOのアウリガ・ヌサンタラは、インドネシアで2014年から2023年の間に環境保護活動家に対するスラップ訴訟が少なくとも133件発生したと記録している。活動家らは、このような事件は将来の内部告発を抑止する可能性があると警告している。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/01/indonesian-scientist-under-fire-for-revealing-extent-of-illegal-tin-mining/
https://news.mongabay.com/2025/01/indonesian-scientist-under-fire-for-revealing-extent-of-illegal-tin-mining/
【パーム油問題】
●2025.2.12 Food Ingredients 1st:パーム油の代替品:NoPalm Ingredientsが酵母由来脂肪を商業化へ
オランダのバイオテクノロジー企業NoPalm Ingredientsは、副産物から酵母由来の食品グレード油脂を12万リットルの工業レベルにまで拡大し、これを「世界で初めて」達成したと主張している。
CEO の Lars Langhout 氏は、同社の酵母油はパーム油の「真の代替品」であると述べている。融点や粘度などの主要な要素が一致しており、従来のパーム油と同等の価格を提供する。「当社は微生物を改良しているわけではない。その代わりに、原料、酵母菌株、プロセスの組み合わせを最適化している。」と述べている。
同社によると、この油脂はアップサイクルされた農産物の副産物の発酵を利用して作られ、二酸化炭素排出量がパーム油に比べて90パーセント少なく、使用する土地も99パーセント少ないという。また、「多くの企業が当社との協力に熱心である。当社は現在、規制当局の承認プロセスを進めており、今年後半に必要な承認が得られると期待している。」と同社は述べている。
原文はこちら(英語)
 https://www.foodingredientsfirst.com/news/substituting-palm-oil-nopalm-ingredients-scales-fermentation-based-fats-for-commercialization.html
https://www.foodingredientsfirst.com/news/substituting-palm-oil-nopalm-ingredients-scales-fermentation-based-fats-for-commercialization.html
●2025.1.10 Mongabay:ボルネオでのパーム油の管轄認証の試験運用にNGOが懸念を表明
2023年10月、バンカルの先住民族ダヤク村で、インドネシアの警察は、BESTグループが所有するアブラヤシ農園会社、ハンパラン・マサウィット・バングン・ペルサダ(HMBP)に反対するデモを行っていた農民たちに発砲した。デモ参加者らは、ベスト・グループの子会社が「プラズマ」と呼ばれる義務的な利益分配制度において小規模農家に対する法的義務を果たさなかったと主張した。
現行のRSPOルールでは、パーム油生産者は、マレーシアに拠点を置く同組織に、個々の農園の承認を申請することになっている。
一方、管轄認証の試みは2015年にマレーシアのサバ州で始まり、その後エクアドルとインドネシアのセルヤン地区に拡大された。RSPOは、この制度が規模拡大と、政府の能力・権限の活用によってコスト削減につながることを期待していると述べている。またRSPOは、「認証を取得するのは管轄区域であり、その区域内で生産されたパーム油はRSPOに準拠しているとみなされる」とも述べている。
しかし、インドネシアの複数の市民グループは、区域全体のパーム油生産を承認することは、人口16万6000人以上のセルヤンのような場所で地元レベルで長年続いている数多くの紛争を隠蔽するリスクがあると述べている。
「これらの措置は本当に地域コミュニティのためなのか、それとも市場の利益を満たすためだけなのか」と、11月に他のNGOとともにこの問題に関する報告書を発表したインドネシアの非営利団体「正義のための変革(TuK)」のアブドゥル・ハリス氏は述べた。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/01/ngos-raise-concerns-over-borneo-pilot-of-jurisdictional-certification-for-palm-oil/
https://news.mongabay.com/2025/01/ngos-raise-concerns-over-borneo-pilot-of-jurisdictional-certification-for-palm-oil/
●2024.12.17 Mongabay:インドネシア固有のエンガノ島でパーム油が先住民族社会に広まる
エンガノのような海洋島は、マグマが上昇して新しい陸地ができた際に形成され、現在、多くの固有種が生息し、6つの異なる先住民族集団が自給自足の暮らしを送っている。
1990年代初頭以来、開発業者らが島の大部分の支配権を獲得しようとしてきたが、6つの先住民部族からの強固な反対に遭遇してきた。
現在は、ロンドン・スマトラ・グループと関係があるとされるスンベル・エンガノ・タバラク社(SET社)が、1万5000ヘクタールを超えるアブラヤシ農園の造成を目指しており、2022年にエンガノでアブラヤシ栽培の許可を申請した。ある住民によると、SET社は地元住民にアブラヤシの苗木を無料で提供すると申し出て、自給自足農家の一部にこの新たな換金作物を勧めようとしており、バンジャル・サリとカアナの2村では、住民が自宅の庭にアブラヤシを植えはじめ、その面積は30ヘクタールになっているという。
市民社会の研究者や先住民族の長老たちは、島には地域コミュニティとアブラヤシ農園の両方に必要な十分な水はなく、大規模な農園の造成は生態系の危機をもたらす危険性があると述べている。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2024/12/on-indonesias-unique-enggano-island-palm-oil-takes-root-in-an-indigenous-society/
https://news.mongabay.com/2024/12/on-indonesias-unique-enggano-island-palm-oil-takes-root-in-an-indigenous-society/
【コミュニティ】
●2025.1.15 ブラジル日報:文明未接触の先住民族を撮影ーアマゾン密林に設置したカメラで
国立先住民保護財団(FUNAI)は8日、ロライマ州内陸部の森林内に設置したカメラで撮影された、今まで記録されたことのない先住民族の写真を公開した。彼らはロライマ州アルタ・フロレスタ・ド・オエステとサン・フランシスコ・ド・グアポレの間にある、先住民族保護地域(TI)のマサコ先住民族居住区で生活している。
この調査は昨年1月から4月にかけて、未接触部族や孤立部族保護の専門家8人で構成されたチームによって、彼らの痕跡や活動を記録する目的で行われた。調査団は密林の中を5日間で約65キロメートル移動しながら、孤立部族の活動の痕跡を記録するためのカメラなどを設置した。
マサコ先住民族居住区は1998年12月11日に政令によって境界策定が行われた。約42万ヘクタールを超え、97.5パーセントがグアポレの保護地区となっている。
グアポレ地区では常に先住民族の土地への不法侵入、伐採などの違法行為が行われないように監視や保護活動が行われている。FUNAIは保護強化のため、清掃や境界修復も担っている。
FUNAIは、孤立部族がこの区域にいるということは、彼らの生活を保護し、外部との接触を避けるための保護体制を更に強化させる必要が明確になったとした。
他にも、マット・グロッソ州リオ・パルドのカワヒバ族の保護地区でも未接触民族が確認された。
詳しくはこちら
 https://www.brasilnippou.com/2025/250115-11brasil.html
https://www.brasilnippou.com/2025/250115-11brasil.html
●2025.1.14 Mongabay:クラホ族の女性たちが領土を守るために先住民警備隊を率いる(ブラジル)
南米の先住民コミュニティでは、領土の保護は主に男性の責任であると考えられている。しかし、ブラジルのトカンティンス州では、クラホ族の女性たちが、侵入者から領土を守るために女性だけの監視グループを結成した。こうしたことはこの地域では珍しいことである。監視グループはこれまでに、先住民族の領土への侵入に関連する脅威を1件特定し、ブラジルの先住民保護機関であるFunaiに報告することができた。
30.3万ヘクタールのクラホ先住民族保護地域(TI)は、伐採業者、狩猟者、アグリビジネス、木炭工場からの大きな圧力にさらされており、クラホ族の土地の水は、近くの大豆・綿花の農園に散布された殺虫剤によって汚染されている。
女性監視グループのメンバーの一人、ルイザ・クラホ氏は、監視グループは、領土の境界の農民や他の人々からすでに何度も脅迫や批判を受けていると語った。「この仕事には多くの危険が伴います」と彼女は言う。「しかし、私たちは危険を恐れて諦めてはいけません。こうしたことは長い間続いており、私たちを破滅させているのです。」
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/01/kraho-women-lead-surveillance-actions-to-protect-territory-in-brazil/
https://news.mongabay.com/2025/01/kraho-women-lead-surveillance-actions-to-protect-territory-in-brazil/
●2024.12.11 Mongabay:国連が人権保護団体向け人権保護に関するガイドラインを策定
国連環境計画は最近、既存の人権基準10項目についておよび、これらを環境保護団体や資金提供者(COF)にどのように適用すべきかを詳述した報告書を発表した。生物多様性の深刻な喪失と気候危機に対応するため、多くが北半球の団体である民間の自然保護団体が、グローバルサウスに保護区を設置するようになった。しかし、保護区予定地に住む周縁化されたコミュニティに対し、適切な保護措置が取られていないため、人権侵害の報告が相次いでいる。
たとえば、コンゴ民主共和国では、サロンガ国立公園を管理している世界自然保護基金(WWF)が、環境活動家によって公園近隣のコミュニティの人権が侵害されたとの申し立てを知りながらも、資金と物質的な支援を続けていた。タンザニアのセレンゲティの保護と持続可能な開発を支援するフランクフルト動物学協会は、非暴力的および暴力的にマサイ族の立ち退きに関与したタンザニア国立公園局に、保護資金と機材を提供していた。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/short-article/2024/12/un-sets-guidelines-for-conservation-groups-to-safeguard-human/
https://news.mongabay.com/short-article/2024/12/un-sets-guidelines-for-conservation-groups-to-safeguard-human/
●2024.11.7 Mongabay:コロンビア先住民族の土地の守護者”ウルフ”が殺害される
ウルフのニックネームを持ち、先住民族の土地の守り人・教育者であったカルロス・アンドレス・アスキュ・トゥンボ氏(30歳)は、今年、コロンビアで殺害された115人目の社会指導者となった。
彼はキウェ・テグナス(カウカ先住民警備隊)の一員として、コミュニティの森、土地、若者を違法な武装集団とコカ栽培から守っていた。
警察の捜査は続いているが、コミュニティのメンバーは、カルロス氏が、先住民族ナサ族の人々が40年以上も闘ってきた武装集団と麻薬密売人の犠牲になったと考えている。
武装グループがコカインを生産するために行っているコカ栽培は、人々の生活だけでなく環境にも影響を与えている。伝統的に神聖な作物であるコカは、今やこの地域の暴力と荒廃に結びついている。
コロンビア法務省によると、栽培の48パーセントは国立公園、集団的領土、森林保護区などの特別管理地域に集中している。国連薬物犯罪事務所の最新の報告書によると、2022年から2023年の間に、コカ栽培により1万1829ヘクタールの森林が破壊された。この森林破壊は2023年に10パーセント増加し、生物多様性を脅かし、 50種以上の生物を絶滅の危機に晒していると、法務省は生物多様性条約第16回締約国会議で述べた。
カウカでは、エスタード・セントラル・マヨールやダゴベルト・ラモス戦線など、いくつかの反体制グループが活動している。これらのグループは2016年の和平合意後に現れ、社会復帰プロセスを拒否または放棄した元コロンビア革命軍(FARC)ゲリラで構成されている。
先住民警備隊のリーダー、オベイマール・テノリオ氏は、「武装集団はもはやかつてFARCを特徴づけていた政治的イデオロギーを持っていない。代わりに、先住民警備隊に対する彼らの攻撃は、麻薬ルートの利益と支配によって動かされている。」と述べている。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2024/11/the-underreported-killing-of-colombias-indigenous-land-guardian-the-wolf-photos/
https://news.mongabay.com/2024/11/the-underreported-killing-of-colombias-indigenous-land-guardian-the-wolf-photos/
【日本は今!】
●2025.3.3 読売新聞:大船渡の山林火災発生から6日、市の人口の11パーセントが避難生活…進学控える女子高生「新生活も心配」
岩手県大船渡市の山林火災は、発生から6日目となった3日も延焼が続き、焼失面積は300ヘクタール増えて約2100ヘクタールに拡大した。市内では1896世帯4596人に避難指示が出され、市の人口の約11パーセントにあたる3661人が避難生活を送っている。
火災は2月26日に同市赤崎町で発生。山林火災による焼失面積は平成以降で最大となっており、80棟超の建物被害が出たとみられているが、詳しい調査はできていない。
詳しくはこちら
 https://x.gd/Whp7r
https://x.gd/Whp7r
●2025.2.28 テレビ金沢:【解説】“能登の木材” 地震・豪雨で例年の半分に 能登半島の林業の現状 復活のカギは…
能登半島地震以降、競りにかけられる木材の量は減っているといいます。能登の木材のほとんどを扱っている能登木材総合センターの年間の取扱量ですが、去年1年間の数字は例年の半分ほどとなっています。その最も大きな理由としてあげられるのが、林道の変化です。
能登森林組合・山田 峻伊智 さん:「地震の影響で山が崩れて、道を完全にふさいじゃっているような状況です」「この先、道の先で仕事があるんですけど、現場に行くことができない状況です」
石川県によりますと、こうした林道の被害は県内全体で2200箇所あまり確認されています。
詳しくはこちら
 https://news.yahoo.co.jp/articles/16a6eca45a5161e2c3d05ba40b3c8987f7c98c88?page=1
https://news.yahoo.co.jp/articles/16a6eca45a5161e2c3d05ba40b3c8987f7c98c88?page=1
●2025.2.27 テレビ宮崎:花粉量1パーセント以下のスギ苗木も 宮崎県内で「花粉症対策苗木」の植栽進む
宮崎県内では、花粉の少ないスギの苗木による再造林が進められています。
川南町にある林田樹苗農園。ここで栽培されている苗木はすべて『少花粉スギ』。
県内で作られているスギの苗木のうち9割以上を従来の苗木と比較して、花粉の飛散が1パーセント以下の「少花粉スギ」と20パーセント以下の「低花粉スギ」が占めています。
宮崎県内では、2002年から花粉が少ないスギの苗木による再造林が行われていて、現在はスギ林の10パーセント以上が花粉の少ないスギに植え替えられています。
詳しくはこちら
 https://news.yahoo.co.jp/articles/e0e4a5f930da244c06ef763a7283f26425f96c2e
https://news.yahoo.co.jp/articles/e0e4a5f930da244c06ef763a7283f26425f96c2e
●2025.2.19 林政ニュース:広葉樹の利活用へプラットフォームの創設を、推進会議が提言
林野庁が設置している「里山広葉樹利活用推進会議」(土屋俊幸座長)は、2月12日に東京都内で3回目の会合を開いて検討成果をまとめ、「里山広葉樹利活用・再生プラットフォーム」(仮称)を創設して情報共有や需給マッチングを進めるよう提言した。林野庁は、来年度(2025年度)予算などを活用して提言の実現を目指す。
詳しくはこちら(一部有料記事)
 https://rinseinews.com/news/9047/
https://rinseinews.com/news/9047/
●2025.2.18 林政ニュース:「立木市場」が本格スタートへ、国の補助なくし“自立”を目指す
民有林を対象に「立木市場」(立木取引システム)の創設を目指す取り組みが新たなステージに入る。国(林野庁)の補助事業を活用して進めてきた売買マッチングシステムの基本設計などが完了し、来年度(2025年度)からインターネット上で民間同士の取引が本格的に始まる。山元立木価格の決定過程を透明化する従来にない試みがいよいよ実行段階に移る。
詳しくはこちら
 https://rinseinews.com/news/8917/
https://rinseinews.com/news/8917/
●2025.2.12 長周新聞:メガソーラーや大規模風力による災害や健康被害を規制する方策 日弁連主催シンポジウム(2) 法的課題と地域共生型電力のあり方も論議
日本弁護士連合会が1月29日におこなったシンポジウム「メガソーラー及び大規模風力による開発問題への法律・条例による対応について」で、小島智史弁護士は、全国各地で違法行為・脱法行為や開発による土砂災害、水源枯渇などが多発しているにもかかわらず、法整備が追いついていないために有効に対応できていないこと、にもかかわらず政府が「保安林解除の迅速化」など、さらなる規制緩和を進めていることを報告した。
パネルディスカッションでは、法律では対応できないなら、地方自治体が制定する条例でどのように実効性ある対応ができるかが論議された。
詳しくはこちら
 https://www.chosyu-journal.jp/shakai/33755
https://www.chosyu-journal.jp/shakai/33755
●2025.2.11 長周新聞:メガソーラーや大規模風力による災害や健康被害を規制する方策 日弁連主催シンポジウム(1) 長崎県宇久島や秋田県由利本荘市から報告
全国各地でメガソーラーや大規模風力発電の建設によって、土砂災害の発生や低周波音の健康被害が現実的なものとなり、地域住民が反対の声をあげ、再エネ規制条例を制定する自治体が増えている。そうしたなか日本弁護士連合会は1月29日、シンポジウム「メガソーラー及び大規模風力による開発問題への法律・条例による対応について」を、東京の会場とオンラインのハイブリッド方式で開催し、以上の問題に現時点の法律でいかなる対応が可能か、法律が無理ならどのような条例の制定が必要かの論議を深めた。
長崎県宇久島のメガソーラー事業は、開発面積が720ヘクタール、島の4分の1の広大な土地に太陽光パネルを設置するもので、豪雨による土砂災害の危険が増幅する可能性がある。そこで、講演者の島谷幸宏熊本県立大学特別教授は、事業者・九電工に対応策を提言している。
秋田県由利本荘市周辺では陸上に53基の風力発電が稼働している。風力発電が民家の近くで稼働し始めてから、頭痛、めまい、耳鳴り、不眠、動悸などの体調不良を訴える人が出るようになった。2022年9月6日、由利本荘・にかほ市の風力発電を考える会とAKITAあきた風力発電に反対する県民の会が秋田県庁で記者会見を開き、地域住民に健康被害が出ているとして、発電事業者に夜間の運転停止を訴えた。
詳しくはこちら
 https://www.chosyu-journal.jp/shakai/33748
https://www.chosyu-journal.jp/shakai/33748
●2025.2.10 林政ニュース:2024年の林産物輸出額が667億円に増加、近年で最高に
昨年(2024年)の林産物輸出額が対前年比7.5パーセント増の667億円に増加し、近年における最高値を記録した(財務省貿易統計による)。林産物の輸出額は上昇基調で推移してきており、コロナ禍の影響で2023年は同2.7パーセント減の621億円に減少したが、再び増加に転じた。
詳しくはこちら(一部有料記事)
 https://rinseinews.com/news/8908/
https://rinseinews.com/news/8908/
●2025.2.5 日本経済新聞:レノバ、静岡のバイオマス発電の運転開始
再生可能エネルギー開発大手のレノバは5日、静岡県のバイオマス発電所の商業運転を始めたと発表した。同発電所は当初23年7月に運転開始を予定していたが、安定稼働のためボイラーやタービンの調整に時間がかかっているとして、運転開始時期の延期を繰り返していた。生み出した電気は国の固定価格買い取り制度(FIT)を使って販売し、燃料は海外製の木質ペレットやパームやし殻(PKS)を使う。
詳しくはこちら
 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC05A2M0V00C25A2000000/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0oIOLbzr3FRKHTjskPy_vgaxZgZDuSfskGuU9LFpQWsNinn97-XRlvcks_aem_iCvbzC0eiyRzHJPpUixSNQ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC05A2M0V00C25A2000000/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0oIOLbzr3FRKHTjskPy_vgaxZgZDuSfskGuU9LFpQWsNinn97-XRlvcks_aem_iCvbzC0eiyRzHJPpUixSNQ
●2025.2.5 ヤフージャパン:木質バイオマス発電の新宮フォレストエナジー合同会社(和歌山)が破産
新宮フォレストエナジー合同会社は、1月23日に和歌山地裁より破産手続き開始決定を受けた。
和歌山県新宮市において、紀南地域において産出された間伐材や低質材などを活用し、自社工場でウッドチップに加工・乾燥して発電の熱源に利用する木質バイオマス発電事業を行っていた。
しかし、収入高は10億円に届かない水準にとどまっていたうえ、木材の切り出しや輸送に多額のコストを要し、採算が悪化。輸入材のほか、国内他府県産材などを用いることで採算改善を図っていたものの、2022年以降は円安の進行に加え、発電に必要となる燃料コストの上昇も重なって採算はさらに悪化。厳しい運営を強いられていた。
詳しくはこちら
 https://news.yahoo.co.jp/articles/254bc3b0bc52bb0cf29651c4e747e18ede08bbcb?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2aKTCqfkdF6uZoib13JAhhKZAbt0dDKbsrROD7A6Jd4eNNxfucptM9ias_aem_D9ufepFWW60uA8rXAA4BOQ
https://news.yahoo.co.jp/articles/254bc3b0bc52bb0cf29651c4e747e18ede08bbcb?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2aKTCqfkdF6uZoib13JAhhKZAbt0dDKbsrROD7A6Jd4eNNxfucptM9ias_aem_D9ufepFWW60uA8rXAA4BOQ
●2025.2.5 日刊工業新聞:最大傾斜約50度の急斜面で実証成功、「地ごしらえ」無人化へ
東京電機大学や福島県ハイテクプラザなどが参画する産学官連携組織「下刈機械自動化コンソーシアム」は、福島県いわき市で同県林業の復興・再生に向けた実証実験を実施した。最大傾斜約50度の急斜面で無線操縦地ごしらえ機とウインチアシスト技術を活用し、機械地ごしらえに成功した。同コンソーシアムはこの成果を踏まえ、全自動林業機械の研究開発を進める。
実証実験では伊MDB製の急傾斜対応林業機械「LV800PRO」と、日本キャタピラーや住友林業、サナースが共同開発したウインチアシスト(テザー)技術を組み合わせた。
詳しくはこちら
 https://newswitch.jp/p/44577
https://newswitch.jp/p/44577
【中国情報】
●2025.2.22 木材網:中国が輸入木製品の関税を調整
中国は内需拡大、高水準の生産促進を目指し、2025年関税調整計画を発表し、2025年1月1日より施行された。
関税調整計画のうち、935品目の商品については最恵国税率よりも低い輸入暫定税率が適用され、良質な製品の輸入拡大に有利となる。木炭、フローリング材、合板等の木製品の輸入について税率が調整された。
24の自由貿易協定および特恵貿易協定に基づき、2025年から34の国または地域から輸入される一部の製品には合意された関税率が適用される。
原文はこちら(中国語)
 https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=84869
https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=84869
●2025.2.22 木材網:ロシアの原木輸出量の75パーセントは中国へ
木材輸送に従事するロシア鉄道運営企業、TransLes社の分析データによると、2024年、中国が輸入した原木はロシアの原木輸出量の75パーセントを占めた。2024年のロシアの原木の対外輸出量は160万トンであった。
専門家によると、2024年に中国の対ロシア木材の需要は5パーセント減少したが、2025年は中国の対ロシア木材の需要はさらに増加する見込みであるという。
原木以外に、ロシアは昨年は930万トンの製材を輸出し、主な輸出先も中国であり、2024年のロシアの製材の中国向け輸出量は670万トンであった。
原文はこちら(中国語)
 https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=84864
https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=84864
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆フェアウッド×木のある暮らし~循環の家・伝統知の家がつくる未来
2025年3月13日(木)18:00~20:00@大手町3×3ラボ
参加費2,000円【学生無料】
 https://fairwood.jp/event/250313/
https://fairwood.jp/event/250313/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「いまの暮らしを、もっと木のある環境にしたい。」そう思っている若い人たちは多いのでしょうか?
震災、コロナ、気候変動、少子高齢化など、私たちの取り巻く課題は難しいですが、「あたたかな家、あたたかな家庭、人とのつながり」といった願いは、それを乗り越え、より一層、人々の心に広がっていると思います。そこには、「木の温もりある暮し」が必要なのではないでしょうか。そこで、木の家をもっと身近にし、次世代に手渡したいと考えます。
日本の風景を彩る、素晴らしい木の家づくり・木造建築は、地域の風土に調和した民家、神社仏閣などに見られます。その地域で採れる資源・自然素材が使われ、大工の知恵、地域共生の知恵がそこかしこにあります。それらは、決して古くはならず、今だからこそ、「わたしたちの暮らし」を見つめ直すために様々な示唆を与えてくれます。
自然の恵みである木や竹、土など自然素材を生活の中に取り入れることで、「暮らすこと」のプリミティブな喜び、人間本来のニーズを呼び起こし、今の暮らしに活かすことはできないでしょうか。本会は、それらを実践してきたお二人をお迎えして対談形式でお送りします。
全国に亘り伝統建築・民家集落等の調査研究を行い、校倉造りなど伝統工法を現代の建築設計に活かしてきた里山建築研究所の居島さんと、長野県・山梨県・関東圏を中心に、地域の人たちと自ら森林や竹林に入り、環境に配慮した自然住宅「循環の家」をつくるアトリエデフの戎谷さんをお迎えします。
全てを言い尽くせませんが、どちらも地域全体の「自然環境の活性化」や「丁寧な暮らしのコミュニティを生む」、新しい価値感の家づくりに未来を感じます。環境・社会に配慮した木材利用を進めるフェアウッド・パートナーズと、大手町・丸の内・有楽町のまちづくり団体であるエコッツェリア協会の共催によるプログラム第二弾です。二度とないこの機会に、どうぞ皆さまお誘いあわせの上、ご参加ください。
■日時:2025年3月13日(木)18:00~20:00(受付開始17:30)
■参加費;2,000円、*学生、エコッツェリア協会会員は無料
■対象:学生~社会人(学生、若手社会人歓迎)
■会場:3×3Lab Future
 https://www.ecozzeria.jp/about/accessmap.html
https://www.ecozzeria.jp/about/accessmap.html
東京メトロ、都営地下鉄大手町駅(C10出口)より徒歩2分
■プログラム
イントロダクション
講演1:居島 真紀 氏/里山建築研究所
講演2:戎谷 純一 氏 /アトリエデフ
質疑応答&パネルディスカッション
モデレーター:野村 由多加 氏/Yutaka Create
■お申込み
お申し込みフォーム( https://fw250313.peatix.com)よりお申し込みください。
https://fw250313.peatix.com)よりお申し込みください。
フォームがご利用できない場合、「3/13開催フェアウッド×家具開催参加希望」と件名に明記の上、1)お名前、2)ふりがな、3)ご所属(組織名及び部署名等、学生の場合は学校名)、4)Eメールアドレス、5)チケット種類(有料参加、無料参加/学生またはエコッツェリア協会会員)、6)参加の動機やイベントへの期待などを、メールにてinfo@fairwood.jp まで送付ください。
■ゲスト詳細
●居島 真紀 氏/株式会社里山建築研究所 代表
富山県生まれ。土蔵の解体現場に立ち会い衝撃を受ける。伝統構法を研究、板倉構法を提唱する安藤邦廣研究室で、各地の古民家集落をフィールドワークし、深みにはまる。里山資源を生かした居住スタイル「板倉の家」を提案する里山建築研究所を設立。拠点となる筑波山麓北条で仲間と古民家を改修し、サードプレイス「iriai Tempo」の運営に携わる。
主なプロジェクト:かやぶきの里プロジェクト(2013グッドデザイン賞ベスト100)、板倉建築の普及啓発活動[板倉構法をハブとした震災復興のための一連の活動](2018グッドデザイン賞)、「AGRI CARE GARDENかすみがうら」(2021ウッドデザイン奨励賞)他
*里山建築研究所HP: https://satoyama-archi.co.jp/
https://satoyama-archi.co.jp/
●戎谷 純一氏/株式会社アトリエデフ 取締役専務
大学卒業後、実家の稼業を手伝うも、ログハウス建築に憧れ長野のログハウス会社へ転職。
在職中、日本の気候風土・日本人の気質に対してログハウスに違和感を感じ、デフへ就職。デフでは業務全般を担当。自然素材という観点から野外保育にも興味を持ち、森のようちえんの運営にも理事として参加。
*アトリエデフHP: https://a-def.com/
https://a-def.com/
●野村 由多加 氏/Yutaka Create 代表
山梨WOOD ROCK 事務局長
フェアウッド研究部会/事務局支援
美大助手となり李朝家具の研究とデザイン教育に奔走。2011年より株式会社ワイス・ワイスにて、企画・開発・広報・営業など幅広く担当。全国の林業地を訪問し、国産材・地域材を使った家具づくり・空間づくりに尽力。
2024年、山梨県北杜市に移住。都市と地域を結ぶ産業づくりや森林サービス、地域創生などを主なフィールドとし、「第2のふる里をあなたに。」をコンセプトに掲げたデザイン事務所を設立。地域文化を醸成し、地域を元気にするために、企業や自治体などのサステナブルプロジェクト推進・支援・デザイン制作を行う。また、山梨の地元材を積極的に使う木工作家グループ「山梨WOOD ROCK」を旗揚げする。
 https://www.instagram.com/yamanashi_woodrock/
https://www.instagram.com/yamanashi_woodrock/
■主催
フェアウッド・パートナーズ(国際環境NGO FoE Japan、地球・人間環境フォーラム)、佐藤岳利事務所
■共催
エコッツェリア協会(一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会)
■助成
緑と水の森林ファンド
■お問合せ
地球・人間環境フォーラム(担当:坂本)
 http://www.fairwood.jp、info@fairwood.jp、TEL:03-5825-9735
http://www.fairwood.jp、info@fairwood.jp、TEL:03-5825-9735
FoE Japan(担当:佐々木)
 http://www.foejapan.org、info@foejapan.org、TEL:03-6909-5983
http://www.foejapan.org、info@foejapan.org、TEL:03-6909-5983
※テレワーク推進中のため、極力メールにてお問合せをお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆改正クリーンウッド法の適正な施行・運用に向けた提言
 https://fairwood.jp/document/241001proposalcwa
https://fairwood.jp/document/241001proposalcwa
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
近年、国際社会では気候変動対策や生物多様性保全の観点から包括的な森林減少・劣化対策の必要性への認識が定着しています。2024年12月から施行される欧州森林減少防止規則(EUDR)も、違法伐採対策に主眼を置いていた前身の欧州木材規則(EUTR)を大幅に刷新しました。
日本の違法伐採対策法であるクリーンウッド法も改正され、2025年4月に施行されますが、違法伐採対策から森林減少対策へ推移した国際社会との課題認識の乖離が見られます。
日本政府による違法伐採対策によって日本の木材市場から違法リスクおよび森林減少リスクの高い木材が取り除かれ、世界の森林保全に寄与することを期待し、責任ある木材利用の実現に向けて提言します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆かわさきFM "TO THE NATURE"で紹介されました!
 https://www.youtube.com/watch?v=NOxPsgWUXcQ
https://www.youtube.com/watch?v=NOxPsgWUXcQ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
フェアウッド・パートナーズの事務局団体の一つである地球・人間環境フォーラム活動がFMかわさきの"TO THE NATURE"で紹介されました。
「カナダの原生林を燃やす日本の木質バイオマス 本当に二酸化炭素削減になるのだろうか?森の役割、豊かな生態系の価値。みんなで考えよう!」と題して、8月16日に放送されました。
Youtubeで視聴可能です。ぜひお聞きください。
 https://www.youtube.com/watch?v=NOxPsgWUXcQ
https://www.youtube.com/watch?v=NOxPsgWUXcQ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・みなさんの知人、友人、ご家族の方にもこのメールマガジンをお知らせしてください。メールマガジンの登録、バックナンバーはこちらです。
 http://www.fairwood.jp/news/newsbk.html
http://www.fairwood.jp/news/newsbk.html
・本メールマガジンの記事について、無断転載はご遠慮ください。
ただし、転載許可の表記のある場合を除きます。
・本メールマガジンに関するご意見・ご感想などは下記のEmailにお寄せくだ さい。お待ちしております。e-mail: info@fairwood.jp
発 行 : フェアウッド・パートナーズ  http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp
編 集 : 坂本 有希/三柴 淳一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
![]() http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp![]() https://fairwood.jp/event/
https://fairwood.jp/event/![]() https://www.sustainablebrands.
https://www.sustainablebrands.![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://www.reuters.com/
https://www.reuters.com/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://www.licas.news/2025/
https://www.licas.news/2025/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://digital.asahi.com/
https://digital.asahi.com/![]() https://digital.asahi.com/
https://digital.asahi.com/![]() https://project.nikkeibp.co.
https://project.nikkeibp.co.![]() https://www.nikkei.com/
https://www.nikkei.com/![]() https://news.yahoo.co.jp/
https://news.yahoo.co.jp/![]() https://news.yahoo.co.jp/
https://news.yahoo.co.jp/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://www.
https://www.![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://www.brasilnippou.com/
https://www.brasilnippou.com/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://news.mongabay.com/
https://news.mongabay.com/![]() https://x.gd/Whp7r
https://x.gd/Whp7r![]() https://news.yahoo.co.jp/
https://news.yahoo.co.jp/![]() https://news.yahoo.co.jp/
https://news.yahoo.co.jp/![]() https://rinseinews.com/news/
https://rinseinews.com/news/![]() https://rinseinews.com/news/
https://rinseinews.com/news/![]() https://www.chosyu-journal.jp/
https://www.chosyu-journal.jp/![]() https://www.chosyu-journal.jp/
https://www.chosyu-journal.jp/![]() https://rinseinews.com/news/
https://rinseinews.com/news/![]() https://www.nikkei.com/
https://www.nikkei.com/![]() https://news.yahoo.co.jp/
https://news.yahoo.co.jp/![]() https://newswitch.jp/p/44577
https://newswitch.jp/p/44577![]() https://www.chinatimber.org/
https://www.chinatimber.org/![]() https://www.chinatimber.org/
https://www.chinatimber.org/![]() https://fairwood.jp/event/
https://fairwood.jp/event/![]() https://www.ecozzeria.jp/
https://www.ecozzeria.jp/![]() https://fw250313.
https://fw250313.![]() https://satoyama-
https://satoyama-![]() https://a-def.com/
https://a-def.com/![]() https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/![]() http://www.fairwood.jp、info@
http://www.fairwood.jp、info@![]() http://www.foejapan.org、info@
http://www.foejapan.org、info@![]() https://fairwood.jp/document/
https://fairwood.jp/document/![]() https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?![]() https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?![]() http://www.fairwood.jp/news/
http://www.fairwood.jp/news/![]() http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp