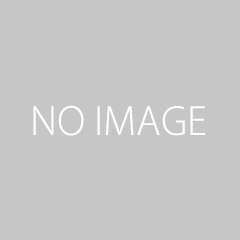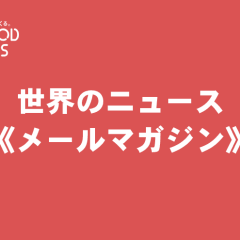--- フェアな木材を使おう --- http://www.fairwood.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
春を迎えている南半球のオーストラリアでは、森林火災が猛威を振るい始めています。近年の森林火災の現状について、研究者によるレポートが公開されている他、FAOが5年に一回に発行するレポートにおいて、森林減少の現状も報告されています。
再び延期が伝えられていたEUの森林減少防止規則(EUDR)に関しては、延期される対象が小規模事業者に絞られることが発表されています。
インドネシアにおける新たな違法伐採の報道や、英国のNGOであるアースサイトによるFSC森林認証の問題点が指摘されるなが、森林へ負のインパクトを与えない木材利用のあり方について、改めて課題が浮き彫りになっています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【森林減少】
●2025.10.22 RIEF:EU欧州委員会。「森林伐採規則(EUDR)」の今年末での施行の再延期問題。対象を小規模事業者に限定する案で合意。延期期間は未定。最終決定は欧州議会とEU理事会の調整に移行
EU欧州委員会は21日、今年末に予定している森林伐採規制(EUDR)の適用開始問題をめぐって、先にIT問題による遅れを理由に、1年間の延期案を打ち出していたが、最終的に延期は、全対象企業ではなく、規制対象の農林業商品を市場に流通させる小規模事業者に絞ることに変更する方針になった。欧州議会関係者がメディアに明かした。
それによると、欧州委が同日に開いた同問題での再審議の場で、環境担当欧州委員のジェシカ・ロスウォール(Jessika Roswall)氏と、規則の1年延期案を支持する欧州委副委員長のテレサ・リベラ(Teresa Ribera)氏との間で激しい議論になった末、EUDRは予定通り12月末(31日)に発効し、規制延期の適用対象を縮小する案に変更することになったという。
延期措置が適用されるのは、カカオ、コーヒー、木材、パーム油、家畜、ゴムなどの製品を扱う小規模・零細事業者だけに絞られる案とする。これらの小規模事業者の規制延期期間については、当初の延期案通りの1年後の2026年12月までとなる可能性があるとしているが、最終的な延期期間での合意はまだできていない模様。
また延期対象となる小規模生産者は、デューデリジェンス宣言(EU市場向け商品生産に伴う森林伐採がなかったことを証明する文書)についても簡素化された措置を適用されることになる。EUDRは本来、昨年末に施行される予定だったが、EU内外の関係業者等の反対で、すでに1年先送りされている。
詳しくはこちら
https://rief-jp.org/ct12/161751
●2025.10.21 FAO:世界の森林破壊は減速しているが、依然として圧力にさらされていると、国連食糧農業機関(FAO)が報告
最新のデータによると、森林面積は41億4000万ヘクタールであり、地球上の陸地面積の約3分の1に相当する。FRA2025によると、森林減少率の減速に加え、世界の森林にとって更なる明るい兆しが示されており、現時点で森林の半分以上が長期管理計画の対象となっており、5分の1が保護区として法的に守られている。
しかしながら、同報告書では、現在の年間1090万ヘクタールという森林減少率は依然として高すぎであり、世界中の森林生態系が依然として課題に直面していると指摘されている。
森林は、食料安全保障、地域住民の生活、再生可能なバイオマテリアルとエネルギーの供給にとって重要である。森林は世界の生物多様性の大部分が展開される場所であり、地球規模の炭素循環と水循環の調整に役立ち、干ばつ、砂漠化、土壌浸食、地滑り、洪水のリスクと影響を軽減することができる。
原文はこちら(英語)
https://www.fao.org/newsroom/detail/global-deforestation-slows--but-forests-remain-under-pressure--fao-report-shows/en
●2025.10.22 Reuters:豪・NZで異常熱波、山火事相次ぐ シドニーは春に40度超え
オーストラリアとニュージーランドで22日、猛烈な熱波の影響で各地で山火事が発生し、シドニーの一部では春としては異例の40度を超える気温が観測された。
最大時速100キロメートルの突風により山火事の危険性が高まっており、最も人口の多いニューサウスウェールズ州全域で屋外での全面的な火気使用禁止令が出された。豪当局によると36件の火災が発生し、このうち9件は鎮火していない。
シドニー西部の郊外では気温が40度に達し、中心部でも37度を超えた。気象局の予報官は「まだ春なのに信じられないほどの高温だ」と述べた。
ニュージーランドでは、極端な気象状況でしか出されない「赤」レベルの強風警報が中部と南部で出された。南島のカイコウラ近郊や北島のホークスベイで山火事が発生し、これまでに住宅5棟を含む複数の建物が焼失した。
詳しくはこちら
https://jp.reuters.com/markets/commodities/A6KUIIMOYFOO5ECWJPZYNFSFYY-2025-10-22/
●2025.10.20 alterna:過去1年で世界の森林火災が焼失した面積は、インドの国土よりも広い:報告書
世界の科学者らが、「森林火災の現状」に関する報告書をまとめた。2024年3月から2025年2月にかけて、世界で大規模な森林火災が発生し、CO2排出量は過去20年平均より1割多い80億トン超に達した。また同期間の土地の焼失面積は少なくとも370万km2と、インドの国土面積を上回った。科学者らは人為的な気候変動によって、炭素を豊富に含む森林での火災の規模・強度が増していると警告する。
報告書によると、2024年3月から2025年2月までの1年間で、世界では森林火災によって80億トン超のCO2を排出した。この数値は、2023年に記録を開始して以来6番目に高く、過去20年での平均を9%上回った。この上回った9%分の排出量だけでも、200カ国以上の化石燃料によるCO2排出量より多いと指摘した。
詳しくはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/6c2fe77936ed3bc2ca0628f19721675fe7bb53f2
●2025.10.28 Chita.ru:ザバイカル地方天然資源省が、2025年の森林火災の主な原因を特定
10月28日、ザバイカル地方立法議会における統一ロシア党の会合において、ザバイカル地方天然資源相代理のパベル・ヴォルジン氏が、2025年の同地方における森林火災の主な原因を特定した。
ヴォルジン氏によると、代理知事の任期が終了する今回の火災シーズン中に、ザバイカル地方では691件の火災(うち101件は住宅地での火災)が記録され、その面積は190万ヘクタールに及んでいる。同氏によると、最も多かった原因は人による不注意な火の取り扱いで、378件の火災が発生している。これらの火災により137万ヘクタールが焼失し、45件の刑事事件が起訴されている。
その次に多い原因は落雷(99件)である。3番目に多い原因は、農地からの延焼であり、いわゆる草地火災である。さらに、この地域では意図的な放火が10件、軍の射撃訓練に起因した火災が4件、ブリヤート共和国からザバイカル地方にかけて延焼した火災が3件確認されている。
原文はこちら(露語)
https://www.chita.ru/text/ecology/2025/10/28/76094626/
【違法伐採問題】
●2025.10.23 Earthsight:FSCは、自らが内包する数十億ドル規模の詐欺行為に対し対処するのか?
森林管理協議会(FSC)は、世界最大の環境ラベルである。世界の消費者の約半数が、木を象ったFSCのロゴを認識しているだろう。それは、ティッシュペーパーや家具、木材、書籍、さらには木質繊維で作られた衣類に至るまであらゆる製品に表示されている。消費者の8割は、このロゴにより当該製品が森林に悪影響を与えていないと確信している。しかしながら、消費者は騙されている。
実際には、消費者が購入している製品は、FSCによって認証されてはいるが、「持続可能」な森林から生産されたものではない可能性が高い。加えて、原材料が違法に伐採されている可能性さえある。
FSCのサプライチェーンには、詐欺が蔓延している。家具、トイレットペーパー、紙皿、木炭、床材、ペレットなど、幅広いFSC認証製品において詐欺行為が発覚している。熱帯材・非熱帯材、広葉樹・針葉樹の別に関わらず、幅広い木材カテゴリーに関して、組織的な不正行為が摘発されている。このような問題は中国において最も深刻であるが、欧州や米国を含む世界中においても同様である。
原文はこちら(英語)
https://www.earthsight.org.uk/news/FSC-billion-dollar-fraud
●2025.10.20 Wedge:日本の法律は穴だらけ!野放図に拡大する違法伐採、森林破壊を食い止める手立てはあるのか?
釧路湿原に建設されているメガソーラーが問題になっている。許可なく木を伐採したとして、森林法違反の疑いも出てきた。業者側は許認可を取ったと主張しているが、法の隙間を縫うような行為だからだ。
こうした合法性を疑われる森林開発は続発している。
輸入される木材や木質製品にも、森林破壊によって得た木材が混ざっているという指摘がされている。その中には盗伐など明らかに違法伐採された木材や、合法かどうか確認できないようなグレー木材も含まれている。
こうした森林破壊が進行しているのは日本ばかりではなく、世界中に蔓延している。そのため違法伐採、違法木材を取り締まる法律も各国で設けられてきた。しかし、本当に機能しているのだろうか。
詳しくはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/87a0e5ad8e2fd8bbb31b5ace6d62ddade5e6c8f7?page=1
●2025.10.15 Antara:インドネシア、メンタワイ諸島における大規模違法伐採を摘発
インドネシア当局はメンタワイ諸島における違法伐採を発見し、シポラの森林から4,610.16立方メートルの木材を押収した。
「これにより、国家は最大2,400億ルピア(1,400万米ドル)の損失を被ったと思われます」と、林業省林業犯罪局長のルディアント・サラギ・ナピトゥ氏は水曜日に述べた。
この度の押収は、10月4日に行われた合同現地捜査の結果である。ガルーダ・チーム森林地域執行部隊(PKH)と林業省職員は、伐採地域を封鎖し、シポラ森林管理局(HPT)の生産施設を差し押さえた。
現在、IMと名乗る人物とPT BRN社に対する捜査が行われている。
原文はこちら(英語)
https://en.antaranews.com/news/386257/indonesia-shuts-down-massive-illegal-logging-operation-in-mentawai
【バイオマス】
●2025.10.4 RIEF:日本の木質バイオマス発電で、米国南部の森林地帯が皆伐破壊され、木質ペレット製造工場の違法操業で周辺住民が健康被害。米NGOらが来日して日本政府や日本の電力消費者らに訴え
「日本の環境政策の影響で米国が大変な状況に陥っている」──米国のNGO幹部が9月下旬に来日し、日本がバイオマス発電用に米国から輸入している木質ペレットの生産活動等の影響で、米国の森林やコミュニティが破壊されている、と訴えた。
この数年で、日本国内の木質バイオマス発電に使われる木質ペレットの輸入が急増。その輸入の約2割が米国産だ。同発電は経済産業省の固定価格買取制度(FIT)の対象となっているが、来日した南部環境法律センターの弁護士ヘザー・ヒラカー(Heather Hillaker)氏は「木質バイオマス発電は再生可能エネルギーではない」と指摘している。
来日したのは、ヒラカー氏のほか、アラバマ州などでペレット工場建設の反対運動に携わるポーシャ・シェパード(Portia Shepherd)氏、英国や米国で活動する環境NGO「Biofuelwatch」の共同ディレクターのゲイリー・ヒューズ(Gary Hughes)氏。このほど環境金融研究機構の取材に応じたほか、東京でセミナーや記者会見も開き、国会議員や経済産業省や林野庁の担当部局等に、米国の現状を訴えた。
3人によると、ミシシッピ州など米国南東部に木質ペレットの生産工場が立地し、同地周辺の豊かな森林が伐採され、木質ペレットの製造に充当されているという。こうした開発の進行で、南東部の豊かな森林は、その生物多様性の損失のリスクに直面、絶滅が危惧される種も少なくないという。さらに、工場の操業による大気汚染や粉塵公害も起きて、地域住民を悩ましている。
同地で製造された木質ペレットは米国内での使用ではなく、大半が輸出に回されている。輸出先は英国や日本だ。実際に、日本の木質ペレットの輸入量は急増している。林野庁によると、2024年の木質ペレットの輸入量は638万トンで、20年の202万トンの3倍に増大している。638万トンの輸入量のうち米国産は約2割の118万トン。
日本では2012年に始まったFITによってバイオマス発電が急増してきた。3人を招いた「一般財団法人地球・人間環境フォーラム」によると、同発電燃料の7割が輸入バイオマスとされ、そのうちの多くが輸入木質ペレットで占められているという。
詳しくはこちら
https://rief-jp.org/ct7/161316
●2025.10.30 RIEF:インドネシアの生物多様性「宝庫」の島の森林を皆伐・製造した木質ペレットを、阪和興業が東京ガス向けのバイオマス発電燃料として輸入。環境NGO等が両社に公開質問状送付
アジア等の森林伐採に原料を依存する日本のバイオマス発電事業影響を懸念する非営利機関や環境NGO等が連名で、インドネシアで日本向けバイオマス発電用の木質ペレット製造事業に関わらう日本の阪和興業と東京ガスの2社に対して、公開質問書を送付した。日本向けの木質ペレット輸出ではベトナム産が有名だが、同ペレットは認証偽造等の不正問題が表面化、燃料の爆発・火災問題も頻発したことから、新たにインドネシア産の生産/輸入が増大しているという。
しかし、日本等からの急速な需要の集中で、現地では生物多様性豊かで絶滅危惧種・固有種の生息地でもある熱帯林が大量に伐採され、伐採後には固有種ではない早生樹の単一植林に転換され、生物多様性の破壊が進行しているとされる。
詳しくはこちら
https://rief-jp.org/ct7/161957
【パーム油問題】
●2025.10.23 Reuters:軍が農園を接収、インドネシアのパーム油業界に恐怖が広がる
6月下旬、インドネシア軍兵士たちが軍服姿でボルネオ島にある民間パーム油農園に進軍し、農園が政府の管理下にあることを示す看板を掲げたと、同農園の経営者らが述べた。
約370万ヘクタール(910万エーカー)の農園が接収され、そのほぼ半分が新興国営企業アグリナス・パルマ・ヌサンタラに移管された。これにより同社は、保有土地面積で世界最大のパーム油企業となった。
プラボウォ・スビアント大統領が命じた取り締まりは、インドネシアのパーム油産業における最大の構造変化であり、合計500万ヘクタールが軍の監視下に置かれた。これは同国のパーム油栽培総面積の約30%に相当し、オランダの面積よりも広い。
この地域は最終的にアグリナス社に引き渡される可能性があるが、業界専門家によると同社には管理能力が不足していると指摘されている。
原文はこちら(英語)
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/fear-grips-indonesian-palm-oil-industry-military-seizes-plantations-2025-10-23/
【日本は今!】
●2025.10.4 産経新聞:外国に買われる森林、昨年は東京ドーム81個分も 05年以前は実態不明 外資規制はなし
国内で、昨年1年間に外国人や外国法人に買われた森林(私有林)が382ヘクタールあったことが林野庁の調べで分かった。東京ドーム(広さ約4.7ヘクタール)81個分、東京ディズニーランド(約51ヘクタール)では7.5個分にもあたる広さだが、同庁によると、こうした事態に外資規制は「ない」というのが現状だ。このまま”放置”し続けていて日本の山林は大丈夫なのか。
北海道が最多 大半が「資産保有」のため
同庁によると、住所が海外にある外国法人と外国人による取得は計48件あった。面積は計171ヘクタールだ。内訳をみると、北海道が富良野市やニセコ町、倶知安町など36件(162ヘクタール)と最多だった。中国や香港の個人など、大半が「資産として保有するため」という理由からで、28件を数えた。白糠町では「太陽光発電」設置のため、シンガポールの法人が93ヘクタールを得ていた。
詳しくはこちら
https://www.sankei.com/article/20251004-PGEQZEGOYFAHTJNV3ICREAQ4XM/
●2025.10.20 PresidentOnline:外国人でも簡単に「日本の水」を支配できる…全国各地で着々と進む「中国人による森林買収」の二大リスク
日本の森林を外資が購入するケースが相次いでいるのはなぜか。中国人の生態や活動をウォッチしているルポライターの昭島聡さんは「地下水は土地所有者の私有財産という日本の特異な法制度のせいで、水源を買えば豊富な水を支配できてしまうからだ」という──。
日本の水源地が、じわじわと外資の手に落ちていく──その事実に、私たちはどれほど気づいているだろうか。
おそらく、その最初の舞台となったのが、三重県大台町。宮川ダム湖のほとりに広がる原生林の静けさを破ったのは、中国系企業の突然の打診だった。2008年のことである。
町側は「水源林としての保全を望む」としてこれを拒否し、交渉は打ち切られた。
この一件を契機に、各地の自治体や森林組合に危機感が広がっていく。
詳しくはこちら https://president.jp/articles/-/103824?page=1
●2025.10.18 TBSNEWS:マツ新品種「クリーンラーチ」野ネズミなどの食害に強くCO2吸収量多い特徴 当麻町で植樹「地域で盛り上がる力に」
17日、北海道当麻町で、マツの新品種「クリーンラーチ」の植樹が行われました。
「クリーンラーチ」は道が開発したマツの新品種で、従来のカラマツよりも野ネズミなどの食害に強く、二酸化炭素の吸収量が多い特徴があります。当麻町では「クリーンラーチ」の苗木作りを地元の農協が担当し、栽培を全て町内で行うことでより多くの二酸化炭素の削減を目指しています。
詳しくはこちら
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2235909?display=1
●2025.10.27 Timee:タイミー、秋田県森林組合連合会と業務提携契約を締結
スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー(所在地:東京都港区、代表取締役:小川 嶺)は、秋田県森林組合連合会(所在地:秋田県秋田市、代表理事会長:小松 佳和)と業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。
日本における林業従事者の数は長期的に減少傾向で推移しており、国勢調査(総務省)によると2020年には4.4万人になっています。また、林業従事者の高齢化も課題となっており、2020年の林業における高齢化率は25%と全産業平均の15%と比較しても高水準となっています(※1)。
労働力不足や高齢化に加えて、デジタル技術導入の遅れやバックオフィス業務の非効率化なども課題となっており、これらの課題を解決することが林業界全体として急務となっています。
この度の業務提携では、秋田県森林組合連合会が有するノウハウや弊社がこれまで各産業において蓄積してきた知見をもとに、林業におけるスポットワークの活用を進めてまいります。秋田県森林組合連合会を通じて、森林組合や林業事業者に「タイミー」を紹介することで、労働力不足の解消を目指します。
詳しくはこちら
https://corp.timee.co.jp/news/detail-5403/
【中国情報】
●2025.9.30 CCTV(中国中央電視台):トランプ米大統領が10月14日から輸入木材等への追加関税を決定
トランプ米大統領は現地時間9月29日、輸入木材に10%、輸入キャビネット、バスルームキャビネット及び木製家具に25%の追加関税を課すと発表した。
新たな関税は10月14日から発効し、一部の税率は来年1月1日からさらに引き上げられる。
原文はこちら(中国語)
https://news.cnr.cn/sq/20250930/t20250930_527381442.shtml
●2025.10.11 中国木材網:EU、中国産広葉樹合板に約90%の反ダンピング関税
EUは、2025年12月7日より中国産広葉樹合板の輸入に対し大幅に引き上げられた反ダンピング関税を課すと発表した。具体的には、江蘇省ヒ州市の生産者に対する関税は従来の25.1%から43.2%に引き上げられ、その他の中国国内の生産者には最大86.8%の関税が課される。
Paged Plywood社のヤロスワフ・ミフニウク副会長はこの決定を歓迎し、欧州企業と雇用を保護し、不公正な貿易慣行に対抗する上で有益だと述べた。グリーンウッド・コンソーシアムも今回の措置を支持し、一部輸入業者が製品分類を操作して関税回避を図り、市場に潜在的な脅威をもたらしていたと指摘した。
今回の反ダンピング措置はTARIC関税分類コードを通じて実施され、欧州合板業界の公正な競争環境を維持すると同時に、反ダンピング政策の有効性を確保することを目的としている。
原文はこちら(中国語)
https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=85647
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆11/21 第89回フェアウッド研究部会「ネイチャーポジティブ実現に向けた生物多様性の定量評価~群馬みなかみ町を事例に」
https://fairwood.jp/event/251121/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
気候変動と並び、緊急の対応が求められる生物多様性保全。世界のどこでも共通で使える炭素量という指標のある気候変動とは異なり、地域によって異なる指標等を検討する必要のある生物多様性では、客観的な定量評価の手法が国内外でさまざまに議論・検討されています。
日本自然保護協会は昨年、生物多様性を客観的かつ定量的に評価する6つの手法を公表しました。この手法は、自然保護協会が群馬県みなかみ町、三菱地所と結んでいる連携協定の中で進めている活動の一環で開発されたもので、みなかみ町に手法をあてはめて評価した結果も合わせて公表されています。
今回の研究部会では、この開発に携わった日本自然保護協会の高川晋一さんを講師に迎えて、手法の詳細や課題、今後の展望をお聞きします。2050年の世界目標として合意されたネイチャーポジティブの実現に向けて、日本の自然保護に携わる立場、または関心を寄せる立場から何ができるのかのヒントを探りたいと思います。
自然共生サイトなどを活用して日本各地で生態系保全に取り組む自治体やNGO・NPO、またTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)に対応しようとする企業の皆様の参加をお待ちしています。
参考:日本自然保護協会プレスリリース(2024年7月8日)「ネイチャーポジティブ実現に向けた、生物多様性を客観的に評価する6つの手法を策定」
【開催概要】
日時:2025年11月21日(金)18:00~19:30(開場:会場は15分前、オンラインは5分前)
場所:ハイブリッド(zoom×地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)東京都渋谷区神宮前 5-53-70国連大学ビル 1F)
参加費:一般 1,500 円、学生無料(いずれも懇親会費別)
定員:会場 25 名、オンライン 90 名
※懇親会は会場参加者のみご参加いただけます。当日の受付の際にお申込み・お支払いを承ります。
※会議 URL:お申込みいただいた方に後日ご案内いたします。
※お申込みいただいた方で希望のある場合は、当日の録画アーカイブを後日、期間限定でご覧いただくことが可能です。
【プログラム】(敬称略、内容は予告なく変更することがあります)
第1部:講演(18:00~19:30 質疑含む)
講師:高川 晋一/公益財団法人日本自然保護協会 自然のちから推進部 主任
第2部:懇親会(会場参加者の希望者のみ、別会場にて開催予定)
【講師プロフィール】(敬称略)
高川 晋一(たかがわ・しんいち)/公益財団法人日本自然保護協会 自然のちから推進部 主任
東京大学農学生命科学研究科にて博士号を取得後、2006年より現職。市民を主体にした全国規模の自然環境モニタリング調査や、全国の約8000人の自然観察指導員の活動支援・養成、都市近郊の里山の保護問題、里山の保全活動計画の策定支援などを担当してきた。
現在は自治体と企業とのパートナーシップの下にネイチャーポジティブの実現を目指す新たな事業を担当しているほか、環境省の自然共生サイト・生物多様性評価に関する委員も務めている。専門は保全生態学、生物多様性評価、市民科学、環境教育。
【お申込み】
お申し込みフォーム(https://fw251121.peatix.com)よりお申し込みください。
フォームがご利用できない場合、「第88回フェアウッド研究部会参加希望」と件名に明記の上、1)お名前、2)ふりがな、3)ご所属(組織名及び部署名等)、4)Eメールアドレス、5)参加方法(会場またはオンライン)、6)(会場参加の場合)懇親会の出欠を、メールにてinfo@fairwood.jp まで送付ください。
【主催】
国際環境 NGO FoE Japan、地球・人間環境フォーラム、佐藤岳利事務所
【後援】
マルホン
【助成】
緑と水の森林ファンド
【問い合わせ】
FoE Japan(担当:佐々木)
http://www.foejapan.org、info@foejapan.org
地球・人間環境フォーラム(担当:坂本)
http://www.fairwood.jp、info@fairwood.jp
※テレワーク推進中のため、メールにてお問合せお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆ウェブサイト『バイオマス発電info』を公開しました!
https://bioenergyinfo.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地球・人間環境フォーラム(以下GEF)は、日本の再生可能エネルギー固定価格買取(FIT)制度が支援する「輸入木質バイオマス発電」の課題について理解を促すための最新動向やデータを提供するウェブサイト『バイオマス発電info』(https://bioenergyinfo.jp/)を公開しました。
「バイオマス発電info」は、主にメディア関係者と再エネに関心を寄せる事業者や金融機関を対象に、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)で支援されている輸入木質バイオマスが、再エネとして「持続可能」なのかを検証できる情報を提供しています。
“カーボンニュートラル”で“地産地消”とされる木質バイオマス発電の気候変動対策としての有効性や燃料生産地における環境・社会への悪影響などをわかりやすく解説し、「輸入木質バイオマス発電」をFIT制度で支援することが本当に「持続可能」と言えるのか、考えるサイトです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆レポート「持続可能なバイオマスプログラム:持続不可能なものを認証する」を発行!
https://www.gef.or.jp/news/info/250731sbpreport/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地球・人間環境フォーラムは、海外の環境NGO、4団体の共同でレポート『持続可能なバイオマスプログラム:持続不可能なものを認証する』を発行しました。
日本語版レポートの公開は10月上旬を予定しています。
バイオマス発電は、経済産業省の「再生可能エネルギー固定価格買取」(FIT)制度で「カーボンニュートラルな再生可能エネルギー」とされ、消費者負担の再エネ賦課金を原資に支援されてきました。
製材の残材や間伐材を燃料とすると言われてきましたが、実際には約7割の発電所で、海外から輸入される木質ペレットやパーム核殻(PKS)を燃やしています。2024年の輸入量は、木質ペレット638万トンとPKS 600万トンに上っています。
当団体では過去にカナダ・ブリティッシュコロンビア州の現地視察を行い、ペレット生産と原生林等の貴重な森林の伐採と関係など、現地の問題をお伝えしてきました。
本レポートは、カナダのペレット工場のケーススタディも踏まえて、現地で広く用いられている「持続可能なバイオマスプログラム(SBP)」の問題点を解説するものです。
日本のFIT・FIP制度は燃料の持続可能性の証明を「認証」に過度に依存しており、SBPも既に証明方法として認められています。早急な見直しに向けて、本レポートは極めて重要な分析を提供しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆フェアウッド・マガジン 世界のニュース登録方法を追加しました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
フェアウッド・パートナーズが、毎月、無料で配信している「フェアウッド・マガジン 世界のニュース」の登録・削除方法を追加しました。
これまでは、外部のメールマガジン配信サービス「まぐまぐ」のみとなっていましたが、フェアウッド・パートナーズからのダイレクト配信システムを加えました。いずれも無料ですので、以下からお好みの方法で登録してください。
https://fairwood.jp/mailmagagine/16/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・みなさんの知人、友人、ご家族の方にもこのメールマガジンをお知らせしてください。メールマガジンの登録、バックナンバーはこちらです。
https://fairwood.jp/worldnews/
・本メールマガジンの記事について、無断転載はご遠慮ください。
ただし、転載許可の表記のある場合を除きます。
・本メールマガジンに関するご意見・ご感想などは下記のEmailにお寄せくだ
さい。お待ちしております。e-mail: info@fairwood.jp
発 行 : フェアウッド・パートナーズ http://www.fairwood.jp
編 集 : 坂本 有希/三柴 淳一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです
◎フェアウッド・マガジン-世界のニュース
の配信停止(unsubscribe)はこちら
⇒ https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=147706&e=sagaragef%40gmail.com&l=scj1851435