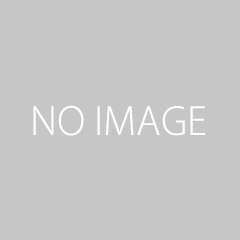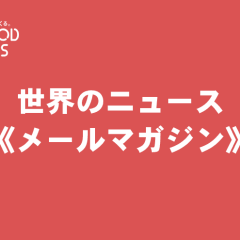--- フェアな木材を使おう ---  http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41.2度という日本最高気温が7月末に更新されました。8月にはさらなる記録が出るかもしれません。
気候変動への対策として推進されているEVや水力、バイオマス発電が森林破壊を引き起こすというニュースを複数取り上げました。鉱物資源の開発は森林を壊滅させ水源を汚染し、環境と社会に多大な影響を与えます。大規模水力発電は森林とコミュニティを水没させ、バイオマス発電は石炭以上の排出量を出し燃料生産地では森林を減少・劣化させています。
一方、若い二次林の炭素吸収量の多さが科学的に確認され二次林の保護が植林よりも有効であることが示されたり、アブラヤシ農園での在来種の混植が、生態系機能と生物多様性を向上させ、生産量も落とさないという研究結果が報告されています。
吸収源かつ炭素ストックである健全な森林を維持回復することが気候変動対策としても生物多様性保全にも有効であることが広く認識され、自然の再生力を最大限に引き出すことができれば、未来にまだ希望をつないで行けるのかもしれません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【森林減少】
●2025.6.9 Mongabay:EUのEV需要が熱帯林の森林破壊の新たな波を引き起こす
欧州連合(EU)は2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを約束した。この目標を達成するには、EU全体の排出量の75パーセントを占める交通システムを電気自動車にアップグレードする必要がある。
しかし、この供給源となる採掘活動は、新たな炭素排出につながる可能性がある。欧州の組織であるフェルンと、レインフォレスト・ファウンデーション・ノルウェーの委託を受け、生態経済学研究所とウィーン経済・経営大学が作成した報告書によると、EUの環境目標達成のため、2050年までに世界中で11万8000ヘクタールの森林が破壊される可能性がある。
影響の大きさは、自動車が使用するバッテリーの種類によって異なる。例えば、いわゆるNMC 811は欧州市場で最も一般的なバッテリーであり、大量のニッケルとコバルトを必要とする。一方、LFPはこれらの資源を必要とせず、森林破壊への影響も少ない。しかし、本報告書で分析されたすべてのシナリオにおいて、ブラジルはインドネシアと並んで森林破壊が最も深刻な国としてトップとなっている。
移行鉱物のリストには、銅、アルミニウム、マンガン、ニオブ、銀、ニッケル、コバルト、希土類元素、リチウムなど、数十種類の物質が含まれている。これらは電気自動車だけでなく、太陽光発電や風力発電といった他の低炭素エネルギーにも不可欠である。
この新たな鉱物ブームの影響は森林破壊にとどまらない。生物多様性の喪失、水源の汚染、そして伝統的コミュニティの権利侵害なども含まれる。国際人権団体ビジネス・人権リソースセンターは2024年、世界の重要な鉱物プロジェクトにおける環境破壊、労働災害による死亡、環境保護活動家への攻撃など、156件の人権侵害疑惑を追跡した。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/06/eu-appetite-for-evs-drives-new-wave-of-deforestation-in-tropical-forests/
https://news.mongabay.com/2025/06/eu-appetite-for-evs-drives-new-wave-of-deforestation-in-tropical-forests/
●2025.4.14 Mongabay:「ハート・オブ・ボルネオ」のダム群、インドネシアのグリーンエネルギー推進のために先住民族の森を破壊
インドネシア中央政府は、東南アジア最大の水力発電プロジェクトの一環として、北カリマンタン州の3つの河川沿いに5つのダムを建設する計画を推進している。ダム建設の費用は200億ドル以上と推定されている。2035年の完成時には、発電能力の合計は9,000メガワットになるとみられ、ブルンガン地区に建設中のカリマンタン工業団地の産業に電力を供給する予定。政府はこの場所を太陽光パネルとバッテリー製造の世界的な拠点にしたいとしている。
地元住民によると、最初のダムのためのトンネル工事は全長1キロメートル以上に達しており、北カリマンタン州当局は541世帯を早急に移住させる計画という。
2007年にブルネイとインドネシア、マレーシアの政府は、世界で最も広範な生物多様性を擁するボルネオ島の自然を保護する誓約である「ハート・オブ・ボルネオ」イニシアチブに署名した。
しかし、このハート・オフ・ボルネオにあるカヤン・ムンタラン国立公園(336万ヘクタール)の約2パーセントに相当する約244ヘクタールが、この水力発電プロジェクトのために水没することになる。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/04/heart-of-borneo-dams-raze-indigenous-forests-for-indonesia-green-energy-drive/
https://news.mongabay.com/2025/04/heart-of-borneo-dams-raze-indigenous-forests-for-indonesia-green-energy-drive/
【森林保全】
●2025.7.8 Mogabay:若い二次林は地球上で最も見落とされている炭素吸収源の一つである可能性がある
政府や企業が気候変動対策の公約達成に奔走する中、信頼性が高く、大規模に実施可能な炭素除去戦略として森林に注目が集まっている。植林が脚光を浴びる中、新たな研究では、よりシンプルで低コスト、より効果的な戦略があることが示唆されている。それは、既に存在している二次林の保護だ。
環境非営利団体「ザ・ネイチャー・コンサーバンシー」の研究チームが、世界中の10万以上の森林区画で、地上部の炭素蓄積量を100年以上の再生期間にわたり地図化した。その結果、森林の炭素除去率は、林齢、地域、生態系条件によって大きく異なり、最も成長の遅いサイトと最も成長の早いサイトで200倍の差が確認された。多くの森林が20~40歳で炭素吸収のピークを示し、再生後の最初の数十年で達成される除去量をはるかに上回る。特に熱帯森林は最も優れた性能を示し、23歳ごろに最大吸収量に達する。
この時間的動態には実践的な意味は、2025年に8億ヘクタール(オーストラリアの面積以上)の劣化した土地で自然再生を開始した場合、2050年までに203億tの炭素が吸収される可能性がある。このタイムラインを5年遅らせると、利益がほぼ4分の1に減少する可能性がある。しかし既存の若齢林は、一部の地域では1ヘクタール当たりの吸収量で新規植林の820パーセントを超える性能を発揮する可能性がある。
二次林は伐採のリスクが著しく高く、ラテンアメリカでは原生林の10倍の確率で失われ、ブラジルのアマゾンでは、半数が8年以内に破壊される。
現在の炭素市場メカニズムは、二次林の保護に対してほとんどまたは全くクレジットを提供せず、代わりに植林や古い林の管理に焦点を当てている。
排出量ギャップを埋める競争において、既に働き始めている森林を保護することは、苗木が成長するのを待つよりも速く、安価な方法かもしれない。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/short-article/young-secondary-forests-may-be-the-planets-most-overlooked-carbon-sink/
https://news.mongabay.com/short-article/young-secondary-forests-may-be-the-planets-most-overlooked-carbon-sink/
●2025.5.15 Mongabay:ボルネオのプロジェクトは、森林とアブラヤシが共存できることを証明しようとしている
サバで活動するNGOのHutan(ウータン)と、フランス農業開発研究国際協力センター(CIRAD)そしてマレーシア・プトラ大学が共同で運営している研究プロジェクト「TRAILS」は、マレーシアのボルネオ島で、パーム油の収穫量を大幅に減らすことなく、在来種の樹木をアブラヤシ農園に植えることができるかどうか、実験を行っている。
ウータンは、10年前には既にメランキン・アブラヤシ農園(MOPP)と協力し、川沿いの緩衝地帯に沿って1キロメートルの野生生物回廊の森林再生に取り組んでいた。このパートナーシップにより、MOPPはアグロフォレストリーを実施することに同意、キナバタンガンにある8,000ヘクタールの農園内の区画39ヘクタールで、実験が行われている。
プロジェクトに参加しているCIRADの研究者によると、実験はまだ初期段階だが、これまでのところ、アブラヤシの生育に悪影響はないことが分かっている。
TRAILSはまた、アブラヤシの植栽密度を減らした場合に何が起こるかについても実験している。話を聞いた栽培業者たちによると、光が当たる量が増えれば、アブラヤシはより多くの果実をつけるので、植栽密度が高い場合と比べて、生産量に大きな違いはないだろうと言う。アグロフォレストリーを導入しなくても、アブラヤシの密度を下げることで、必要な化学物質の投入量を減らすというメリットがある。
TRAILSプロジェクトに最も影響を与えた研究の一つは、ドイツのゲッティンゲン大学がインドネシアのスマトラ島を拠点に実施した試験であった。この研究では、成熟したアブラヤシの間に在来樹種の樹木島を形成することで、収量を低下させることなく生物多様性と生態系機能が向上するという結論が出された。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/05/borneo-project-hopes-to-prove-that-forests-and-oil-palms-can-coexist/
https://news.mongabay.com/2025/05/borneo-project-hopes-to-prove-that-forests-and-oil-palms-can-coexist/
【カーボンクレジット】
●2025.5.8 Mongabay:報告書は、炭素に関わる森林コミュニティの権利保護をめぐり、政策ギャップがあることを示している
アジア、アフリカ、ラテンアメリカの33か国を調査対象とした最近の報告書によると、政府による法律や政策の改革が行われていないことが、炭素排出削減計画に関わる先住民族、アフリカ系の人々、地域コミュニティの権利に影響を与えている。
アドボカシー団体「Rights and Resources International(RRI)」が発表したこの報告書は、炭素取引規制における森林、土地、資源に対するコミュニティの権利についての調査結果を概説している。
報告書によると、調査対象となった国の半数以上は炭素取引規制を持たず、半数近くは地域コミュニティの「自由意思に基づく事前の十分な情報に基づく同意」の権利を認める法的規定がない。
REDD+などのプログラムに10年以上資金提供や投資が行われてきたにもかかわらず、コミュニティの権利の衡平で意味のある認識に向けた進歩は依然として遅いと、報告書の著者であり、RRIの権利、気候、保全担当ディレクターのアラン・フレシェット氏は言う。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/05/report-shows-policy-gaps-in-safeguarding-the-carbon-rights-of-forest-communities/
https://news.mongabay.com/2025/05/report-shows-policy-gaps-in-safeguarding-the-carbon-rights-of-forest-communities/
●2025.4.9 Mongabay:スキャンダルの絶えないカーボンクレジット業界、アマゾンでの森林再生で汚名返上なるか
2024年、ブラジル最大のカーボンクレジット創出事業者に対する警察の強制捜査は、REDDプロジェクトの評判が長きにわたり危機的状況にあるなかでも、最悪の事態を招いた。
カーボンクレジットの価格が暴落する中、森林保全のための資金調達手段として、異なるタイプの事業が台頭しつつある。それは、アマゾンの広大な土地を再生することで吸収されるカーボンをクレジットとして販売するというものである。ブラジルは、1億900万ヘクタールの劣化した牧草地を抱えていることから、再生という「金の卵を産むガチョウ」として急浮上した。
ブラジルでは、このビジネスモデルが、鉱業や食肉産業、銀行、新興企業、大手テクノロジー企業の注目を集めている。
ブラジルの公共部門も森林再生のためのカーボンクレジット市場に参入した。連邦政府は、 2030年までに、北朝鮮とほぼ同じ面積の1,200万ヘクタールの在来植生を再生すると約束している。ブラジル在来植生再生国家計画(Planaveg)には、保護区などの公有地で、植生の再生に取り組む民間企業へのコンセッション発給も含まれている。植生の再生事業実施の見返りとして、企業はこれらの土地で創出されたカーボンクレジットを販売することができる。ルラ政権は2026年までに合計35万ヘクタールの公有林を民間企業に提供する計画である。
植生回復プロジェクトには多額の投資と長期にわたる取り組みが必要であり、深刻化する火災などの課題に直面し、カーボンクレジット市場の将来に関する不確実性にも対処する必要がある。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/04/for-scandal-ridden-carbon-credit-industry-amazon-restoration-offers-redemption/
https://news.mongabay.com/2025/04/for-scandal-ridden-carbon-credit-industry-amazon-restoration-offers-redemption/
【バイオマス】
●2025.7.30 東京新聞:木質バイオマス発電 エコじゃない? 事業への投融資、環境NGOが調査 金融機関は燃焼時CO2考慮を
木やヤシ殻などを燃料に発電する木質バイオマス発電は、国が固定価格買い取り制度(FIT)などで支援する再生可能エネルギーの一つ。だが、二酸化炭素(CO2)の排出や燃料輸入元で原生林が皆伐されるなど問題点が次々と指摘されている。環境問題に関わる国内の非政府組織(NGO)6団体は、大手金融機関が木質バイオマス発電事業に投融資する際の環境や人権などへの配慮を定めた方針を調べて評価、公表した。
詳しくはこちら(一部有料会員限定記事)
 https://www.tokyo-np.co.jp/article/424867
https://www.tokyo-np.co.jp/article/424867
●2025.7.11 日本経済新聞:再エネのレノバ、バイオマス発電の新規開発凍結 補助縮小や燃料高
再生可能エネルギー大手のレノバが木材などを燃やして発電する木質バイオマスの大型新規開発を凍結する。燃料が高いほか、政府補助の認定条件が厳しくなり、収益確保が難しいと判断した。石油資源開発(JAPEX)も新規計画がないなどバイオマスの拡大にブレーキがかかる。
詳しくはこちら(一部会員限定記事)
 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC247SP0U5A620C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC247SP0U5A620C2000000/
●2025.5.28 Mongabay:インドネシアのパルプ材およびバイオマス・プランテーションでは森林破壊と火災が続いている
インドネシアのNGOは、2023年以降、33の産業造林で森林および泥炭地の破壊、火災、先住民コミュニティとの土地紛争など、広範囲にわたる環境および社会違反を記録している。
南スマトラ州では日本の丸紅傘下のMHPが、813ヘクタールの土地を焼失し、ガワン・グミリル村の住民との間で土地紛争が続いていることが判明した。
また、大手企業のAPPとAPRILは、持続可能性に関する誓約を発表しているにもかかわらず、それに従わず、違法な森林伐採や、泥炭地の排水を行い、適切な同意手続きを踏まなかったとされている。
この2社は、世界をリードする持続可能な森林認証機関である森林管理協議会(FSC)の基準にも違反している。APRIL社とAPP社はかつてFSCの会員だったが、大規模な森林破壊と社会紛争への懸念が継続していることから、それぞれ2013年と2017年に脱退した。
APPの場合、FSCとの再交渉に関して、紛争の解決と回復を優先すべき泥炭地および森林地域の回復に取り組んでいると述べた。しかし、再交渉プロセスは現在中断されている。
NGOは、現在の違反行為がインドネシアの気候目標を損ない、EUの森林伐採規則に基づく市場へのアクセスを脅かす可能性があると警告し、法執行の強化と改革を促している。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/05/deforestation-and-fires-persist-in-indonesias-pulpwood-and-biomass-plantations/
https://news.mongabay.com/2025/05/deforestation-and-fires-persist-in-indonesias-pulpwood-and-biomass-plantations/
【違法伐採問題】
●2025.05.16 Mongabay:カンボジアの環境ジャーナリスト、オウク・マオ氏が逮捕される
違法伐採に関する報道で身体的にも、法的にも攻撃を受けていたカンボジア人ジャーナリスト、オウク・マオ氏が5月16日に逮捕された。地元オンラインメディアで働くマオ氏の同僚たちは、その後、彼を逮捕した男たちが憲兵隊員であると特定した。人権監視NGOのアドホックも逮捕を確認し、マオ氏を拘束した男たちは制服を着ていなかったと指摘した。
「令状なしで行われた恣意的な逮捕により、マオ氏が長らく耐えてきた厳しい司法上の嫌がらせはさらに悪化した」と国境なき記者団アジア太平洋支局長セドリック・アルビアニ氏は声明で述べ、氏の即時釈放を求めた。
マオ氏への攻撃は、2024年6月にストゥントレン州のコミュニティフォレストが皆伐されたことについての調査に関し、軍警察から尋問を受けたことから始まった。2024年8月、彼はモンガベイの協力を得て、カンボジア軍とつながりのある鉱山会社が伐採を行っていたことを突き止めた。モンガベイがこの件を報じた後、マオ氏はカンボジアの森林保護活動で豊富な実績を残してきたにもかかわらず、国有林での違法伐採の罪で起訴された。
その後、マオ氏はプレイロング野生生物保護区における森林破壊について取材を続けてきた。その結果、2025年3月、少なくとも元警察官1名を含む者から暴行を受けた。また、環境省から名誉毀損と扇動の新たな容疑で告訴されている。
今回の逮捕は、カンボジアにおける報道の自由の縮小と、長きにわたり政権を握ってきたカンボジア人民党に批判的な市民社会活動家を沈黙させようとする政府のキャンペーンを背景に起きた。
ジャーナリスト保護委員会の東南アジア上級代表ショーン・クリスピン氏は、当局に対し、マオ氏の釈放と「捏造されたあらゆる容疑の撤回」を求めた。「環境問題を報道したジャーナリストへの嫌がらせは、この地域で最も悪質な環境犯罪の温床となっているカンボジアにとって、イメージダウンに繋がります。また、この国の報道の自由に関する悲惨な記録に新たな汚点が加わることになります。」
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/05/cambodian-environmental-journalist-ouk-mao-arrested/
https://news.mongabay.com/2025/05/cambodian-environmental-journalist-ouk-mao-arrested/
【パーム油問題】
●2025.5.23 Mongabay:分析によると、コミュニティベースのバイオ燃料はパーム油に代わる「賢明な」選択肢になる(インドネシア)
インドネシアの現在のバイオ燃料戦略は、バイオディーゼル規制B40および近々導入されるB50を満たすためにアブラヤシ農園の拡大に大きく依存しており、環境および社会に最大47億2000万ドルの損害をもたらす可能性があると、環境NGOマダニ・ベルケランジュタンの新たな分析が警告している。
インドネシアでは、今年1月より、ガソリンスタンドで販売されるすべての軽油に、パーム油由来のバイオディーゼルを40パーセント配合すること(B40)が義務付けられている。政府は来年、この比率をB50に引き上げる計画で、これは世界で最も野心的なバイオディーゼル移行プログラムの一つとなっている。
現行のB40の義務だけでも、1,420万トンのパーム原油(CPO)の供給が必要で、B50計画では、この供給量が1,800万トンに増加し、パーム油産業の環境負荷の大きさに対する懸念が高まっている。
マダニは分析の中で、この義務を果たすため、アブラヤシ農園の開発を続けるという現状のシナリオ(BAU)と、既存の農園からの産出量を増やし、各コミュニティがアブラヤシ以外のバイオディーゼル作物を自ら生産する機会を与えられる、という代替シナリオとを比較した。
その結果、代替シナリオは、森林破壊と社会紛争を回避し、地域経済を支え、現状のシナリオ(BAU)での313.6億ドルと比較して、371億ドルと、より高い利益を生み出す可能性があるという。
研究者らは、インドネシアのアブラヤシ農園は生態学的限界に近づいていると警告し、取り返しのつかない環境被害を防ぐために、農園の造成規制と既存の農園での生産性向上、バイオ燃料原料の多様化へと転換するよう主張している。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/05/community-based-biofuels-offer-sensible-alternative-to-palm-oil-for-indonesia-analysis-shows/
https://news.mongabay.com/2025/05/community-based-biofuels-offer-sensible-alternative-to-palm-oil-for-indonesia-analysis-shows/
●2025.4.29 Mongabay:パーム油会社がボルネオの森林を伐採、オランウータンの生息地が危機に瀕している
ファースト・ボルネオ・グループ傘下のインドネシアのパーム油会社エクアトール・スンベル・レゼキ(ESR)は、西カリマンタン州の絶滅危惧種、オランウータンの生息地で伐採を開始し、保護価値の高い(HCV)森林とオランウータンの生存を脅かしている。
自然保護論者は、ESR社が大規模な伐採を計画しており、最大1万ヘクタールの森林が失われるリスクがあると警告している。
環境NGOサティア・ブミのアンディ・ムッタキエン代表は、政府がなぜESR社のコンセッションを非森林地域に指定したのか、つまり自然林が存在するにもかかわらず商業開発を許可する地域として指定するのかについて疑問を呈した。政府は2000年にこのゾーニングの変更を承認したと伝えられている。彼は政府に対し、アブラヤシプランテーション造成の申請プロセスを直ちに停止し、ESR社のコンセッションの包括的な生態学的調査を実施するよう求めた。
ファースト・ボルネオ・グループは複数の子会社を通じて長年にわたり大規模な森林破壊を行ってきた。これを受けて、ムシム・マスやゴールデン・アグリ・リソーシズ(GAR)などのパーム油取引業者を含む多数のバイヤーは、同グループからの購入を停止する措置を迅速に講じた。
しかし、いくつかの企業は、その取引先工場として、ファースト・ボルネオ・グループの子会社であるAUSを挙げている。AUSを取引先工場に挙げている企業には、アヴリル、インドラマ、オレオン、阪本薬品工業、ステアリネリー・デュボワ、VVFに加え、エイボン、バリー・カレボー、バイヤスドルフ、ゼネラル・ミルズ、グルポ・ビンボ、ライオン、明治、モンデリーズ、ネスレ、P&G、PZカソンス、レキットベンキーザー、ユニリーバといった消費財ブランドが含まれる。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/04/orangutan-habitat-under-siege-as-palm-oil-company-clears-forest-in-borneo/
https://news.mongabay.com/2025/04/orangutan-habitat-under-siege-as-palm-oil-company-clears-forest-in-borneo/
●2025.4.15 Mongabay:インドネシアの贈収賄スキャンダルで、パーム油大手の汚職を無罪放免した裁判官が起訴される
インドネシアの裁判官4人(アリフ氏、アガム氏、アリ氏、書記官ワユヒ氏)と弁護士2人が、注目を集めた汚職事件でパーム油大手のペルマタ・ヒジャウ、ウィルマー、ムシム・マスに有利な判決を下すために賄賂を受け取ったとして4月13日に起訴された。
検察は、これらの企業が仲介者の弁護士を通じて最大357万ドル(600億ルピア)を裁判官に流用し、総額10億ドルを超える罰金を回避したと主張している。
これら3社は、全国で食用油が深刻な不足に陥っていた2022年に、許可された量を超えてパーム原油(CPO)を輸出したとして、汚職容疑で裁判にかけられていた。2023年初頭、貿易省職員、著名な経済学者、そしてパーム油会社幹部3名が、輸出スキャンダルへの関与を理由に有罪判決を受け、投獄された。ところが、その後の企業に対する裁判で、裁判官(アリフ氏・アガム氏・アリ氏)は、各社は起訴に値しないとの判決を今年3月19日に下した。
この異例の判決は、オランダ植民地時代の名残である「起訴なしの免責」と呼ばれるもので、輸出は当時の貿易政策に準拠していたという根拠に基づいていた。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/04/judges-charged-in-indonesian-bribery-scandal-after-clearing-palm-oil-giants-of-corruption/
https://news.mongabay.com/2025/04/judges-charged-in-indonesian-bribery-scandal-after-clearing-palm-oil-giants-of-corruption/
【コミュニティ】
●2025.6.5 Mongabay:アマゾンの非接触民族を認識する方法:アンテノール・ヴァズ氏へのインタビュー
非接触民族(Peoples in Voluntary Isolation and Initial Contact:PIACI)の認定手法と保護政策に関する国際的な専門家であるアンテノール・ヴァス氏は、非接触民族の権利の保護及び促進に取り組む国際作業部会であるGTI PIACIの地域顧問として、彼らの存在を政府、先住民族組織、NGOが証明するのに役立つ新しい報告書の作成におけるコーディネートに携わった。
報告書によると、自ら孤立して生活している先住民族の記録は188件だが、そのうち国家によって正式に認められているのはわずか60件である。
非接触民族の存在を認識することがなぜ必要であるのかについて、ヴァス氏は以下のように説明した。「先住民族であろうとなかろうと、国家がその存在を認める場合にのみ、法の対象となる。(新しい報告書によると、)現在、南米には孤立して生活している先住民族に関する記録が188件存在する。これらの記録が存在するのは、我々が各国で徹底的な調査を実施し、特定の地域での孤立民族に関する証拠や情報を明らかにしたためである。一方、国家が認めているのはそのうち60件のみである。
つまり、国には存在しない先住民族が128民族いることになる。彼らは国にとって存在しないため、権利を有していない。権利がなければ、彼らの領土には、他者、特に経済的利益を持つ者がアクセス可能となるのだ。」
また、非接触民族の存在を確認し、認識することが、生物多様性の保全に貢献することになるのかについて、ヴァス氏は次のように述べた。「主な問題は、非接触民族が自然に100パーセント依存しているということである。自然に何らかの変化があれば、真っ先にその影響を被るのはこれらの人々である。先住民族の世界観は、概して森と深く結びついている。だからこそ、土地は(彼らにとって)経済的価値のある空間ではなく、生命なのだ。」
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/06/methods-to-recognize-the-amazons-isolated-peoples-interview-with-antenor-vaz/
https://news.mongabay.com/2025/06/methods-to-recognize-the-amazons-isolated-peoples-interview-with-antenor-vaz/
●2025.5.22 Mongabay:先住民族の権利擁護者が自然保護法の撤廃を求める請願書を提出(インドネシア)
インドネシアでは、国が指定した保護地域が慣習地と重なることが多く、従来と同じように先祖伝来の土地に住み、その土地を管理している先住民族が、起訴されたり投獄されている。
2024年に制定された新たな自然保護法は、土地の管理に関する先住民族の権利を認めるものと、多くの人は期待していた。ところが、先住民族による自然の管理はもっとも効果的なもののひとつであるという科学的証拠があるにもかかわらず、この法律はコミュニティを疎外し続け、彼らの伝統的慣習を犯罪とみなす可能性がある。
先住民族の権利擁護者らは、新法は先住民族の実質的な参加なしに可決されたと主張しており、AMAN、Walhi、Kiaraなどの団体が新法の無効化を求めて憲法裁判所に司法審査請願を提出した。
非政府組織「フォレスト・ウォッチ・インドネシア」のアドボカシー・キャンペーン・マネージャー、アンギ・プトラ・プラヨガ氏は、新法の第9条には、保護区内の土地権利保有者が保護活動の実施を拒否した場合、補償と引き換えに土地権利を放棄しなければならないとの規定があると述べた。この規定の問題は、政府による保護活動とみなされるものが、インドネシア最古の部族の一つであるメンタワイ族のような先住民族の慣習とは異なる可能性があるということである。
先住民族の権利擁護者らは、インドネシアの保護地域(2,740万ヘクタール)内に6,744の村があり、1,630万人が暮らしていると指摘した。
保護地区に住むこれらのコミュニティは依然として法的に認められておらず土地保有権を保障されていないため、犯罪者として扱われ土地から追い出される危険にさらされているとフォレスト・ウォッチ・インドネシアのアドボカシー・キャンペーン・マネージャー、アンギ・プトラ・プラヨガ氏は述べた。
本稿掲載時点では、司法審査は憲法裁判所で審議中である。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/05/indigenous-rights-advocates-petition-to-overturn-indonesian-conservation-law/
https://news.mongabay.com/2025/05/indigenous-rights-advocates-petition-to-overturn-indonesian-conservation-law/
●2025.5.9 Mongabay:世界銀行、開発プロジェクトによる被害に対処する歴史的な枠組みを発表
世界銀行は、国際金融公社(IFC)を含む民間部門を通じて、同行が融資したプロジェクトにより引き起こされた環境および社会への損害に対処するための初の枠組みを発表した。
「これは歴史的な出来事です。IFCが融資するプロジェクトが被害を引き起こした場合、救済措置を講じなければならないという、IFCにとって初めての指令です」と、国際環境法センターの人・土地・資源プログラムディレクター、カルラ・ガルシア・ゼンデハス氏は語った。
世界銀行は、プロジェクトにより引き起こされた社会的・環境的被害への対応が遅いとして、長年批判されてきた。「苦情を申し立てても、対応するまで10年近くも待たされることになる」と、リベリアの市民社会団体グリーン・アドボケーツのプログラム責任者、フランシス・コリー氏はモンガベイに語った。
(ただし今回の指令も)この状況を改善する可能性は低く、新たな苦情のみに適用される。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/short-article/2025/05/world-bank-launches-historic-framework-addressing-harms-from-development-projects/
https://news.mongabay.com/short-article/2025/05/world-bank-launches-historic-framework-addressing-harms-from-development-projects/
●2025.4.9 Mongabay:10年の遅延の後、先住民権利法案の可決を求める圧力が高まる(インドネシア)
インドネシアの先住民権利法案は、可決すると繰り返し約束されていたにもかかわらず、10年以上も議会で停滞している。
インドネシアの先住民連合であるAMANは、2003年にこの法案を初めて提案し、先住民の権利と土地を守り、根深い不正義に対処するために不可欠であると主張した。下院は2012年にこの提案を可決し、正式に審議プロセスを開始した。
しかし、2014年以来毎年立法上の優先事項として挙げられているにもかかわらず、この法案には大きな進展が見られない。
人権団体は、この遅延は土地や資源の管理権を手放すことへの根深い抵抗を隠すための都合の良い言い訳だと見ている。
市民社会連合のメンバーであるアリンビ・ヘロエポエトリ氏は、議会で第3位の議席を持ち与党連合を構成するゴルカル党が、この法案の重要性を繰り返し軽視してきたと指摘した。(一方、)ナスデム党は先住民権利法案への支持を正式に表明しているが、与党連合には参加しておらず、議席数は12パーセント未満である。
法案が可決されれば、先住民族の先祖伝来の土地、文化慣習、自治の権利が国内法に明記され、長らく待たれていた法的確実性がもたらされることになる。現在、先住民族に関する事項は、34もの異なる分野の規制の管轄下にあり、それが官僚的で時間のかかる承認プロセスにつながっている。その結果、多くのコミュニティが未だに認められず、保護も受けておらず、紛争に対して非常に脆弱な状態にあると、NGOのカオエム・テラパックのベニ氏は述べている。
2024年だけでも、AMANは、土地をめぐる紛争を687件特定、それらの紛争で、先住民コミュニティは1100万ヘクタールの土地を失った。少なくとも925人が犯罪者として扱われ、60人が国家治安部隊による暴力を受けた。
NGOのワルヒのウリ氏は、議会が8月までに法案を可決できなかった場合、NGO連合は1万人の先住民による大規模デモを組織する計画だと述べた。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/04/after-decade-of-delays-pressure-mounts-on-indonesia-to-pass-indigenous-rights-bill/
https://news.mongabay.com/2025/04/after-decade-of-delays-pressure-mounts-on-indonesia-to-pass-indigenous-rights-bill/
【日本は今!】
●2025.7.17 日刊工業新聞:住友林業緑化、樹木輸送を鉄道・船舶にモーダルシフト
住友林業緑化はJR貨物、川崎近海汽船、日本通運と連携し、独自の樹木配送サービス「緑配便」を提供している。幹線輸送を従来のトラックから鉄道・船舶にモーダルシフトし、2022年からの本格運用で脱炭素化を推進。長距離の樹木物流において二酸化炭素(CO2)排出量を削減し、環境価値向上のニーズに対応している。
詳しくはこちら
 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00755032
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00755032
●2025.7.15 読売新聞:東北5県でブナ「大凶作」予想、秋田県は市街地でのクマ出没に注意呼びかけ
東北森林管理局は、クマのエサとなるブナの今秋の結実予測について、2年ぶりに「大凶作」となる見込みだと発表した。秋田県は、秋以降に市街地でクマが出没する可能性が高まるとして注意を呼びかけている。
詳しくはこちら
 https://www.yomiuri.co.jp/national/20250715-OYT1T50052/
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250715-OYT1T50052/
●2025.7.15 ハウジングトリビュート:林野庁「林業白書」国際競争力を高め、木材・木製品の生産規模拡大
2020年まで横ばいで推移していた木材・木製品製造業の生産規模は、国際競争力の強化の動きが軌道に乗り20年を境に急角度で増加し始めている。輸入材や他資材との競争がある中、輸入材に対抗できる品質・性能の確かな製品を低コストで安定供給できる体制整備が進められており、主に国産材を原材料とする年間原木消費量10万立米以上の製材・合板等の工場が全国各地で増加してきている。
詳しくはこちら
 https://htonline.sohjusha.co.jp/707-012/
https://htonline.sohjusha.co.jp/707-012/
●2025.7.12 strainer:「木の価値」を再定義するスマート林業銘柄、国内企業の戦略を分析
脱炭素社会への移行が世界の潮流となる中、再生可能資源である木の価値が再評価されているが、国内の林業は長年、担い手不足や生産性の低さといった構造的な課題を抱えてきた。この状況を打破すべく、今「スマート林業」への期待が高まっており、こうした変革期にある市場で、独自の技術と戦略を武器に”木の価値”を未来へ繋ごうとする企業を紹介します。
詳しくはこちら
 https://strainer.jp/notes/8744
https://strainer.jp/notes/8744
●2025.7.11 日本経済新聞:レノバが静岡のバイオマス停止 ボイラー周辺に不具合、9月めど再開
再生可能エネルギー大手のレノバは11日、静岡県のバイオマス発電所の稼働を停止したと発表した。ボイラー周辺の設備で不具合が起きた。補修した上で、9月中をめどに再稼働する。
同発電所は過去にはボイラーやタービンの調整を理由に稼働延期を繰り返していた。
詳しくはこちら
 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1132W0R10C25A7000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1132W0R10C25A7000000/
●2025.7.10 新建ハウジング:国産木材活用の取組状況など報告 提言案も公表─全国知事会
47都道府県の知事で組織する全国知事会は7月17日、「第9回国産木材活用プロジェクトチーム会議」(リーダー:小池百合子東京都知事)を開催。2025年度の「国産木材の需要拡大に向けた提言(案)」について協議したほか、長野県など3県による取組事例の発表、国産木材活用に関するアンケート結果の公表を行った。
詳しくはこちら
 https://www.s-housing.jp/archives/390717
https://www.s-housing.jp/archives/390717
●2025.7.9 山陽新聞:バイオマス燃料となる木質チップ製造の作業棟を全焼、職員1人やけど 岡山・真庭森林組合の集積基地
8日午後2時50分ごろ、岡山県真庭市月田、真庭森林組合(完田二郎組合長)の月田集積基地内から出火、木造平屋の作業棟1棟(約230平方メートル)を全焼した。棟内で製造されたバイオマス燃料となる木質チップがくすぶり続け、約7時間後に鎮火した。
詳しくはこちら
 https://news.yahoo.co.jp/articles/b84e2875a37f34d5643818e6e1da9796660a5bdd
https://news.yahoo.co.jp/articles/b84e2875a37f34d5643818e6e1da9796660a5bdd
●2025.7.8 日本経済新聞:大阪ガス、千葉県袖ケ浦市でバイオマス発電所を稼働 火災で3年遅れ
大阪ガスは8日、千葉県袖ケ浦市でバイオマス発電所の商業運転を開始したと発表した。木材を燃料とし、最大出力は7万5000キロワット。設備の不具合や貯蔵していた燃料の発火事故などで、当初の予定より3年遅れでの稼働となった。
木質燃料を東南アジアから輸入する。
詳しくはこちら
 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF0874M0Y5A700C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF0874M0Y5A700C2000000/
●2025.7.2 新建ハウジング:改正建築基準法・建築物省エネ法改正法への対応に不安の声─全建総連が工務店アンケート
全国建設労働組合総連合(全建総連)は、物価・建材価格の高騰などが組合員にどう影響を与えているかを把握し、対策を要望するため、第5回目となる「住宅の建材・設備の価格高騰等の影響に関する工務店アンケート」を実施。改正建築基準法・建築物省エネ法改正法への対応については、「不安がある」と回答した工務店が52.7パーセントにのぼった。
詳しくはこちら
 https://www.s-housing.jp/archives/389496
https://www.s-housing.jp/archives/389496
●2025.6.30 山陽新聞:【詳報】岡山・真庭のバイオマス集積基地で火災 けが人なし、鎮火まで数日要する見込み
30日午前2時ごろ、岡山県真庭市上河内、真庭バイオマス集積基地第2工場の敷地内から出火。積まれていた樹皮9800立方メートルが燃えた。市消防本部によると、延焼の恐れはないとみられる。樹皮がくすぶり続けており、鎮火までは数日を要する見込み。発電所の稼働に大きな影響はないという。
詳しくはこちら
 https://news.yahoo.co.jp/articles/a5c8ae23d8ae1f65b5d390c5d3786f938cc833bb
https://news.yahoo.co.jp/articles/a5c8ae23d8ae1f65b5d390c5d3786f938cc833bb
【中国情報】
●2025.7.24 国家林草局産業発展計画院:今年上半期、全国の合板生産企業数は800社減、生産能力は12.2パーセント増
中国の合板業界は、企業数が減少する一方で、総生産能力は増加する傾向を示している。
国家林業草原局産業発展計画院の産業モニタリング調査によると、今年6月末までに、全国の合板製品生産企業は5,200社を超え、26の省(市・区)に分布する見込みである。これは2024年末より約800社の減少だが、総生産能力は約2.48億立方メートル/年となり、2024年末より12.2パーセントの増加である。
原文はこちら(中国語)
 https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=85312
https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=85312
●2025.7.18 中国木業信息網:ロシアの木材産業は大規模な生産停止の恐れ
『モスクワ・タイムズ』の報道によると、ロシアの木材業界は、西側の制裁と需要の低下、ルーブルの高騰がロシアの輸出競争力に打撃を与えたため、大規模な生産停止に直面すると警告した。
報道によると、ロシアの紙パルプ業界団体と企業協会は、デニス・マントゥロフ産業貿易相に宛てた書簡の中で、現在の状況は業界の現代史上最も困難な時期の一つだと述べた。業界データによると、2024年の木材伐採量は2021年と比べて13パーセント、木材生産量は11パーセント、合板生産量は23パーセント減少しており、業界で比較的安定して生産されているパルプ生産量も3パーセント減少している。
過去2年間、SegezhaグループやULKグループを含む主要な業界関係者は、生産量の減少、価格の下落、コストの高騰に対処するためにローンの再編を行ってきた。同時に、ルーブルの強化はロシアの輸出品の海外競争力を弱め、新しい世界貿易環境に適応することが困難な生産者の収入をさらに圧縮した。
さらに、20パーセントというロシア中央銀行の基準金利と20パーセントから25パーセントへの利益税率の引き上げは、経済全体を安定させるための措置だったが、意図せずメーカーに圧力をかけた。
業界は輸出難に加え、国内需要の弱さと中国の先行きの暗さというジレンマに直面している。業界幹部によると、米中の貿易緊張が続き、中国の建築業が長期低迷していることにより、購買活動が大幅に減少したという。Segezhaグループの代表は、「輸出の困難、建設業の課題、需要の減少、物流コストの上昇、業務効率の低下」というジレンマに直面していると語った。
業界のリーダーたちは書簡の中で、政府に対し、産業を監視し安定化策を策定するため、産業貿易省内に緊急行動センターを設置するよう求めた。
原文はこちら(中国語)
 http://www.wood168.net/src/newsdetail.asp?this=58365
http://www.wood168.net/src/newsdetail.asp?this=58365
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆第86回フェアウッド研究部会
「どうなった?改正クリーンウッド法 ~その効果、展望、そして課題~」
2025年8月20日(水)18:00~19:30@ハイブリッド
 https://fairwood.jp/event/250820
https://fairwood.jp/event/250820
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2017年に日本における違法伐採対策法として誕生したクリーンウッド法が、施行5年後見直しプロセスを経て改正され、2025年4月に施行されました。輸入材や国産原木を国内市場に最初に持ち込む第一種木材関連事業者の合法性確認、および彼らからの求めに応じた素材生産事業者の情報提供が義務化されるなど、規制強化による効果が期待されるところですが、一方で具体的な合法性確認の手続きや内容について、その実効性がどうなのか、気になるところです。
そこで、クリーンウッド法改正の具体的な議論やプロセスに参画・貢献された地球環境戦略研究機関(IGES)の鮫島弘光さんを講師にお招きし、改正法の効果や展望、そして課題についてお話いただきます。
また、フェアウッド・パートナーズが継続的に実施している第5回目となる登録第一種木材関連事業者を対象とした合法性確認の内容に関するアンケート調査結果も併せてご報告いたします。ぜひ、ご参加ください。
【開催概要】
日時:2025年8月20日(水)18:00~19:30(開場:会場は15分前、オンラインは5分前)
場所:ハイブリッド(zoom×地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)
東京都渋谷区神宮前 5-53-70 国連大学ビル 1F)
参加費:一般1,500円、学生無料(いずれも懇親会費別)
定員:会場25名、オンライン90名
※懇親会は会場参加者のみご参加いただけます。当日の受付の際にお申込み・お支払いを承ります。
※会議URL:お申込みいただいた方に後日ご案内いたします。
※お申込みいただいた方で希望のある場合は、当日の録画アーカイブを後日、期間限定でご覧いただくことが可能です。
【プログラム】(敬称略、内容は予告なく変更することがあります)
第1部:講演(18:00~19:30 質疑含む)
講師:鮫島 弘光/地球環境戦略研究機関(IGES)生物多様性と森林領域 研究員
※クリーンウッド法第一種登録事業者対象アンケート(第5回)の結果報告
坂本有希/フェアウッド・パートナーズ事務局(地球・人間環境フォーラム)
第2部:懇親会(会場参加者の希望者のみ、別会場にて開催予定)
■講師プロフィール(敬称略)
鮫島弘光(さめじま ひろみつ)/地球環境戦略研究機関(IGES)生物多様性と森林領域 研究員
京都大学大学院理学研究科博士課程修了(理学博士)。研究領域は生態学、持続可能な森林管理、東南アジア地域研究、REDD+、森林リスク産品の責任ある生産と貿易など。林野庁の「クリーンウッド」利用推進事業のうち、海外情報収集、国内定着実態調査、生産国リスク情報活用に向けた調査等に参与。『クリーンウッド法ハンドブック』(地球環境戦略研究機関. 2020)、「木材デューデリジェンス」(森林技術. 2024)、「書評:田中淳夫著『盗伐─林業現場からの警鐘─』」(林業経済. 2025)等を執筆。
■お申込み
お申し込みフォーム( https://fw250820.peatix.com)よりお申し込みください。
https://fw250820.peatix.com)よりお申し込みください。
フォームがご利用できない場合、「第86回フェアウッド研究部会参加希望」と件名に明記の上、1)お名前、2)ふりがな、3)ご所属(学生の場合は学校名など、組織名及び部署名等)、4)Eメールアドレス、5)参加方法(会場またはオンライン)、6)(会場参加の場合)懇親会の出欠を、メールにてinfo@fairwood.jp まで送付ください。
■主催
国際環境 NGO FoE Japan、地球・人間環境フォーラム、佐藤岳利事務所
■後援
マルホン
■助成
緑と水の森林ファンド
■お問合せ
地球・人間環境フォーラム(担当:坂本)
 http://www.fairwood.jp、info@fairwood.jp、TEL:03-5825-9735
http://www.fairwood.jp、info@fairwood.jp、TEL:03-5825-9735
FoE Japan(担当:佐々木)
 http://www.foejapan.org、info@foejapan.org、TEL:03-6909-5983
http://www.foejapan.org、info@foejapan.org、TEL:03-6909-5983
※テレワーク推進中のため、極力メールにてお問合せをお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆レポート「持続可能なバイオマスプログラム:持続不可能なものを認証する」を発行!
 https://www.gef.or.jp/news/info/250731sbpreport/
https://www.gef.or.jp/news/info/250731sbpreport/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地球・人間環境フォーラムは、海外の環境NGO、4団体の共同でレポート『持続可能なバイオマスプログラム:持続不可能なものを認証する』を発行しました。
日本語版レポートの公開は10月上旬を予定しています。
バイオマス発電は、経済産業省の「再生可能エネルギー固定価格買取」(FIT)制度で「カーボンニュートラルな再生可能エネルギー」とされ、消費者負担の再エネ賦課金を原資に支援されてきました。
製材の残材や間伐材を燃料とすると言われてきましたが、実際には約7割の発電所で、海外から輸入される木質ペレットやパーム核殻(PKS)を燃やしています。2024年の輸入量は、木質ペレット638万トンとPKS 600万トンに上っています。
当団体では過去にカナダ・ブリティッシュコロンビア州の現地視察を行い、ペレット生産と原生林等の貴重な森林の伐採と関係など、現地の問題をお伝えしてきました。
本レポートは、カナダのペレット工場のケーススタディも踏まえて、現地で広く用いられている「持続可能なバイオマスプログラム(SBP)」の問題点を解説するものです。
日本のFIT・FIP制度は燃料の持続可能性の証明を「認証」に過度に依存しており、SBPも既に証明方法として認められています。早急な見直しに向けて、本レポートは極めて重要な分析を提供しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆【プレスリリース】 “グリーンプラネットはグリーンウォッシュ” パーム油原料の海洋分解性バイオプラスチックー森を壊して海を守る?!
 https://jatan.org/archives/10919
https://jatan.org/archives/10919
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
フェアウッドの運営団体、地球・人間環境フォーラムと国際環境NGO FoE Japanを含む、7団体のネットワークであるプランテーション・ウォッチ(事務局団体 熱帯林行動ネットワーク:東京都渋谷区)は、6月18日に「グリーンプラネット」のユーザー企業17社を対象としたアンケート調査*1 (2023年~2024年)に基づく5つの問題点を発表しました。
今年1月にスターバックスが紙ストローをやめて採用したバイオプラスチック製のストローは、「飲み心地の良さと、環境負荷低減を両立」すると謳っています。原料は植物油などを原料とする株式会社カネカの海洋分解性バイオポリマー「グリーンプラネット」。カネカは「海洋マイクロプラスチック問題の解決をはじめ、地球環境保全に貢献していくことで世界を健康にしていく」と宣伝していますが、グリーンプラネットの原料は、熱帯林破壊の主要な要因となっているパーム油です。
植物由来であることでCO2排出量を削減するとされていますが、パーム油生産によって東南アジアでは膨大なCO2が排出され、生物多様性にも壊滅的な影響が生じています。グリーンプラネットの使用は、これらの環境課題を覆い隠すグリーンウォッシュ(隠れたトレードオフ)にあたります。
詳しくは以下をご覧ください。
 https://jatan.org/archives/10919
https://jatan.org/archives/10919
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆フェアウッド・マガジン 世界のニュース登録方法を追加しました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
フェアウッド・パートナーズが、毎月、無料で配信している「フェアウッド・マガジン 世界のニュース」の登録・削除方法を追加しました。
これまでは、外部のメールマガジン配信サービス「まぐまぐ」のみとなっていましたが、フェアウッド・パートナーズからのダイレクト配信システムを加えました。いずれも無料ですので、以下からお好みの方法で登録してください。
 https://fairwood.jp/mailmagagine/16/
https://fairwood.jp/mailmagagine/16/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・みなさんの知人、友人、ご家族の方にもこのメールマガジンをお知らせしてください。メールマガジンの登録、バックナンバーはこちらです。
 https://fairwood.jp/worldnews/
https://fairwood.jp/worldnews/
・本メールマガジンの記事について、無断転載はご遠慮ください。
ただし、転載許可の表記のある場合を除きます。
・本メールマガジンに関するご意見・ご感想などは下記のEmailにお寄せください。お待ちしております。
e-mail: info@fairwood.jp
発 行 : フェアウッド・パートナーズ  http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp
編 集 : 坂本 有希/三柴 淳一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです
◎フェアウッド・マガジン-世界のニュース
の配信停止(unsubscribe)はこちら
⇒  https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=147706&e=sagaragef%40gmail.com&l=scj1851435
https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=147706&e=sagaragef%40gmail.com&l=scj1851435
![]() http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/shor
https://news.mongabay.com/shor![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://www.tokyo-np.co.jp/art
https://www.tokyo-np.co.jp/art![]() https://www.nikkei.com/article
https://www.nikkei.com/article![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://news.mongabay.com/shor
https://news.mongabay.com/shor![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://www.nikkan.co.jp/artic
https://www.nikkan.co.jp/artic![]() https://www.yomiuri.co.jp/nati
https://www.yomiuri.co.jp/nati![]() https://htonline.sohjusha.co.j
https://htonline.sohjusha.co.j![]() https://strainer.jp/notes/8744
https://strainer.jp/notes/8744![]() https://www.nikkei.com/article
https://www.nikkei.com/article![]() https://www.s-housing.jp/archi
https://www.s-housing.jp/archi![]() https://news.yahoo.co.jp/artic
https://news.yahoo.co.jp/artic![]() https://www.nikkei.com/article
https://www.nikkei.com/article![]() https://www.s-housing.jp/archi
https://www.s-housing.jp/archi![]() https://news.yahoo.co.jp/artic
https://news.yahoo.co.jp/artic![]() https://www.chinatimber.org/ne
https://www.chinatimber.org/ne![]() http://www.wood168.net/src/new
http://www.wood168.net/src/new![]() https://fairwood.jp/event/2508
https://fairwood.jp/event/2508![]() https://fw250820.pea
https://fw250820.pea![]() http://www.fairwood.jp、info@fa
http://www.fairwood.jp、info@fa![]() http://www.foejapan.org、info@f
http://www.foejapan.org、info@f![]() https://www.gef.or.jp/news/in
https://www.gef.or.jp/news/in![]() https://jatan.org/archives/109
https://jatan.org/archives/109![]() https://jatan.org/archives/109
https://jatan.org/archives/109![]() https://fairwood.jp/mailmagagi
https://fairwood.jp/mailmagagi![]() https://fairwood.jp/worldnews/
https://fairwood.jp/worldnews/![]() http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp![]() https://regist.mag2.com/reader
https://regist.mag2.com/reader