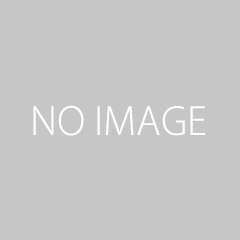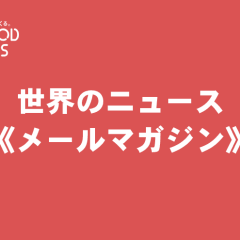--- フェアな木材を使おう ---  http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年も異常な暑さが続く夏でしたが、世界的にも想定外の高温や不安定な気候に見舞われる国々が多く、森林火災などの自然災害が頻発しています。他方、熱帯地域等の森林開発の現場では、森林減少につながる伐採や農地転換が後を絶ちません。異常気象と関連づけて森林減少を考える必要があります。
定期開催しているフェアウッド研究部会は、9月中の開催が調整できず、10月1日の開催となりました。また、10月15日にも開催いたしますので、10月は2回の開催となります。
10月1日は、持続可能な森林管理や川下での木材利用にとっても重要となっている野生生物保護管理の現状についてのご講演、10月15日は、再造林と木材のトレーサビリティを重要視した三菱地所レジデンスと自治体との協定についての最新動向についてのご講演となります。是非、参加をご検討下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【森林減少】
●2025.8.21 Mongabay:インドネシアの遊休地問題
インドネシアは、熱帯林破壊の世界的潮流に逆行している。2024年には、多くの熱帯地域で森林消失率が過去最高を記録したのに対し、インドネシアの森林消失率は前年比で14%減少した。
しかし、一見成功しているように見えるこの結果の背後には、不都合な真実が隠されている。モンガベイのハンス・ニコラス・ジョン氏の報告によれば、記録された森林消失のほぼ半分については、明確な原因を特定できないという。
森林変化を監視する技術コンサルタント会社TheTreeMapによると、2024年に失われた原生林の要因は、伐採が18%、産業用パーム油が13%、パルプ材プランテーションが6%、鉱業が5%、農園開発プロジェクトが3%、火災が2%強を占めている。これらを合計しても、全体の半分には満たない。残りの森林は皆伐されたものの、しばしば何年も利用されないまま「影の森林」と呼ばれる状態に分類されている。
なぜこのような状況が生じるのだろうか。米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載された研究によれば、インドネシアでは森林伐採された土地のほぼ半分が、農地への転用に至る前に少なくとも5年間放置されていることが明らかになった。スマトラ島のリアウ州とベンクル州では、択伐許可区域内の自然林が伐り払われた後、放置され、数年後にアブラヤシ投資家が進出する例が見られる。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/short-article/2025/08/indonesias-idle-land-problem/
https://news.mongabay.com/short-article/2025/08/indonesias-idle-land-problem/
●2025.8.19 Earthsight:不幸なキャンパーたち:アメリカのRV業界がインドネシアの熱帯雨林を破壊している
RV(レクリエーショナル・ビークル)は、アメリカにおいて巨大な市場を形成している。現在、1,100万世帯以上がRVを所有しており、その数はかつてないほどに増加している。
しかし、業界が「自然への回帰」や「持続可能なライフスタイル」を掲げている一方で、Earthsightとインドネシアのパートナー団体Auriga Nusantaraによる新たな調査は、アメリカで人気のRVの一部が、地球の反対側にある手つかずの熱帯雨林を破壊して製造されていることを明らかにした。
軽量で耐水性に優れたラワン合板(メランティとも呼ばれる熱帯広葉樹の一種)が、RVの壁、床、天井に使用されている。一般的なRVでは、最大700平方フィート(約64平方メートル)の合板が使われることもある。
EarthsightとAurigaは、1年以上前からこの調査を進めてきた。調査の過程で、インドネシア有数の伐採業者であるボルネオ島西カリマンタン州のPTマヤワナ・ペルサダ社に行き着き、さらにその木材がカリフォルニアの合板輸入業者に流れていることを突き止めた。そして、この会社にとってラワン材の主要な市場の一つがRV業界であることが判明した。
さらに調査を進めると、このサプライチェーンは氷山の一角に過ぎないことも明らかになった。自然を愛するアメリカ人によって無意識のうちに支えられてきたRV業界の急成長の結果、米国はインドネシア産熱帯木材の世界最大の消費国となっていることが分かっている。
原文はこちら(英語)
 https://www.earthsight.org.uk/news/unhappy-campers
https://www.earthsight.org.uk/news/unhappy-campers
●2025.8.7 NHK:フランス南部で大規模な山火事 仏首相“かつてない規模”
フランス南部で大規模な山火事が発生し、これまでに1人が死亡し、3人と連絡がとれなくなっているということです。フランスのバイル首相は「かつてない規模の災害だ」としたうえで、気候変動による干ばつが影響しているという見方を示しました。
地元当局などによりますと、フランス南部のオード県で5日、山火事が発生し、6日の夕方までに1万6000ヘクタール以上が燃えたということです。
およそ500台の消防車両が出て消火活動を行いましたがその後も火は燃え広がっているということで、これまでに1人が死亡し、3人と連絡がとれなくなっているということです。
ロイター通信が配信した火災現場の映像では、煙が山を覆い尽くす中、上空の航空機から水をかけている様子が確認できます。
6日、現場を視察したフランスのバイル首相は「この災害はかつてない規模のものだ」と述べたうえで、気候変動による干ばつが影響しているという見方を示しました。
詳しくはこちら
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250807/k10014887051000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250807/k10014887051000.html
●2025.8.13 Reuters:欧州で新たな熱波、一部で気温44度 森林火災で死者も
欧州の一部で新たな熱波が発生し、気温が40度を超えている。スペイン、ポルトガル、ギリシャ、トルコ、バルカン半島では森林火災が相次ぎ、消防士らが12日、消火活動に当たった。
科学者は地球温暖化の影響で地中海地域の夏がより暑く乾燥していると指摘。森林火災が年々増加し、「火災旋風」が発生する例もあるという。
ポルトガルのあつ市長は、3件の火災が発生した事態について、「われわれは生きたまま焼かれている。こんなことは続けられない」と訴えた。
スペインのマドリード近郊では馬小屋で作業していた男性が火災に巻き込まれて死亡。カタルーニャ自治州では果実を収穫していたハンガリー出身の季節労働者(61)が熱関連死したとみられている。アルバニアでも火災で男性が死亡した。
イベリア半島最南端のタリファではユーカリ・松林で発生したとみられる火災が拡大し、2000人以上が避難した。
詳しくはこちら
 https://news.yahoo.co.jp/articles/c8416905264b0b7e4880376586edd10c0fe93a47
https://news.yahoo.co.jp/articles/c8416905264b0b7e4880376586edd10c0fe93a47
●2025.8.19 NewsweekJapan:「秋まで燃え続ける可能性」カナダ森林火災、乾燥と高温で拡大
カナダ連邦政府当局者らは18日、今年は観測史上2番目に深刻な森林火災シーズンとなっており、すでに780万ヘクタールが焼失し、今後も数週間続く可能性があると明らかにした。
非常に乾燥した状態が続いている西部のブリティッシュコロンビア州南部とアルバータ州、中部サスカチュワン州では9月末まで平年以上の高温が予想されており、新たな火災が発生するリスクが高いという。
天然資源省の担当者は、平年より高温になると予想されるため、現在発生している火災が秋まで燃え続けるか、くすぶり続ける可能性が高いと述べた。
詳しくはこちら
 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2025/08/565919.php#goog_rewarded
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2025/08/565919.php#goog_rewarded
【バイオマス】
●2025.8.21 Mongabay:持続可能なバイオマス認証制度に欠陥、森林劣化を招いているとレポートで指摘
持続可能なバイオマスプログラム(SBP)は、世界有数のバイオマス認証制度であり、エンドユーザ、とりわけEUやアジア諸国に対し、バイオマス(特にエネルギー用木質ペレット)が「合法かつ持続可能な方法で調達されている」ことを保証している。
しかし、環境NGOグループによる最近の報告書は、SBPが森林破壊につながるバイオマス燃料プロジェクトを承認していると批判している。
カナダを拠点とする森林認証・ガバナンスの専門家リチャード・ロバートソン氏が2025年7月に執筆した報告書によれば、SBP認証を受けたバイオマスは最低限の法的要件を満たしているものの、真の持続可能性には達していないケースが多いという。この分析は、ソリューションズ・フォー・アワー・クライメート(SFOC)、地球・人間環境フォーラム(GEF)、マイティ・アース、バイオフューエルウォッチ、環境ペーパーネットワーク(EPN)の5つの非営利団体によって委託されたものである。
急成長を遂げているバイオマスエネルギー産業は、木質ペレットや木質チップを気候変動対策の有力な解決策として宣伝している。だが報告書では、この主張は「バイオマス由来の排出をゼロとみなす」という誤った炭素会計の抜け穴に依拠していると指摘する。実際、多くの研究において、バイオマス燃焼の炭素集約度はエネルギー生産量当たりで石炭よりも高いことが示されている。
原文はこちら(英語)
 https://news.mongabay.com/2025/08/sustainable-biomass-certification-scheme-is-flawed-degrades-forests-report-finds/
https://news.mongabay.com/2025/08/sustainable-biomass-certification-scheme-is-flawed-degrades-forests-report-finds/
●2025.8.21 日本経済新聞:神戸製鋼、木質燃料100万トン生産へ UBE三菱セメントと共同で
神戸製鋼所はUBE三菱セメント(東京・千代田)と木質燃料「ブラックペレット」の生産に乗り出す。共同出資会社を2025年度中に立ち上げ、30年以降に年産100万トンの体制を構築する。石炭の代替燃料として発電所などに販売するほか、自社の製鉄所などでも活用する。木材調達先の東南アジアに製造拠点を設けることも視野に入れ供給網を整える。
詳しくはこちら(要登録)
 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0571N0V00C25A8000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0571N0V00C25A8000000/
●2025.8.29 alterna:「バイオマス燃料はカーボンニュートラルではない」世界最大のESG投資家ネットワークのPRIが警鐘
バイオ燃料はライフサイクル全体で見ればカーボンニュートラルとは言えないーー。国連が支援する世界最大のESG投資家ネットワーク・責任投資原則(PRI)は、昨年12月に発表した報告書で、森林資源などの生態系を、燃料としてしか捉えない視点に警鐘を鳴らす。今後、求められるのは、バイオマスを生きたまま活かす方向性であり、過度なバイオマス燃料への依存は、企業のレピュテーションリスクや資本コスト上昇リスクにもつながりかねない。
バイオ燃料というと、誰しも「カーボンニュートラル」で、再生可能な自然エネルギーだと考えるでしょう。木を燃やしても、また木が育てば同じ量の炭素を吸収するので、大気中のカーボンは差し引きゼロ、そんな説明が一般的です。しかし、話はそう単純ではありません。
2024年12月に公開されたPRI(責任投資原則)のポリシーレポート『欧州連合(EU)のバイオエネルギー政策と投資が気候と自然にもたらすリスクへの対応』を読むと、そのことがよくわかります。
たとえば、バイオ燃料はライフサイクル全体で見れば、決してカーボンニュートラルとは言えません。伐採から輸送、燃焼に至るまでの過程を含めて考えると、むしろ化石燃料より多くのCO2を排出してしまうことすらあるのです。
詳しくはこちら
 https://news.yahoo.co.jp/articles/28810b4c86d1d0231770478659d2c49101058e74
https://news.yahoo.co.jp/articles/28810b4c86d1d0231770478659d2c49101058e74
【日本は今!】
●2025.8.6 日本経済新聞:住友林業、インドネシアで複合都市開発 現地企業と戸建てなど4100戸
住友林業は6日、インドネシアで住宅や商業施設などの複合都市開発を始めると発表した。現地の不動産開発大手シナルマス・ランドと共同で、戸建て分譲住宅など約4100戸を開発する。総事業費は約1370億円。住友林業のインドネシアの不動産開発では最大規模になる。
ジャカルタ近郊のボゴール県に、戸建て分譲住宅約3800戸と、店舗併用住宅約300戸を建築・販売する。このほか約110区画の商業用地に商業施設やスポーツクラブ、学校などを誘致する。2025年にも戸建ての販売を始め、41年までの完売を目指す。
詳しくはこちら
 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0697Z0W5A800C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0697Z0W5A800C2000000/
●2025.8.12 日本経済新聞:住友林業、米国に製材拠点 関税・木材高で自前サプライチェーン
住友林業は米南部ルイジアナ州に製材工場を持つティール・ジョーンズ・ルイジアナ・ホールディングス(TJLH)を子会社化した。取得額は約43億円。米関税政策や世界的な木材相場の高騰「ウッドショック」など外的要因に影響されにくい木材サプライチェーンの構築を目指す。
TJLH社はルイジアナ州に約100ヘクタールの土地と工場を保有する。8月から住宅に使用する米国産材による構造用製材(ディメンション材)などを商業生産する。一般的な米国住宅約1万4000戸分に相当する年50万立方メートル程度の製造を見込む。
住友林業はルイジアナ州と隣接するテキサス州で米国戸建ての4割を供給する。製材販売エリアの周辺には屋根の部材など、住宅のトラスやパネルの設計や製造するFITP事業の工場が複数ある。分譲戸建てと不動産開発の2事業に向けて製材を供給する。
詳しくはこちら
 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC103QR0Q5A710C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC103QR0Q5A710C2000000/
●2025.8.26 遊都総研:三菱地所レジデンス・大館市・北鹿地域林業成長産業化協議会の3者、「大館市産森林認証材等の利用拡大に関する建築物木材利用促進協定」を締結 秋田県大館市
三菱地所レジデンス株式会社(東京都千代田区、中島篤社長)・大館市(石田健佑市長)・北鹿地域林業成長産業化協議会(秋田県大館市、石田健佑会長)の3者は2025年8月25日、「大館市産森林認証材等の利用拡大に関する建築物木材利用促進協定」を締結した。
三菱地所グループは、木材活用を通じた環境負荷の低減に取り組んでおり、その中で三菱地所レジデンスは、「森林循環(再造林)が約束され、トレーサビリティが確保された木材」の利用を通じ、環境配慮と地域貢献に寄与する木材活用を推進している。
今回の同協定締結により、同市の地域資源である秋田スギをはじめとした森林認証材や木材加工品の建築物への利用を促進し、持続可能な森林経営と地域経済の活性化を支援するという。
詳しくはこちら
 https://yutosoken.com/wp/2025/08/26/mec-321/
https://yutosoken.com/wp/2025/08/26/mec-321/
●2025.9.2 日本経済新聞:森未来、伐採木の再利用を促進 マンション向け加工サービス
木材情報のプラットフォームを運営する森未来(東京・港)は2日、伐採されこれまで廃棄されてきた街路樹や伐採木を資源として再活用する新サービスを始めると発表した。伐採された木を保管し、乾燥させてから、テーブルやイスなど顧客が希望する製品に加工して引き渡す。
森未来によれば、民間事業者からの引き合いが強く、マンション開発を手掛ける大手デベロッパーからすでに依頼されている。地主や地域住民の希望によって、マンション用地にあった樹木をなんらかの形で再利用したいというニーズが増えている。
詳しくはこちら
 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC022RR0S5A900C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC022RR0S5A900C2000000/
●2025.9.2 新潟日報:植林・造林から伐採まで事業一元化 村上市内の林業関連企業などでつくる一般社団法人が活動開始
伐採されずに放置される森林の整備につなげようと、村上市などの林業関係企業3社でつくる一般社団法人が村上市で本格的な活動をスタートさせた。法人と山林所有者が契約を結び、法人会員企業が伐採、材木の買い取り、その後の造林を担う。造林の原資は行政の補助金などを充て、山林所有者は費用負担がない。伐採から造林までのサイクルづくりを促す。
活動を本格化させたのは一般社団法人「新潟・山のバトン」。植林・造林を専門とする青葉組(東京)と丸実(村上市)、中嶋木材(同)の3社で構成する。青葉組は2022年、村上市に事業拠点を設置している。
詳しくはこちら
 https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/680417
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/680417
【中国情報】
●2025.8.18 木頭雲:ロシア木材取引所の累計取引量が230万立方メートルに
ロシア政府は、西側市場におけるロシア産木材のジレンマを緩和するため、免税、承認手続きの簡素化、輸送補助金など、一連の輸出促進政策を導入した。さらに、ロシア木材取引所はより広範な輸出チャンネルを開拓した。
ロシア連邦森林局(Rosleskhoz)の広報室が発表した情報によると、ロシア木材取引所は2025年上半期に好調な取引実績を記録し、累計取引量は230万立方メートルに達し、同期間の取引所を通じた木材販売総量の98.7%を占めた。
報告期間中、取引所は5,500件の取引を成立させ、総取引量は46億ルーブルに達した。木材の平均取引価格は1立方メートルあたり2,000ルーブルで安定していた。
地域別では、クラスノヤルスク地方、ヴォログダ州、トヴェリ州、スヴェルドロフスク州、ウドムルト共和国が取引所における木材販売で特に好調で、これら5地域の取引量は、取引所における木材販売総量の約70%を占めた。
原文はこちら(中国語)
 https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=85442
https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=85442
●2025.8.7 木材網:ベトナムの林業セクターは、輸出市場の拡大に向けた取り組みを強化
木材産業はベトナムで最も輸出額の多い農業セクターの一つであり、輸出の伸びと経済発展に大きく貢献している。しかし、関税、原材料の合法性、主要輸出市場における購買力の低下などが企業にとって新たな課題となっており、企業は生き残りと持続可能な発展のために事業再編と競争力強化を迫られている。
現在、ベトナム全土で5,000社以上の木材・木材製品加工企業があり、その95%は民間企業である。これらの企業の約3.5%は、500億ベトナムドンを超える投資額を有している。約2,000社の企業が輸出用木材製品を生産しており、国内企業が市場シェアの65%を占めている。
市場の圧力:
ベトナム木材林産物協会(VIFOREST)によると、主要市場における木材および木材製品の輸出は引き続き着実に増加している。米国市場への輸出は前年同期を上回り、日本、中国、韓国への木材チップおよび木質ペレットの輸出も堅調な伸びを維持した。主に屋内・屋外用木製家具を中心とするEU市場も、若干の伸びを記録した。
しかし、ベトナムの木材輸出業者は2つの大きな課題に直面している。第一に、ベトナムの木材輸出全体の54~56%以上を占める米国市場は、8月1日にホワイトハウスが発表した20%の報復関税の影響を受けた。
EU市場において、ベトナム企業は屋内・屋外用家具と木質ペレット部門に大きく貢献しており、年間輸出額は10億米ドルを超えている。EUは最近、コーヒー、ゴム、大豆、木材、パーム油など、世界的な森林破壊につながる農産物の輸入を禁止する「欧州森林破壊防止規則(EUDR)」を制定した。
これらの課題に直面しながら、ベトナム企業は持続可能なサプライチェーンの構築、森林破壊の回避、国際基準の遵守という厳格なコミットメントを着実に果たしている。日本、中国、韓国といった他の主要輸出市場も、木材原産地の検証、環境保護要件、グリーン生産基準の遵守、温室効果ガス排出削減といった課題に直面している。
輸出市場からの圧力は、企業にとって成長モデルを見直し、適応力を高め、外部市場の変動に効果的に対応する機会にもなる。VIFORESTの呉世懐副会長は、2025年以降の世界経済の変動と地政学的紛争が相まって、輸送コスト、木材価格、貿易規制に影響を与え、ひいては輸出活動にも影響を及ぼすだろうと述べている。しかし、輸出市場からのこうした圧力は、企業にとって成長モデルを見直し、適応力を高め、外部市場の変動に効果的に対応する機会も提供すると指摘した。
成長はもはや安価な原材料や低労働コストといった比較優位に頼るのではなく、品質とブランドに基づく競争へと移行する必要があると強調した。さらに、企業は輸出市場を拡大・再構築し、事業展開の多様化を図る必要がある。
中国、日本、そして英国、ロシア、中東、南米、ASEANといった多くの潜在市場は、未開発のままである。こうした新興市場は、企業にとって持続可能な輸出競争力を開発・強化するための大きな機会を提供している。
原文はこちら(中国語)
 https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=85390
https://www.chinatimber.org/news/detail.html?id=85390
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆第87回フェアウッド研究部会
「鹿と人間、揺れ動く関係史、ニホンジカ問題の背景と対応方向」
2025年10月1日(水)18:00~19:30@ハイブリッド
 https://fairwood.jp/event/251001
https://fairwood.jp/event/251001
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ニホンジカはかつて人々の貴重な資源でしたが、江戸後期以降、農地開発が進むにつれて害獣と見なされるようになりました。明治以降は乱獲や生息地減少により個体数が激減し、保護政策が取られるようになります。しかし、戦後の大規模伐採や造林、そして近年の温暖化や少雪化といった環境変化により、生息環境が改善し、個体数が急増しました。
加えて、集中高密度化しやすく繁殖力が高い、幅広い植物を多く採食する等の生態的特性、そして保護から管理への政策転換の遅れが重なり、農林業被害や生物多様性への影響を深刻化させてきました。また、捕獲を担う狩猟者の減少と高齢化も、この問題の解決をさらに難しくしています。
昨今の人工林の伐採・再造林の活発化は、アクセスの悪い山地で本種をさらに増やし、被害を加速していく可能性が大きいです。このため、林業活動と連携した効果的な捕獲体制の構築などが喫緊の課題と考えられます。
今回の研究部会では、森林資源の持続可能な利用を考える上でも重要となっている、野生生物保護管理の歴史と現状について、長年、丹沢山地においてニホンジカの問題に従事された山根正伸さんをお招きしてご講演いただきます。
【開催概要】
日時:2025年10月1日(水)18:00~19:30(開場:会場は15分前、オンラインは5分前)
場所:ハイブリッド(zoom×地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)
東京都渋谷区神宮前 5-53-70 国連大学ビル 1F)
参加費:一般1,500円、学生無料(いずれも懇親会費別)
定員:会場25名、オンライン90名
※懇親会は会場参加者のみご参加いただけます。当日の受付の際にお申込み・お支払いを承ります。
※会議URL:お申込みいただいた方に後日ご案内いたします。
※お申込みいただいた方で希望のある場合は、当日の録画アーカイブを後日、期間限定でご覧いただくことが可能です。
【プログラム】(敬称略、内容は予告なく変更することがあります)
第1部:講演(18:00~19:30 質疑含む)
講師:山根正伸/一般社団法人自然環境管理サポートセンター理事
第2部:懇親会(会場参加者の希望者のみ、別会場にて開催予定)
■講師プロフィール(敬称略)
山根正伸(やまね まさのぶ)/1958年、大阪生まれ。一般社団法人自然環境管理サポートセンター理事。農学博士。元神奈川県自然環境保全センター研究企画部長。丹沢山地でニホンジカの栄養生態や保護管理、自然再生の調査研究に取り組んできた。また、「地球環境戦略研究機関」派遣を契機に中ロ木材貿易など北東アジア森林保全研究も行ってきた。
主な著書は「森林と野生動物」(分担執筆・共立出版)、「丹沢の自然再生」(分担執筆・日本林業調査会)、「ロシア森林大国の内実」(編著・日本林業調査会)、「モノの越境と地球環境問題 : グローバル化時代の「知産知消」」(分担執筆・昭和堂)など
■お申込み
お申し込みフォーム( https://fw251001.peatix.com)よりお申し込みください。
https://fw251001.peatix.com)よりお申し込みください。
フォームがご利用できない場合、「第87回フェアウッド研究部会参加希望」と件名に明記の上、1)お名前、2)ふりがな、3)ご所属(学生の場合は学校名など、組織名及び部署名等)、4)Eメールアドレス、5)参加方法(会場またはオンライン)、6)(会場参加の場合)懇親会の出欠を、メールにてinfo@fairwood.jp まで送付ください。
■主催
国際環境 NGO FoE Japan、地球・人間環境フォーラム、佐藤岳利事務所
■共同企画・実施
一般社団法人自然環境管理サポートセンター
■後援
マルホン
■助成
緑と水の森林ファンド
■お問合せ
地球・人間環境フォーラム(担当:坂本)
 http://www.fairwood.jp、info@fairwood.jp、TEL:03-5825-9735
http://www.fairwood.jp、info@fairwood.jp、TEL:03-5825-9735
FoE Japan(担当:佐々木)
 http://www.foejapan.org、info@foejapan.org、TEL:03-6909-5983
http://www.foejapan.org、info@foejapan.org、TEL:03-6909-5983
※テレワーク推進中のため、極力メールにてお問合せをお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆第88回フェアウッド研究部会「認証材が取り持つビジネスマッチング
~大館市・北鹿地域林業成長産業化協議会と三菱地所レジデンスが木材利用促進協定を締結した訳~」
2025年10月15日(水)18:00~19:30@ハイブリッド
 https://fairwood.jp/event/251015
https://fairwood.jp/event/251015
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2021年に創設された「建築物木材利用促進協定制度」。全国で多くの事例が生まれる中、今年8月25日に締結された大館市・北鹿林成協と三菱地所レジデンスによる協定は、少し異なる“縁”から始まりました。そのきっかけとなったのは、「認証材」。木材の品質と信頼性が、川上(林業)と川下(マンション開発)を結びつけたのです。
本セミナーでは、大館市林政課 加賀谷洋昌氏と三菱地所レジデンス 石川博明氏のお二人を講師にお迎えし、行政・林産地域の理念と期待、そして木材を使用する側の希望と背景をそれぞれの視点から語っていただきます。
「なぜこの連携が実現したのか?」「認証材が果たした役割とは?」「地域材利用の未来に何が期待されているのか?」「川上と川下がどう結びついたのか?」、そのプロセスと想いを深掘りする貴重な機会です。木材利用の新たな可能性を探るこのセミナー、ぜひお聞き逃しなく!
【開催概要】
日時:2025年10月15日(水)18:00~19:30(開場:会場は15分前、オンラインは5分前)
場所:ハイブリッド(zoom×地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)
東京都渋谷区神宮前 5-53-70 国連大学ビル 1F)
参加費:一般1,500円、学生無料(いずれも懇親会費別)
定員:会場25名、オンライン90名
※懇親会は会場参加者のみご参加いただけます。当日の受付の際にお申込み・お支払いを承ります。
※会議URL:お申込みいただいた方に後日ご案内いたします。
※お申込みいただいた方で希望のある場合は、当日の録画アーカイブを後日、期間限定でご覧いただくことが可能です。
【プログラム】(敬称略、内容は予告なく変更することがあります)
第1部:講演(18:00~19:30 質疑含む)
講師:石川 博明/三菱地所レジデンス(株)経営企画部サステナビリティ推進グループ専任部長
加賀谷 洋昌/大館市産業部森林整備課林政課木材産業係主任
第2部:懇親会(会場参加者の希望者のみ、別会場にて開催予定)
【講師プロフィール】(敬称略)
石川 博明(いしかわ・ひろあき)/三菱地所レジデンス(株)経営企画部サステナビリティ推進グループ専任部長
広島県出身。1985年藤和不動産(株)入社、設備・電気技術者としてマンションの品質管理などに従事、2011年会社統合により三菱地所レジデンス(株)が誕生、分譲・賃貸マンションのモノづくりや企業のサステナビリティ推進を行う。現在は持続可能な木材活用とは何か?を日々研究中であり、日本の山がはげ山にならない木材活用をするための仲間集めに奔走中。
加賀谷 洋昌(かがや・ひろあき)/大館市産業部林政課木材産業係主任
秋田県出身。2014年大館市役所に入庁、福祉部子ども課で補助金や給付費業務に従事。2017年に全く畑違いである秋田県庁産業労働部に出向、東京事務所配属となり、企業誘致業務を担う。大館市に戻って以降、企業誘致・折衝、市有林整備・整備計画策定など産業畑を中心とした業務に従事し、現在は森林認証林整備と流通調整を行いながら、森林(もり)と消費者との心理的距離を近いものとするため、地元林業事業体や木材加工事業者と共に各所との関係性構築を進めている。
■お申込み
お申し込みフォーム(本サイト)よりお申し込みください。
フォームがご利用できない場合、「第88回フェアウッド研究部会参加希望」と件名に明記の上、1)お名前、2)ふりがな、3)ご所属(学生の場合は学校名など、組織名及び部署名等)、4)Eメールアドレス、5)参加方法(会場またはオンライン)、6)(会場参加の場合)懇親会の出欠を、メールにてinfo@fairwood.jp まで送付ください。
■主催
国際環境 NGO FoE Japan、地球・人間環境フォーラム、佐藤岳利事務所
■後援
マルホン
■助成
緑と水の森林ファンド
■お問合せ
FoE Japan(担当:佐々木)
 http://www.foejapan.org、info@foejapan.org、TEL:03-6909-5983
http://www.foejapan.org、info@foejapan.org、TEL:03-6909-5983
地球・人間環境フォーラム(担当:坂本)
 http://www.fairwood.jp、info@fairwood.jp
http://www.fairwood.jp、info@fairwood.jp
※テレワーク推進中のため、極力メールにてお問合せをお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆ウェブサイト『バイオマス発電info』を公開しました!
 https://bioenergyinfo.jp/
https://bioenergyinfo.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地球・人間環境フォーラム(以下GEF)は、日本の再生可能エネルギー固定価格買取(FIT)制度が支援する「輸入木質バイオマス発電」の課題について理解を促すための最新動向やデータを提供するウェブサイト『バイオマス発電info』( https://bioenergyinfo.jp/)を公開しました。
https://bioenergyinfo.jp/)を公開しました。
「バイオマス発電info」は、主にメディア関係者と再エネに関心を寄せる事業者や金融機関を対象に、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)で支援されている輸入木質バイオマスが、再エネとして「持続可能」なのかを検証できる情報を提供しています。
“カーボンニュートラル”で“地産地消”とされる木質バイオマス発電の気候変動対策としての有効性や燃料生産地における環境・社会への悪影響などをわかりやすく解説し、「輸入木質バイオマス発電」をFIT制度で支援することが本当に「持続可能」と言えるのか、考えるサイトです。
主なコンテンツ
問題を知る:気候変動/生産地/FITという3つの軸から、輸入木質バイオマス発電の課題についてデータを交えて解説しています
木質バイオマス発電のCO2排出量やエネルギー効率を解説、気候変動対策として有効性を検証
日本のバイオマス発電の燃料の生産地であるベトナムやカナダなどで起きている環境・社会への影響を解説
再エネ普及による環境負荷の低減や地域活性化というFIT制度のねらいが実現されているのか、同制度におけるバイオマス発電が抱える課題を解説
最新トピックス/最新の活動内容:より詳しい解説や、国内外のバイオマス関連最新ニュース、セミナー・イベント情報などを更新していきます
データベース:より深いリサーチに使えるような参考資料を「よくある質問」「キーワード集」としてまとめています.
ぜひご覧ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆レポート「持続可能なバイオマスプログラム:持続不可能なものを認証する」を発行!
 https://www.gef.or.jp/news/info/250731sbpreport/
https://www.gef.or.jp/news/info/250731sbpreport/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地球・人間環境フォーラムは、海外の環境NGO、4団体の共同でレポート『持続可能なバイオマスプログラム:持続不可能なものを認証する』を発行しました。
日本語版レポートの公開は10月上旬を予定しています。
バイオマス発電は、経済産業省の「再生可能エネルギー固定価格買取」(FIT)制度で「カーボンニュートラルな再生可能エネルギー」とされ、消費者負担の再エネ賦課金を原資に支援されてきました。
製材の残材や間伐材を燃料とすると言われてきましたが、実際には約7割の発電所で、海外から輸入される木質ペレットやパーム核殻(PKS)を燃やしています。2024年の輸入量は、木質ペレット638万トンとPKS 600万トンに上っています。
当団体では過去にカナダ・ブリティッシュコロンビア州の現地視察を行い、ペレット生産と原生林等の貴重な森林の伐採と関係など、現地の問題をお伝えしてきました。
本レポートは、カナダのペレット工場のケーススタディも踏まえて、現地で広く用いられている「持続可能なバイオマスプログラム(SBP)」の問題点を解説するものです。
日本のFIT・FIP制度は燃料の持続可能性の証明を「認証」に過度に依存しており、SBPも既に証明方法として認められています。早急な見直しに向けて、本レポートは極めて重要な分析を提供しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆【プレスリリース】 “グリーンプラネットはグリーンウォッシュ” パーム油原料の海洋分解性バイオプラスチックー森を壊して海を守る?!
 https://jatan.org/archives/10919
https://jatan.org/archives/10919
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
フェアウッドの運営団体、地球・人間環境フォーラムと国際環境NGO FoE Japanを含む、7団体のネットワークであるプランテーション・ウォッチ(事務局団体 熱帯林行動ネットワーク:東京都渋谷区)は、6月18日に「グリーンプラネット」のユーザー企業17社を対象としたアンケート調査*1 (2023年~2024年)に基づく5つの問題点を発表しました。
今年1月にスターバックスが紙ストローをやめて採用したバイオプラスチック製のストローは、「飲み心地の良さと、環境負荷低減を両立」すると謳っています。原料は植物油などを原料とする株式会社カネカの海洋分解性バイオポリマー「グリーンプラネット」。カネカは「海洋マイクロプラスチック問題の解決をはじめ、地球環境保全に貢献していくことで世界を健康にしていく」と宣伝していますが、グリーンプラネットの原料は、熱帯林破壊の主要な要因となっているパーム油です。
植物由来であることでCO2排出量を削減するとされていますが、パーム油生産によって東南アジアでは膨大なCO2が排出され、生物多様性にも壊滅的な影響が生じています。グリーンプラネットの使用は、これらの環境課題を覆い隠すグリーンウォッシュ(隠れたトレードオフ)にあたります。
詳しくは以下をご覧ください。
 https://jatan.org/archives/10919
https://jatan.org/archives/10919
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆フェアウッド・マガジン 世界のニュース登録方法を追加しました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
フェアウッド・パートナーズが、毎月、無料で配信している「フェアウッド・マガジン 世界のニュース」の登録・削除方法を追加しました。
これまでは、外部のメールマガジン配信サービス「まぐまぐ」のみとなっていましたが、フェアウッド・パートナーズからのダイレクト配信システムを加えました。いずれも無料ですので、以下からお好みの方法で登録してください。
 https://fairwood.jp/mailmagagine/16/
https://fairwood.jp/mailmagagine/16/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・みなさんの知人、友人、ご家族の方にもこのメールマガジンをお知らせしてください。メールマガジンの登録、バックナンバーはこちらです。
 https://fairwood.jp/worldnews/
https://fairwood.jp/worldnews/
・本メールマガジンの記事について、無断転載はご遠慮ください。
ただし、転載許可の表記のある場合を除きます。
・本メールマガジンに関するご意見・ご感想などは下記のEmailにお寄せください。お待ちしております。
e-mail: info@fairwood.jp
発 行 : フェアウッド・パートナーズ  http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp
編 集 : 坂本 有希/三柴 淳一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです
◎フェアウッド・マガジン-世界のニュース
の配信停止(unsubscribe)はこちら
⇒  https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=147706&e=sagaragef%40gmail.com&l=scj1851435
https://regist.mag2.com/reader/Magrddel?reg=unsubscribe_direct_footer&id=147706&e=sagaragef%40gmail.com&l=scj1851435
![]() http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp![]() https://news.mongabay.com/shor
https://news.mongabay.com/shor![]() https://www.earthsight.org.uk/
https://www.earthsight.org.uk/![]() https://www3.nhk.or.jp/news/ht
https://www3.nhk.or.jp/news/ht![]() https://news.yahoo.co.jp/artic
https://news.yahoo.co.jp/artic![]() https://www.newsweekjapan.jp/s
https://www.newsweekjapan.jp/s![]() https://news.mongabay.com/2025
https://news.mongabay.com/2025![]() https://www.nikkei.com/article
https://www.nikkei.com/article![]() https://news.yahoo.co.jp/artic
https://news.yahoo.co.jp/artic![]() https://www.nikkei.com/article
https://www.nikkei.com/article![]() https://www.nikkei.com/article
https://www.nikkei.com/article![]() https://yutosoken.com/wp/2025/
https://yutosoken.com/wp/2025/![]() https://www.nikkei.com/article
https://www.nikkei.com/article![]() https://www.niigata-nippo.co.j
https://www.niigata-nippo.co.j![]() https://www.chinatimber.org/ne
https://www.chinatimber.org/ne![]() https://www.chinatimber.org/ne
https://www.chinatimber.org/ne![]() https://fairwood.jp/event/2510
https://fairwood.jp/event/2510![]() https://fw251001.pea
https://fw251001.pea![]() http://www.fairwood.jp、info@fa
http://www.fairwood.jp、info@fa![]() http://www.foejapan.org、info@f
http://www.foejapan.org、info@f![]() https://fairwood.jp/event/2510
https://fairwood.jp/event/2510![]() http://www.foejapan.org、info@f
http://www.foejapan.org、info@f![]() http://www.fairwood.jp、info@fa
http://www.fairwood.jp、info@fa![]() https://bioenergyinfo.jp/
https://bioenergyinfo.jp/![]()
![]() https://www.gef.or.jp/news/in
https://www.gef.or.jp/news/in![]() https://jatan.org/archives/109
https://jatan.org/archives/109![]() https://jatan.org/archives/109
https://jatan.org/archives/109![]() https://fairwood.jp/mailmagagi
https://fairwood.jp/mailmagagi![]() https://fairwood.jp/worldnews/
https://fairwood.jp/worldnews/![]() http://www.fairwood.jp
http://www.fairwood.jp![]() https://regist.mag2.com/reader
https://regist.mag2.com/reader